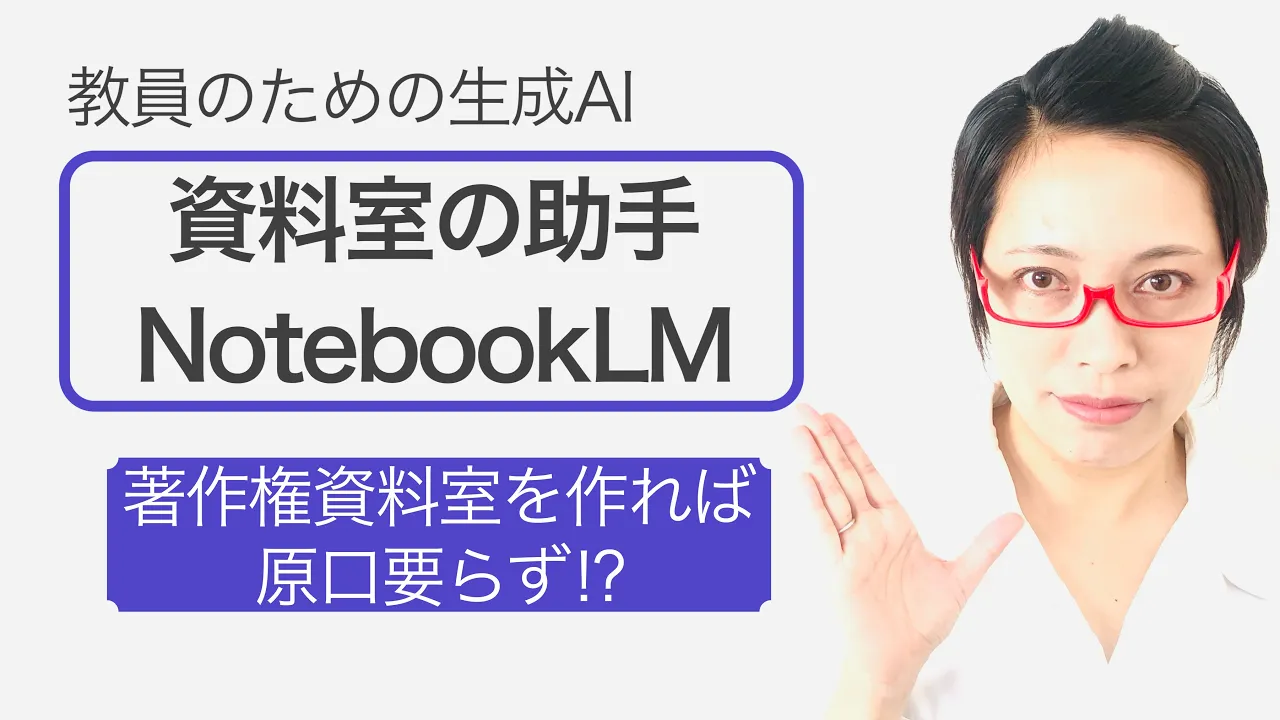皆さん、こんにちは。「一歩先ゆく音楽教育」の原口直です。
学校現場における生成AIの利用については、文部科学省の専用サイトが6月30日にスタートいたしました。ガイドラインの概要も出ていますので、そちらも合わせてご覧ください。

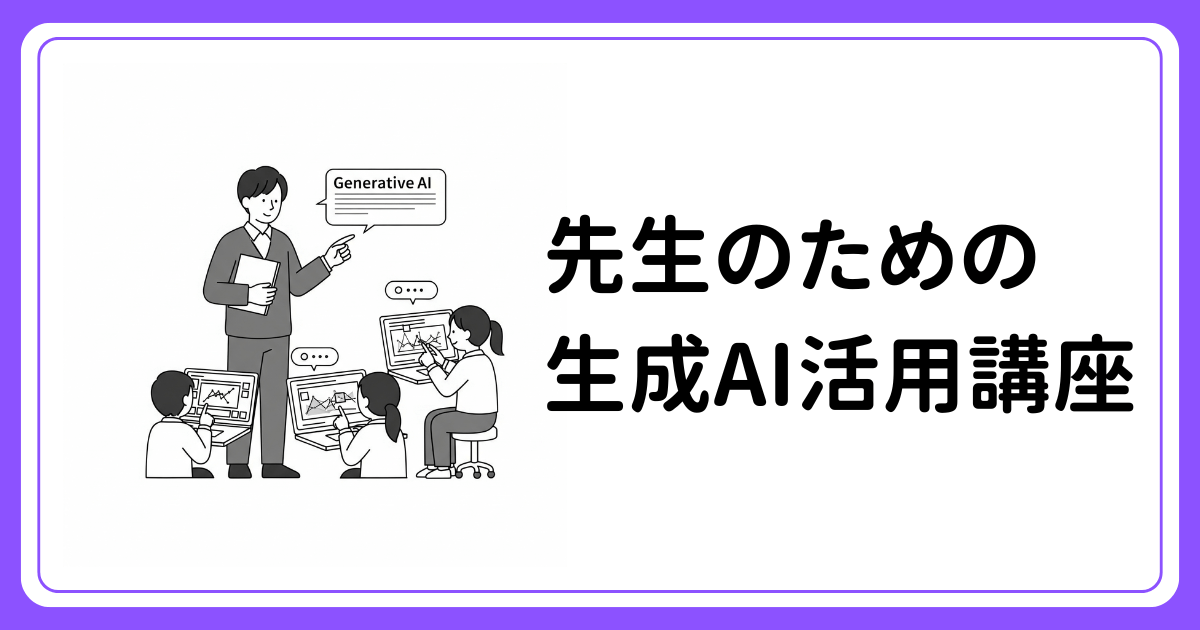
授業や校務で使える実践的な生成AI活用法を紹介。コピペして使えるプロンプトやリスク対策も含めて、生成AI初心者でも生成AIがすぐに使えるよう分かりやすく解説しています。
生成AIの「もっともらしい嘘」という不安
今回は「生成AI活用術 NotebookLM編」です。
前回の動画で、生成AIから質の高い答えを導き出す「魔法の呪文」プロンプトの作り方を紹介しました。
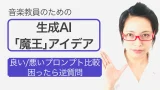
しかし、いくらプロンプトを工夫しても拭いきれない不安が1つありました。
それは、生成AIが最もらしい嘘をつく可能性がある、つまり、ハルシネーションのリスクです。生成AIの答えが正しいか、いちいち教科書や資料で裏付けを取るのは大変です。
【重要】生成AI利用にあたっての注意点
- 情報の鮮度: 生成AIは日々進化しており、精度、機能、利用規約が変わる可能性があります。常に最新情報を各自で確認するようにしてください。
- 解釈の多様性: 生成AIに関する考え方や受け取り方には個人差があります。本記事は理解を助けるための一資料であり、現場での運用方法は所属する学校や自治体の方針にも左右されます。必ずしも正解を提示するものではない点にご注意ください。
- ご自身の教育観との照合: 動画の内容は生成AIの可能性と課題を分かりやすく伝えることを目的としています。ご自身の教育観、教科の特性、児童生徒との関わり方を照らし合わせながら、活用方法を検討してみてください。
先生方の願いを叶える「NotebookLM」とは?
「もしAIが、自分が指定した資料の内容だけを読んで、その範囲の中で正確に答えてくれたら…」
そんな先生方の願いを叶えるツールが、今回ご紹介するGoogleの「ノートブックLM」です。
自分専用の「真面目な生成AIアシスタント」
ノートブックLMは一言で言うと、自分専用の資料室で働く「真面目な生成AIアシスタント」といったところです。
この記事をご覧いただくと、ハルシネーションのリスクを大幅に減らし、著作権の確認、校内規定のチェックといった「絶対に間違えられない業務」で、生成AIを安心して活用する方法が分かります。
本日の流れはこちらです。
- ノートブックLMって何がすごいの?
- ノートブックLMの基本的な使い方
- ノートブックLMの活用アイデア(教員のためのアイデア)
ノートブックLMって何がすごいの?
まず、ノートブックLMが先生・教員の仕事の何を変えるのか、その核心に迫っていきます。
一般的な生成AIとの違い
一般的なChatGPT、Google Gemini、Copilotといった生成AIは、インターネット上の膨大な情報を学習しています。
知識は広いですが、その分、不正確な情報や古い情報を基に、もっともらしい嘘をついてしまうことがあります。
最大のポイント:出典を明記する
一方、ノートブックLMは、あなたがアップロードした資料だけを知識の源泉とします。
そして、これが最大のポイントですが、ノートブックLMは回答を生成する際、必ず「どの資料のどの部分を根拠にした」という点を、引用元・出典を明記してくれるのです。
つまり、「知らないことは答えない」「答えの根拠が必ず分かる」。これは、正確性が何よりも求められる教員の仕事にとって、まさに理想的な生成AIと言えます。
ノートブックLMの基本的な使い方
次に、基本的な使い方です。使い方は非常に直感的です。
まず、ノートブックLMにアクセスをし、Googleアカウントでログインをします(ノートブックLMはGoogleのサービスです)。
ステップ1:ノートブックを作成します
新しいノートブックを作成します。これは、テーマごとに資料をまとめるための「本棚」や「ファイルボックス」のようなものです。
ステップ2:ソース・資料を追加していきます
そこに、ソース・資料を追加していきます。 生成AIに読み込ませたい資料、PDF、テキストのファイル、またGoogleドキュメントやウェブサイトのURLなどを直接読み込ませることができます。
ステップ3:質問をする
あとは、画面下のチャット欄から、読み込ませたい資料の内容について質問するだけです。
そうすると、生成AIが選んだ資料を読解して回答を生成してくれます。
ファクトチェックも一瞬でできます
そしてその回答には引用元の番号が振られており、クリック1つで資料の該当箇所にジャンプできます。これでファクトチェックも一瞬でできます。
【教員向け】ノートブックLMの活用アイデア
では、このノートブックLMを使って、教員のどんな悩みが解決できるのか、具体的な活用例を2つ見ていきましょう。
活用アイデア1:フリーイラストサイトの利用規約をチェックする
先生方のお悩みでとても多いのが、著作権のお悩みです。
「学級通信やスライドなどで『いらすとや』さんのイラストを使いたいが、この使い方は規約違反ではないか?」
「例えば、教材を他の先生に配布してもよいのだろうか?」
「毎回サイトで長文の規約を読むのは大変」
このようなお悩みに適した使い方です。
では実際に、ノートブックLMを使って「フリーイラストサイトの利用契約チェック」こちらのノートブックを作成します。
- 右上「新規作成」をクリックすると、「ソースをアップロード」という表示が出ます。
- 今回はフリーイラストの「いらすとや」さんを使用します。「ご利用について」のURLをコピーして、ウェブサイトに貼り付けをします。
- 「よくあるご質問」のURLもコピーして、URL貼り付けをします。
- 「学校での著作物の利用について」ということで、第35条の運用指針(サートラスのサイト)も2種類貼り付けます。
- 挿入を押します。
これで、これらの4つの資料の中で答えを導き出すように指定することができます。
「著作物の利用について」聞いてみます。
「いらすとやのイラストを5点使ったパワーポイントを、校内の他の先生に配布できるか?」これを聞いてみます。
紙飛行機のマークを押します。先ほど指定したソースの中からのみ答えを出すように指定されているため、これ以外の情報からは引用しないことになります。
すぐに答えが生成されるのも大きな利点です。
さらに、回答には「3」や「4」といった番号が付けられていますが、これは、引用元が記載されていることを示します。例えば「4」をクリックすると、「ソースガイド」が表示されます。「よくあるご質問」の中の該当部分を基に回答を生成した、ということが示されています。
そのため、どの部分が該当するかをすぐに確認できるため、疑問に思ったら元の資料に戻って確認できますし、「なぜ大丈夫なのか」と問われた際にも、「ここに記載があります」と他者に説明しやすい利点もあります。

活用アイデア2:複雑の著作権の問題を解消する
教員の皆さんからよく寄せられるお悩みについてです。
「例えば、文化祭の合唱で子供たちが好きなJ-POPの楽譜をクラスの人数分コピーしたいが、これは許可されるか?」
「オンライン授業で新聞の記事をカメラに写して使いたい」
このような著作権の悩みは判断が難しい上に、そのケースごとにたくさん出てきて尽きません。このような時も、ノートブックLMは非常に役立ちます。
では次に、「複雑な著作権の疑問」についてです。
まずはソースとして「文化庁の著作権テキスト」をアップロードしました。(※年度ごとに更新されるため、必ず該当年度のものであるか確認してアップロードしてください)
また、ノートブック作成後もソースは追加できます。「追加」ボタンを押して、先ほどの「第35条運用指針」や「追補版」も追加します。
後から追加することも可能なため、まず関連しそうな資料を入れた後に、さらに詳しい内容や付随する内容を加えていくことができます。
また、資料右側のチェックマークで分かるように、「今回はこの資料を使用しない」といった設定も可能です。これも便利な点です。
では、先ほどの「合唱の楽譜」について質問してみます。紙飛行機のマークを押します。
これは「文化庁の著作権テキスト」と「35条運用指針」2種類、ここから答えを導き出します。
結論から先に提示されます。結論と理由(1、2、3、4など)が示され、それぞれに引用元の番号が付けられています。それぞれ、どこを根拠にしているかが分かります。

聞きづらい質問も一時的な判断が自分でできる
これまで、専門家や管理職に確認が必要だった難しい問題、また「こんなことを聞いてもよいか」と心配だった点や、「初歩的すぎて恥ずかしい」と感じるような質問も、一時的な判断が自分でできるようになります。
その他のおすすめ資料
その他、教員が活用する際の資料アイデアとしては、学習指導要領やその解説を資料に入れておくと非常に便利です。
また、文部科学省が発表している資料、例えば生成AIの活用ガイドラインなども、このような資料を基に答えを導き出す「資料室」を作っておくと便利です。
まとめ:あなただけの「真面目なAIアシスタント」を
今回はGoogleノートブックLMについて解説しました。
ノートブックLMは、あなたが与えた資料だけを基に、出典を明記して答えてくれる、ハルシネーション(嘘)のリスクが低いAIツールです。
使い方は、「ノートブックを作成」「資料を追加」「質問する」の3ステップです。
利用規約の確認、著作権・校務分掌規定といった、正確性が重要な業務において絶大なパートナーになります。
利用時の注意点
ただし、個人情報や機密情報を含む資料はアップロードしないという基本は必ず守ってください。また、ハルシネーションが起こる確率は極めて低いものの、絶対ではない点にも注意してください。
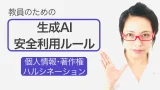
ご自身の担当教科の学習指導要領や学校の服務規定などを読み込ませて、「あなただけの真面目なAIアシスタント」を育ててみてください。
この記事は、動画「教員の「著作権」悩みをAIで解決!「嘘をつかない」NotebookLM活用ガイド|先生のための生成AI活用講座⑥」をもとに作成しました。