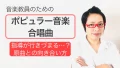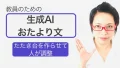「最近、ニュースや研修で『生成AI』という言葉をよく聞くけれど、正直何がすごいのかよくわからない…」
「なんだか難しそうだし、自分には関係ないかな…」
このように感じている先生方はいらっしゃいませんか?
あるいは、使ってみたい気持ちはあるものの、何から始めていいか分からず、一歩を踏み出せずにいる先生もいらっしゃるかもしれません。
この記事を読めば、そんな先生方のモヤモヤはすっきり解消。生成AIの基本から、今日すぐに始められる具体的な一歩まで、分かりやすくご紹介します。情報担当の先生方が、他の先生方にこの便利さを伝える際のヒントとしてもご活用いただけます。
校務が少しでも楽になる、その記念すべき一歩を一緒に踏み出しましょう。
◆はじめに:生成AIに関する情報の取り扱いについて
この記事をご活用いただくにあたり、以下の点にご留意ください。
- 情報の鮮度について
この記事は、元となる動画の公開時点の情報に基づいています。生成AIは日々進化しており、精度、機能、利用規約が変わる可能性があります。ご自身で最新の情報を確認するようにしてください。 - 解釈の多様性について
生成AIに関する考え方や受け取り方には個人差があります。この記事は一つの理解のための資料であり、必ずしも唯一の正解を提示するものではありません。現場での運用方法は、所属する学校や自治体の方針にも左右されます。 - ご自身の教育観との照らし合わせ
この記事は、生成AIの可能性と課題を分かりやすく伝えることを目的としています。ご自身の教育観や教科の特性、児童生徒との関わり方を踏まえながら、活用方法を考えてみてください。
なお、学校現場における生成AIの利用については、文部科学省の専用サイトが6月30日にスタートし、ガイドラインの概要も公開されています。ぜひそちらもあわせてご覧ください。


そもそも生成AIって何?
難しく考える必要は一切ありません。
生成AIとは、一言でいえば『あなたのリクエストに応じて、人間のように自然な文章やアイデアを返してくれる、非常に賢いアシスタント』です。
学校における「賢いアシスタント」としての役割
学校には、副担任の先生、チームティーチャー、アシスタントティーチャー、支援員の方、スクールサポーターなど、先生方を助けてくれる様々な人たちがいます。生成AIも、それと同じような存在と考えることができます。
特に、生成AIは文章の作成・要約・アイデア出しが非常に得意です。
なぜ教員の役に立つのか?
先生方の日々の業務には、学級通信の作成、授業の準備、研修報告書の作成といった、文章を作ったりアイデアを考えたりする作業がとても多く含まれます。
この部分をAIに少し手伝ってもらうことで、先生方はもっと大切な「子どもたちと向き合う時間」や「教材研究を深める時間」に集中できるようになります。これが、生成AIを活用する大きなメリットです。
今日から使える!無料の生成AIツール
実は、生成AIは特別な機材がなくても、先生方が普段お使いのGIGA端末やスマートフォンで無料で始めることができます。
代表的なツールには、「ChatGPT」「Google Gemini」「Microsoft Copilot」などがあります。今回は、多くの先生が使い慣れているGoogleアカウントですぐに始められる「Google Gemini」を例に紹介いたします。
まずは無料ツールで気軽に試し、「生成AIってこんな感じなんだ」と知ることが何よりも大切です。操作に慣れ、ご自身の業務で「これは使える」と感じたら、さらに高機能な有料版を検討するというステップで十分です。

最初の一歩:アカウント作成から最初の質問まで
Google Geminiにアクセスする
まずはブラウザで「Google Gemini」と検索します。検索結果の一番上に出てくる公式サイトを開いてください。ダイヤモンドマークが目印です。
もしログインを求められたら、いつもお使いのGoogleアカウントでログインすれば準備完了です。本当にこれだけで、とても簡単です。
最初の質問をしてみよう【体験が重要】
ログインが済んだら、早速最初の質問をしてみましょう。画面の下の方にある入力欄に、お願いしたいことを入力します。怖がらず、難しく考えず、普段誰かに話しかけるような言葉で大丈夫です。
【質問例】
「小学校3年生向けの学級通信で使える夏休みの過ごし方についての前向きな挨拶文を考えてください」
入力したら、右下の「送信」ボタンを押します。
すると、すぐさま学級通信の冒頭に使えるような文章が生成されます。
この「お願いしたら本当に答えが返ってくる」という経験こそが、生成AIの「難しそう」というイメージをぐっと下げてくれます。この小さな成功体験が、次のステップに進むための大きな自信になるのです。
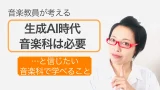
まとめ:まずは触れてみることが大切
今回は、教員のための生成AI超入門として、以下の3つのポイントをお伝えしました。
- 生成AIは「賢いアシスタント」であること。
- GIGA端末などを使い、無料で今すぐに始められること。
- まずは簡単な質問を投げかけ、答えてくれる体験をしてみること。
いかがでしたでしょうか。なんだか自分でも使えそうな気がしてきませんか?
もちろん、最初から完璧な答えが返ってくるわけではありませんし、生成AIの答えが全て正しいわけでもありません。それで良いのです。
まずは、ご紹介したように簡単な挨拶文を考えてもらうなど、本当にちょっとしたことからで大丈夫です。とにかく触ってみて、「こんなこともできるんだ」と感じてもらうことが、何よりも大切な一歩になります。
情報担当の先生は、まずご自身で試された後、ぜひ同僚の先生方にもこの『最初の質問』を体験してもらう場を設けてみてはいかがでしょうか。この記事を読み終えたら、ぜひすぐに試してみてください。
この記事は、動画「【5分でわかる】先生のための生成AI入門|「難しそう」はもう卒業!」をもとに作成しました。