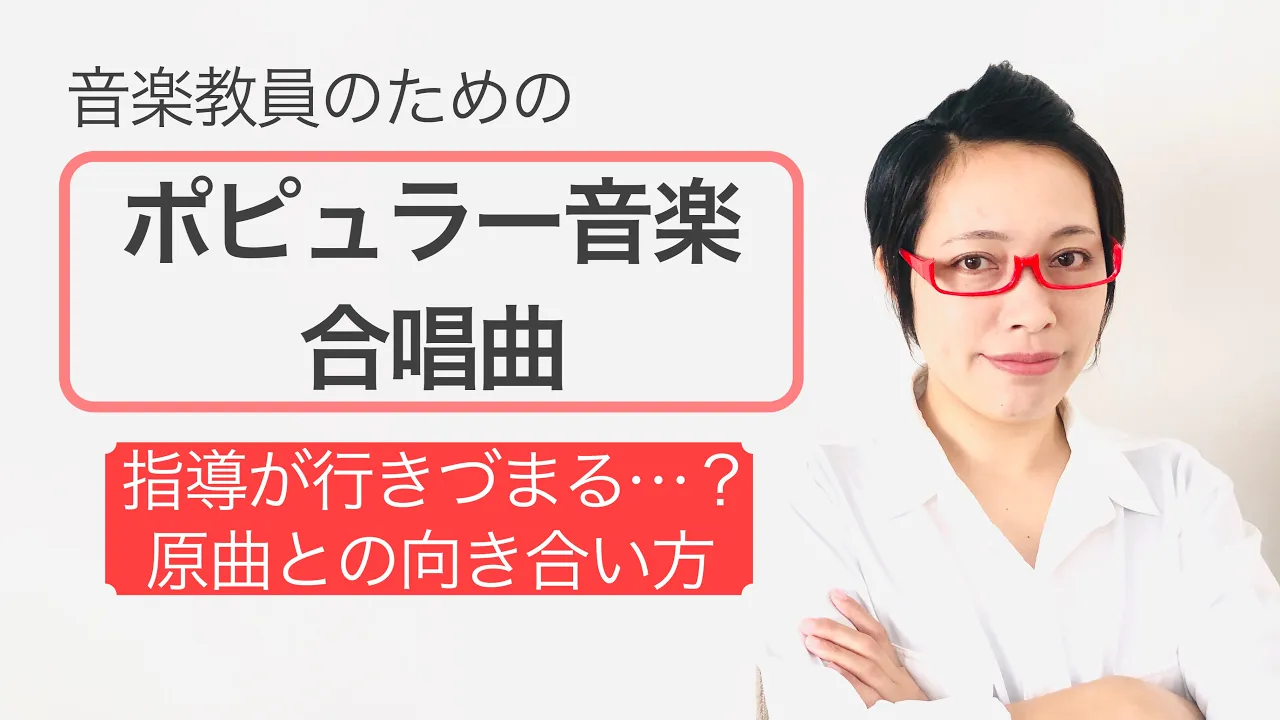今回は「Jポップ合唱曲指導のコツ」についてお話しします。
子供たちに「普段聞いている音楽は?」と尋ねると、ポピュラー音楽、アニメソング、ボーカロイドなど多彩なジャンルが挙がります。
先生方自身も、クラシック音楽を好む方もいれば、オペラに触れる機会が少ない方もいらっしゃるでしょう。クラシック音楽を専門的に学ぶと、他のジャンルに対する偏見を抱きがちですが、どのジャンルにも固有の魅力と価値が存在します。
ポピュラー音楽を授業に取り入れるために
私も学生時代はクラシック中心でしたが、社会人になり音楽関連企業に勤めたことで、ライブハウスやクラブに足を運び、ポピュラー音楽の広がりを実感するようになりました。
別の動画「ポピュラー音楽を教材にした音楽の授業のやり方」では、授業に流行を取り入れる方法として、YouTube、JASRAC賞、グラミー賞、音楽フェス、そして子供たちに直接流行を尋ねることを紹介しました。また、教科書でのポピュラー音楽の扱いや、常時活動・研究授業での実践についても触れています。
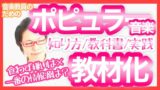
音楽の授業でポピュラー音楽を扱う代表例が「合唱」です。
NHK全国学校音楽コンクール(Nコン)の中学校課題曲では、毎年のようにポピュラー音楽をベースにした楽曲が選ばれています。校内合唱コンクールや授業でも、生徒からのリクエストを受けてポピュラー音楽を元にした合唱曲を取り上げることが増えています。
原曲を知ることから始めよう
私は声楽専攻で合唱を愛しており、学生時代はNコンをはじめとする合唱コンクールに情熱を注ぎました。教員になってからも社会人合唱団で活動し、全国大会で4年連続1位を獲得した経験もあります。そんな私がポピュラー音楽を元にした合唱曲を扱う際に大切にしていることをお伝えします。
この記事は、「ポピュラー音楽が苦手」「通常の合唱曲と何が違うの?」「指導が行き詰まる」と感じる方に向けた内容です。
まず大切なのは「原曲を知る」こと。
生徒も教員も、合唱曲の原曲を好きになることから始めましょう。
歌詞を自分ごと化する
ポピュラー音楽の魅力は、日常や感情に即したリアルな言葉にあります。
そのため、歌詞を「自分ごと化」し、誰かの話ではなく「自分にも当てはまるかも」と感じられるようにすることが重要です。例えば次のような問いかけを通して、生徒に考えさせましょう:
- 「この歌詞は何歳の誰がどんな状況で言っていると思いますか?」
- 「これって何年生の時にあった、あのことに似ていない?」
- 「この部分を最近の出来事と重ねて読んでみよう」
ワークシートやグループ活動を通して取り組むと効果的です。
アーティストへの関心を促す
多くの生徒は、課題曲を「授業の曲」として捉えがちですが、原曲の歌唱やライブ映像、ミュージックビデオ、アーティストのインタビューや楽曲制作の背景などを紹介することで、「この人かっこいい」「こんな風に歌いたい」といった興味を引き出せます。
まずは先生方が原曲やアーティストについてしっかり知ることが重要です。他の教材と同様に、Jポップの合唱曲でも丁寧な導入を心がけましょう。

合唱曲としての違いを理解する
ポピュラー音楽を元にした合唱曲は、従来の合唱曲とは異なる特徴を持っています。
以下の3点に着目した指導が求められます。

リズム感の強調
シンコペーション、裏拍、ビート感などが重要になります。
指導の工夫として、手拍子や体でリズムをとる練習、メトロノームの併用などが効果的です。リズムに乗る楽しさを体験させることで、拍感を育てましょう。
旋律重視の構成
ポピュラー音楽では、主旋律が際立つ構成が多く、ハーモニーは補助的な役割です。主旋律の魅力を引き立てるために、以下のような指導を行いましょう:
- ピアノを使わずにパート同士で聴き合う
- 主旋律をリレー形式で歌う
- ハモリパートの役割を意識させる
世界観への共感と解釈
歌詞が現代的で生徒の実感に近いことから、共感がモチベーションに繋がります。
歌詞の一文一文に立ち止まり、「自分ならどう感じる?」と問いかけたり、原曲の背景や解釈を紹介することで、生徒の考えを引き出しましょう。
指導の行き詰まりを防ぐために
ポピュラー音楽の合唱曲は、音楽的要素がシンプルで原曲のイメージが強く、早期に「やりきった感」が出やすいため、指導が行き詰まりやすい傾向にあります。
以下の3つの対策を取り入れてみてください。
音楽の解像度を上げる
表面的には歌えていても、感情の解釈やニュアンスのバリエーションを深掘りする指導を行いましょう。
- 「2番は1番と同じって思ってない?でも言葉が違うよね」
- 「息継ぎの位置、自然な文章になっているかな?」
- 「同じメロディでも意味は違うよね。表情はどう変える?」
このような声かけを通じて、楽曲の情報密度を高めていきましょう。
別軸の活動を取り入れる
歌うだけでなく、視点・技能・感覚を変える活動を導入することで、多様な関わり方を提供し、生徒の主体性を引き出します。
- 原曲にハモリをつけてみる(iPadやガレージバンドなどを使用)
- 歌詞の続き(2番の歌詞など)を考える
- グループで立ち位置や演出プラン、歌い出し担当などを話し合う
- 各自が異なるフレーズに感情メモを記入し、グループで発表する
比較対象を活用する
他の楽曲と比較することで、曲を多面的に捉え、音楽的視野を広げることができます。
- 同じ作曲者の別の合唱曲と比較して、作風や共通点・違いを探る
- 昭和歌謡、洋楽、伝統音楽と比較し、五感や旋律、強弱の違いを体感する
- 原曲と合唱版を聴き比べて、良さや物足りなさについて議論する
原曲があるからこそ可能な比較活動を活用してみてください。
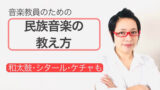
おわりに
今回は、ポピュラー音楽を元にした合唱曲の指導についてお話ししました。
私自身、ポピュラー音楽も合唱曲も好きですが、それらを掛け合わせた指導にはかつて苦手意識がありました。しかし今では、「ポピュラー音楽だからこそできる合唱指導」があると感じています。
ぜひ皆さんも、原曲を聴き、アーティストを好きになることから始めて、ポピュラー音楽の合唱曲をどのように教材化するか、自分なりの考えをもって指導に取り組んでみてください。
この記事は動画「ポピュラー音楽×合唱 指導の極意:原曲理解から応用まで徹底解説!」をもとに作成しました。