今日は教育実習の実習日誌についてお話しします。
教育実習はやることがたくさんあります。もちろん教科の需要も大事ですけれども、それ以外にも学校の生活・学級の様子・先生方の指導を見たりする。そんなことも教育実習の醍醐味です。
先生方の動きはもちろん、どのように働いていらっしゃるのか、また生徒・子どもの動きもとても勉強になるところです。また生徒の関わり方も机上では絶対にできない実習の醍醐味の1つです。
教育実習では、併せてそれらを実習日誌にまとめるというのがあります。
1回の実習で1冊の実習日誌を毎日書きます。大学によって実習日誌の様式は違いますけれども、だいたい同じような「実習の記録をとる」というものがあると思います。実習日誌は大変重要なものではありますけれども、負担にもなるというところもあります。
今回は1年間150人以上の教育実習生を受け入れ、教科では6年間で50人以上の教育実習生を見てきた…つまり教科の実習生の実習日誌を山ほど見てきた私が実習日誌の意義、そして書き方について教えしたいと思います。
この記事は、次のようなことを知りたい方に是非ご覧頂きたい内容です。
▶初めての実習で、初めて実習日誌を書くという方
▶実習日誌を書くための下準備を知りたいという方
▶実習日誌に書いてはいけないこととは何か?ということを知りたい方
ほかには、
授業はもちろんのこと、実習前に必要なメイクや身だしなみ・心構えの話。また事後のお礼状の話なんていうのもしていますので併せてご覧下さい。
音楽科の皆さんに向けて「授業の内容を解説」「学生の専攻別にアドバイス」の動画をまとめています。
「【10年以上前の教育実習】教育実習日誌をただ読む①3年次・大学附属高校」
「【10年以上前の教育実習】教育実習日誌をただ読む②4年次・母校高校」
実習日誌でやってはいけない3つのこと
ここでは3つ紹介したいと思います。実習日誌は、
記録じゃない!
感想じゃない!
実習日誌は日記ではない
「今日は○○をして楽しかった」「○○を見て勉強になった」――こうした日記風の記述は避けましょう。
実習日誌は、ただの感想文ではなく、教育実習で得た学びを言語化し、深く掘り下げる場です。見たことや感じたことをただ綴るのではなく、そこから何を考えたかが大切です。
実習日誌は記録ではない
授業の流れや板書、発問、児童の反応、パワーポイントの使い方などの記録は、自分用のノートにまとめましょう。
日誌には、記録そのものを書くのではなく、記録を元に何を感じ、何を考察したかを記載することが求められます。記録は参考資料であり、日誌そのものには不要です。
実習日誌は感想ではない
「面白かった」「参考になった」といった感想も、実習日誌には不適切です。そうした感想は個人のノートに書き留めましょう。
実習日誌に書くべきは、指導教員との対話に繋がるような、具体的な考察や提案です。
実習日誌に書くべき3つのこと
ここでも3つ提言します。
・本音を書く
・提案を書く
この3つです。
考察を書く
考察は検討したことや分析をした結果という意味です。
授業や学級経営、教師や児童生徒の様子を観察したうえで、「なぜそうしたのか」「なぜそうならなかったのか」といった検討や分析を行いましょう。
見たことをそのまま書くのではなく、深く考えることが求められます。
考察をするためには検討・分析が必要です。
本音を書く
協議会や振り返りでは言いにくいこと、他の実習生には話せないこと、また他の教員には伝えづらいことも、実習日誌には書いてかまいません。
指導教員との信頼関係を築き、率直な思いを伝える手段として活用しましょう。「ここが良くないと感じた」「こうすべきでは」といった自分の意見を記しておくことが大切です。
提案を書く
書くべきことは考察・本音・提案です。
「自分ならこうする」「次回はこうしたい」といった提案を積極的に書きましょう。
授業を見学した際だけでなく、自分が授業をしたときにも「次にどう活かすか」を考えることが、実践的な学びに繋がります。
また、実習日誌は指導教員からコメントが返ってきます。
私がたくさんの実習生の日誌を毎日見てきて「読み応えがあるな」とか「実習をきちんと自分の経験にしているな」とか「現場に出た時に生かせるような実習日誌になっているな」と感じるのはこういった点でした。
実習日誌を毎日書くために必要な力
毎日だから必要になる力は、
・文章力
・瞬発力
だと思います。
語彙力
誤字脱字を防ぐためにも、語彙を増やし、教育用語を正しく理解することが必要です。横文字の流行語ではなく、定番かつ基本的な教育用語や教科特有の表現に精通しておきましょう。
多くの学校では、実習日誌をボールペンや万年筆で記入し、修正液の使用を禁じています。下書きなしで一気に書き上げるには、日頃から頭の中で文章を構成する練習が不可欠です。
文章力
限られた文字数(大学によって異なりますが、目安は300〜400字)で、起承転結のあるまとまった文章を書く力が求められます。
新聞の社説や記事を読むなどして、簡潔に自分の主張をまとめる練習をしておくと効果的です。
瞬発力
日誌はその日のうちに書くものです。実習の出来事を「ホットなうちに」考察・提案としてまとめられるよう、瞬発力を意識しましょう。
大学の授業や論文執筆のように時間をかけられるわけではないため、その場で感じたことをすぐに思考・整理し、文章に起こす瞬発力が求められます。
思考を整理し、限られた文字数で的確に伝える練習を日頃からしておきましょう。
まとめ:【指導教員が解説】教育実習の実習日誌の書き方
今日は実習日誌についてお話をしました。
実習日誌は、単なる提出物ではなく、将来の自分へのメッセージです。実習後も読み返したくなるような内容を心がけて、教育実習の経験をより深い学びに変えていきましょう。
私自身、これまで数々の引っ越しを経験し、多くのものを断捨離してきましたが、実習日誌だけはどうしても手放せませんでした。それほど大切なものだからこそ、「考察・本音・提案」の詰まった、社会人・教員になったときにも読み返したくなるような実習日誌を、ぜひ毎日丁寧に綴ってみてください。
記事の内容は動画と同じです。
YouTubeチャンネルの「【教育実習】実習日誌の正しい書き方|書いてはいけない3つ×書くべき3つを指導教員が解説!」の動画をご覧ください。




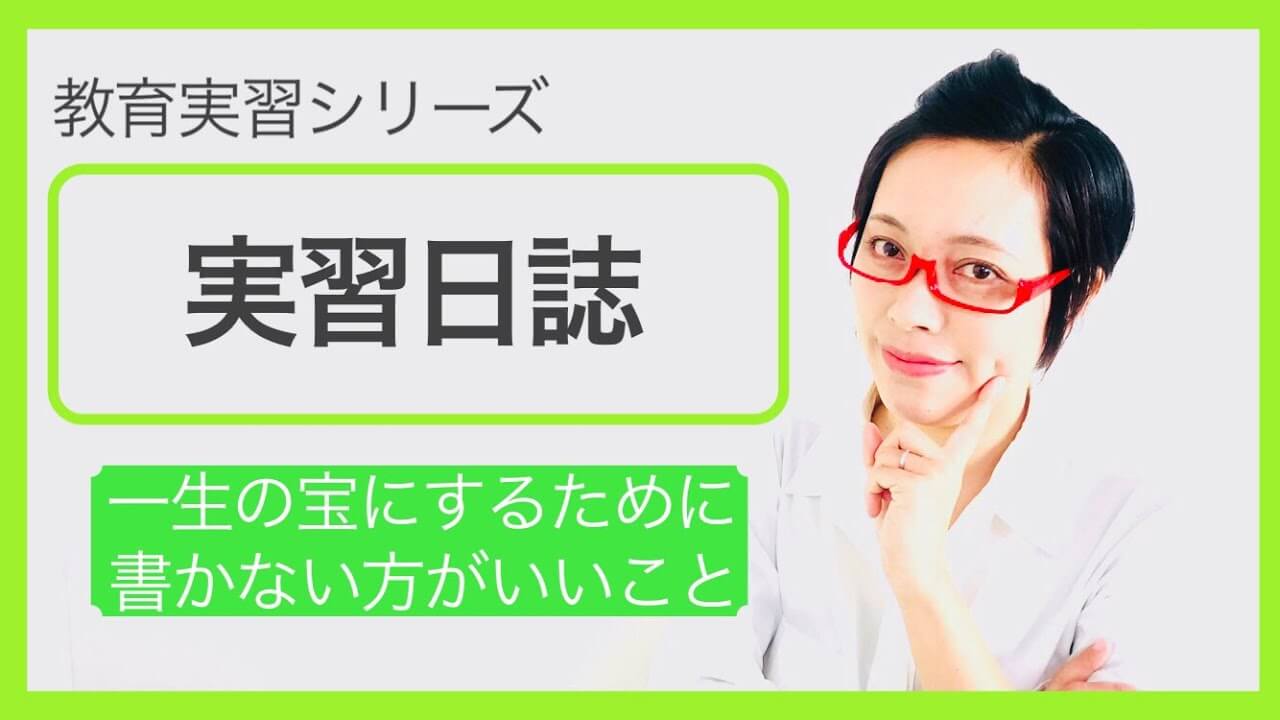
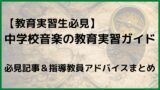








コメント