学校での教育研究の経験と、未来につながる新しい学びについて情報発信しています。
このYouTubeチャンネル「原口直の一歩先ゆく音楽教育」では学び続ける先生と学生さんのために、学校で役立つ情報と提案を発信しています。
今日は「教育実習レポート」についてお話しします。学校によりますが「教育実習を終えて」「報告レポート」という名称のようです。分量や提出先もまちまちです。
教育実習中に毎日書く日誌とは別の「教育実習レポート」。書く際に気を付ける点や、実習日誌と同じ部分・違う部分はどこでしょうか。
今回は1年間150人以上の教育実習生を受け入れ、教科では6年間で50人以上の教育実習生を見てきた私が教育実習レポートの意義・書き方を解説します。
この記事は、次のようなことを知りたい方にご覧頂きたい内容です。
▶初めての教育実習で初めてレポートを書くという方
▶教育実習レポートを書くために必要な下準備を知りたいという方
▶実習日誌と教育実習レポートの違いは何かを知りたい方
この動画の他には
実習日誌は日記・記録・感想文ではない。ならば、何を書くべきか?そのためにどのような力をつけておけばいいかという具体的な話をしています。
授業そのものについてはもちろんのこと、メイクや身だしなみ・心構えの話・終わってからのお礼状の話もしていますので、併せてご覧ください。
も参考になると思います。ご覧ください。
教育実習レポートと実習日誌との違い
書き方を考える前に、実習日誌と教育実習レポートの違いから整理しましょう。
読者が異なる
読む相手が違います。
教育実習レポート→読者は大学の教育実習やゼミの教員(長期的には自分自身)
実習日誌を読む指導教員は、学校で同じ場面を共有し、授業について議論をしています。なので、詳細な描写を書く必要はありません。
一方、教育実習レポートはその場にいなかった人が読むものです。なので、授業の内容(場面や子どもの様子、関係性など)も書く必要があります。
こうなるとレポートの方が容量が増えます。日誌の中から書くポイントをしぼりましょう。しぼり方は後ほど話します。
読む相手の特性も考えます。
日誌を読む指導教員は学校現場、レポートを読む大学教員や担当者は研究の現場にいます。持っている語彙も違えば、優先事項・理念や考えも異なります。
「教育について熱心に考えている」という意味では変わらないのですが、置かれている環境や道のりが異なります。この2つの立場の違いを実習の中で感じることでしょう。それぞれの特性をとらえて、レポートを書きましょう。
教育実習レポートを書く時の注意点
注意点として、実習日誌は提出後にしばらく本人の手元に戻ってこないということです。
学校によるのかもしれません。私が実習を担当していた頃は日誌を実習校に提出した後に大学経由で戻ってくるので、数週間から数か月かかっていたと思います。
その間に教育実習レポートを提出しなければならない場合、日誌の内容を思い出さなければならないのでメモや写真に撮っておくといいと思います。
「【10年以上前の教育実習】教育実習日誌をただ読む①3年次・大学附属高校」
「【10年以上前の教育実習】教育実習日誌をただ読む②4年次・母校高校」
教育実習レポートと実習日誌の共通点
実習日誌の書き方解説の動画「【指導教員が解説】教育実習の実習日誌の書き方」では、「日記じゃない」「記録じゃない」「感想じゃない」と説明しています。この点は実習レポートも同じです。
実習日誌は「何を見た。楽しかった」という日記ではない。
「どのような発問だった」「パワーポイントだった」という記録ではない。
「勉強になった」「参考にしたい」という感想文ではない。
ということです。
続けて、実習日誌に書くべきこととして「考察」「本音」「提案」と述べています。この点も実習レポートと同じです。
起きた事柄ではなく、検討・分析をした考察を書く。研究協議会や授業の振り返りでは言い切れなかったことや、そこからさらに考えた本音を書く。そして、「自分ならこうする」「次あったらこうする」という提案を書くことです。
実習レポートも同様で、読み応えのある文章を書くためには、自分の経験から書けること・自分しか書けないことを書きましょう。
教育実習レポートの構成例
自分しか書けないこととは何か。
レポート書くためには様々な手法がありますが、自分しか書けない文章を書くために「ミクロ・マクロの視点」で書くことを提案します。
マクロは森のイメージ・マクロはその森を構成する木というイメージです。
ミクロの視点
自身の教育実習数週間の中で、1つの場面や思いを切り取ります。
「1時間の授業」「1人の子どもとの関わり」「授業での1場面」「1枚のワークシート」「子どもから言われた一言」など。
最も印象的だった部分…それは希望でなく絶望でもいいのですが…そこを鮮明に、考察・本音・提案を交えながら書いていきましょう。
読み手にとって、その場を見ていなくても場面や思いが伝わってくるような文章です。
マクロの視点
レポートの中では、「教育の未来」「教員という職業」「我が国における教育」といった大きなテーマについて考察・本音・提案を交えながら書くと良いでしょう。
現場に行ったからこそ分かったこと、そして実習中は目の前のことで手いっぱいになってしまうかもしれませんので、実習を終えたあと冷静になって考えたことを書くと日誌とは違う視点と熱量を持った文章が書けると思います。
まとめ:【教育実習を終えて】教育実習レポートの書き方(実習日誌との違い・共通点とは?)
今日は「教育実習を終えて」レポートの書き方についてお話ししました。
教育実習の最終日は「始まり」です。
「大学に戻ってから何をするか?何を考えるか?」が、本当の教育実習の意義です。教育実習では、たくさんの「お土産」を指導教員または子どもから渡されます。
教員として不足している知識や技能、特に音楽科として不足している知識や技能を知ることができます。
他方で自分が得意な事や他の人が優れている点にも気づくことができます。
教育実習レポートを書く際に冷静に実習を振り返って、実習から実感した課題に向き合うきっかけにしましょう。
音楽科の皆さんに向けて「授業の内容を解説」「学生の専攻別にアドバイス」の動画をまとめています。
この記事の内容は動画と同じです。
YouTubeチャンネルの「【教育実習を終えて】教育実習レポートの書き方(実習日誌との違い・共通点とは?)」の動画をご覧ください。




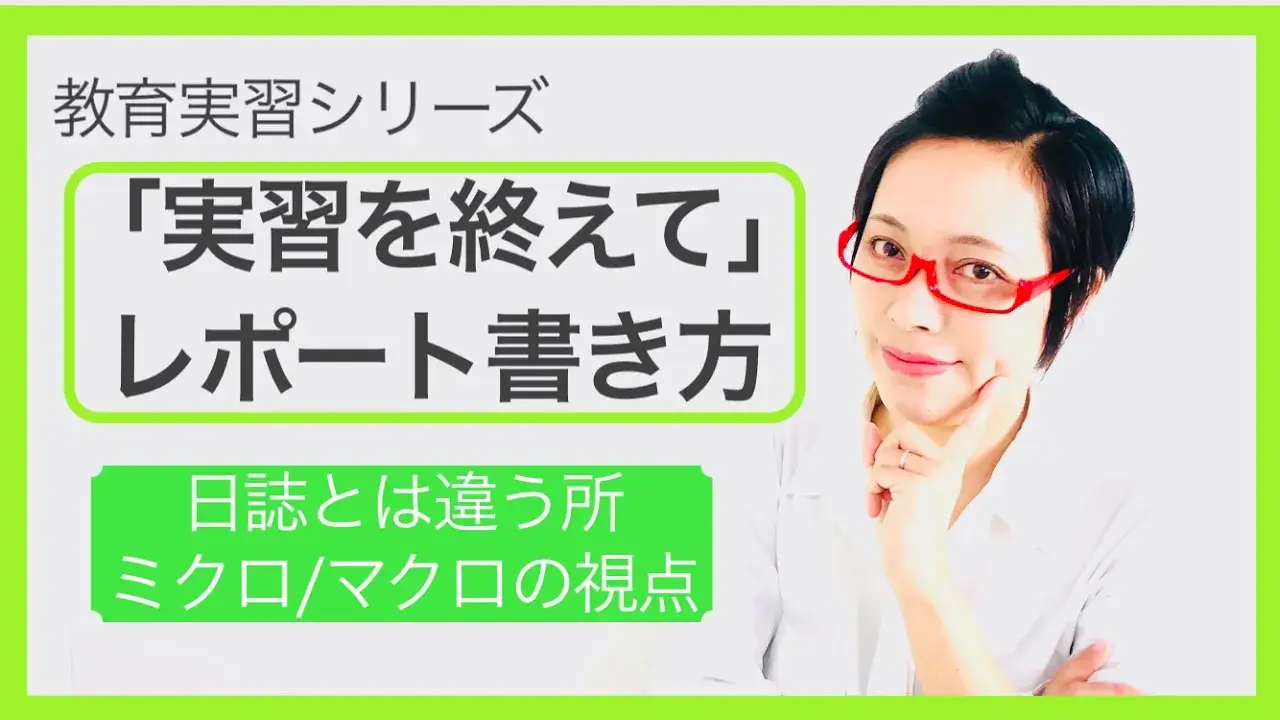
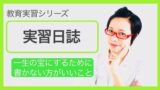



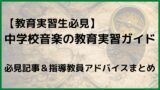


コメント