今回は「合唱指導の基礎の基礎」についてお話しします。
合唱指導は、音楽教育において避けて通れない重要な領域です。特にピアノ専攻の方は、これまで伴奏の経験が中心で、自身が合唱に参加したことが少ない場合も多く、指導に不安を感じがちです。教育実習生にもそのような傾向が見られます。また、出身校によって合唱への意欲やレベルには大きな差があります。
市販の指導書や雑誌、DVDなどは多数ありますが、今回はそれらの前段階として「基礎の基礎」に焦点を当てて解説します。この内容を押さえれば、どの校種・学年でも活用できます。
なお合唱については、再生リスト「教育実習シリーズ」の中で専攻別【ピアノ専攻】【声楽専攻】【管弦打専攻】【音楽教育・音楽学・作曲専攻】の専攻別に解説をしています。是非そちらもご参照ください。
【教員を目指す人へ】ピアノ専攻の皆さんへ送るアドバイス
【教員を目指す人へ】声楽専攻の皆さんへ送るアドバイス
【教員を目指す人へ】管・弦・打楽器専攻の皆さんへ送るアドバイス
【教員を目指す人へ】音楽教育・音楽学・作曲などを専攻する皆さんへ送るアドバイス
また行事運営についての動画もあり、そちらでも合唱について話をしています。
準備:自ら体験し理解する
合唱指導における第一歩は、教員自身が体験を通して合唱曲を理解することです。
全パートを自分で歌う
ソルフェージュ力があっても、実際に声に出して歌うことで、生徒がつまずきやすい箇所が把握できます。
特に女性教員は、男性パートを地声で歌うのか、オクターブ上げるのかなどの調整が必要です。
ノンヴィブラートでの練習
声楽専攻の方は、独唱でビブラートを使う癖があるかもしれませんが、合唱では正確で聞き取りやすい発声が求められます。
ノンヴィブラートで歌う練習をしておきましょう。
伴奏を自分で弾いてみる
ピアノが苦手な方でも、伴奏の見本音源を繰り返し聴いて準備をしましょう。
子どもたちは時に音やリズムを間違えて演奏します。指導者自身が正確に理解していれば、それらの間違いにすぐに気づき、正せるようになります。
手順:明確な段取りで指導する
音取りを含む合唱指導では、手順が非常に重要です。
目的の提示
音程を正確に取る、強弱を意識する、子音を明確に発音するなど、歌う前にその回の目的を生徒に明示します。
これが後の評価にもつながります。
開始位置の指示
練習番号、ページ、小節、段など、楽譜上の開始位置を正確に伝えます。
開始音の提示
毎回丁寧に開始音を出すことが大切です。
絶対音感を持つ人や器楽専攻の人にとっては省略しがちなので注意が必要です。
開始音の上げ方
主音など取りやすい音をパートに関係なく取らせてから、順に複雑な音に進みます。
生徒の発達段階や実力に応じて方法を工夫しましょう。
入り方の指導
歌唱では音の出だしよりも、息を吸う(プレス)タイミングが重要です。
これを明示的に教えることが必要です。
カウントの統一
例として6/8拍子では、
- 「1 2 3 4 5 6」
- 「1 2 3 / 2 2 3」
- 「1 2」
などの方法があります。
どの方法でも構いませんが、必ず毎回同じ方法でカウントし、生徒が混乱しないようにします。
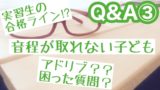
評価の一致
目的が音程であれば音程について、強弱であれば強弱について評価します。
目的と異なる観点で評価をしてしまうと、生徒は戸惑い、モチベーションが下がってしまいます。
指揮者を立てる:クラス練習を見据えた指導
合唱における指揮者の位置づけを明確にすることは、クラスでの自主的な練習を促すうえでも重要です。
指揮者の権威を認める
音楽科教員が「指揮者は絶対的な存在」と明言し、その姿勢を生徒に示します。
演奏後のコメントは指揮者から
指導者が真っ先に評価を述べるのではなく、まず指揮者に意見を求めましょう。
その後、教員が補足説明や課題の追加を行います。
役割の尊重を授業で定着させる
指揮者は授業外の練習でも中心的な存在になります。
他教科で異なる役割を持つ生徒でも、音楽の授業では指揮者としての役割が尊重されるように、授業の中でその位置づけを徹底します。
おわりに
今回は「合唱指導の基礎の基礎」として、次の3つのポイントを紹介しました。
- 準備:教員自身が全パートを歌い、伴奏も確認する。
- 手順:目的の明示から評価まで一貫した段取りを行う。
- 指揮者を立てる:合唱におけるリーダーを明確に位置づける。
発展的な発声練習やエチュード、歌詞解釈などについては、書籍やDVDを参考にしてください。優れた実践例も豊富にありますが、まずは基礎を固めることが最も大切です。
合唱指導に自信を持てれば、担任の先生や保護者からも信頼され、より良い音楽教育が実現できます。
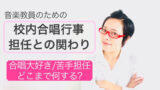
この記事は動画「【合唱指導の基本】授業とコンクールに効く!全学年対応3つの鉄則」をもとに作成しました。







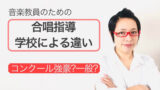


コメント