今回は、学校によって異なる合唱指導の違いについてお話しします。
学校にはそれぞれ独自の文化やカラーがあり、隣の学校の常識が通用しないこともしばしばあります。特に文化祭や合唱コンクールといった文化的行事では、その違いが顕著に現れます。
初めて教員として赴任する際や異動の際、学校を選ぶことはできません。しかし、学校ごとに異なる合唱の文化を知ることはとても重要です。
今回は、私自身が体験した中学校・高校(Nコンで県代表になってブロック大会に進むぐらい、かなり合唱に力を入れている中学校・高校でした)と勤務先中学校(さほどコンクールに力を入れていたわけではありません)での違いについてお伝えします。
なお、合唱指導についての動画「10分でわかる!合唱指導の3つのポイント|全学年対応の簡単コンクール対策」や、文化的行事の運営に関する動画「教員のための学校行事運営の3つのコツ(合唱コンクール・合唱祭・文化祭)」も別途ありますので、ぜひご参照ください。
学校による合唱指導の違い1:ソルフェージュ力
まず一つ目はソルフェージュ力です。
ピアノを習っている子が多いか少ないかということではなく、譜読みや覚えるスピード、耳で覚えて口で表現するルーティンができているかどうかが大きな違いになります。

さらに、先輩たちの合唱を聴いてその曲を知っているということも重要なポイントです。パート練習が生徒だけで運営できる環境も大きな強みになります。
ソルフェージュ力のある生徒や、ピアノや楽器を習っている生徒がいると、その子たちが主導してパート練習を進めてくれます。その結果、教員はパート練習に深く関わる必要がなくなり、より広く合唱全体に関わったり、できない子へのバックアップに専念したりと、異なる立場から指導が可能になります。
ソルフェージュ力は合唱指導における大きな強みとなります。
学校による合唱指導の違い2:声
次に二つ目は声です。
合唱に本気で取り組み、良い声を出すことが当たり前となっている環境では、後輩たちも自然と育っていきます。
良い先輩の見本が近くにいることが非常に有効です。たとえば、女性教員が男性パートを指導するのは難しい面がありますが、優れた先輩の声が良い見本となることで、「あの声を目指そう」「あのような声になりたい」と具体的な目標を持つことができます。
また、声を出すこと自体が当たり前の環境では、教員は「声を出しましょう」という指導ではなく、既に出ている声をどう良くしていくかに集中できます。その結果、合唱曲の仕上がりや目標の水準が大きく変わってきます。
声に関する状況は学校ごとに大きな違いがあります。
学校による合唱指導の違い3:校風
三つ目は校風です。
歌唱や合唱が学校内でどのような位置づけにあるかは、合唱指導に直結します。日常的に歌がある学校や、合唱コンクール以外の行事にも歌唱の場がある学校では、合唱指導が非常にしやすい環境となります。
私自身が中学生の頃、週1回の朝礼で各学級の合唱発表があり、発表した曲を最後に全員で歌うという文化がありました。そのため、歌うことに対する抵抗感がなく、先輩たちの合唱を身近に感じることができました。
高校は音楽科の高校だったため、日常的に合唱があり、年間スケジュールもコンクールを前提に組まれていました。その結果、学校全体が合唱・音楽を認めているという風潮がありました。
校風は、学校における合唱の位置づけや文化を大きく左右し、それが指導のしやすさにも影響を与えます。
まとめ
今回は、学校による合唱指導の違いについてお話ししました。
特に公立学校では先生の異動も多いため、担当する先生がどのように合唱を位置づけたいかによって学校のカラーが大きく変わります。
初めはやりにくさを感じる部分があるかもしれませんが、自分のカラーや目指す方向性を強く打ち出すことが、学校全体や音楽科の授業にとって非常に良い影響をもたらします。
ぜひ、今回の内容を参考に、それぞれの学校の環境に応じた合唱指導を進めていただければと思います。
この記事の内容は、動画「学校によってこんなに違う!合唱指導「3つのリアルな違い」を体験から解説」をもとに作成しました。




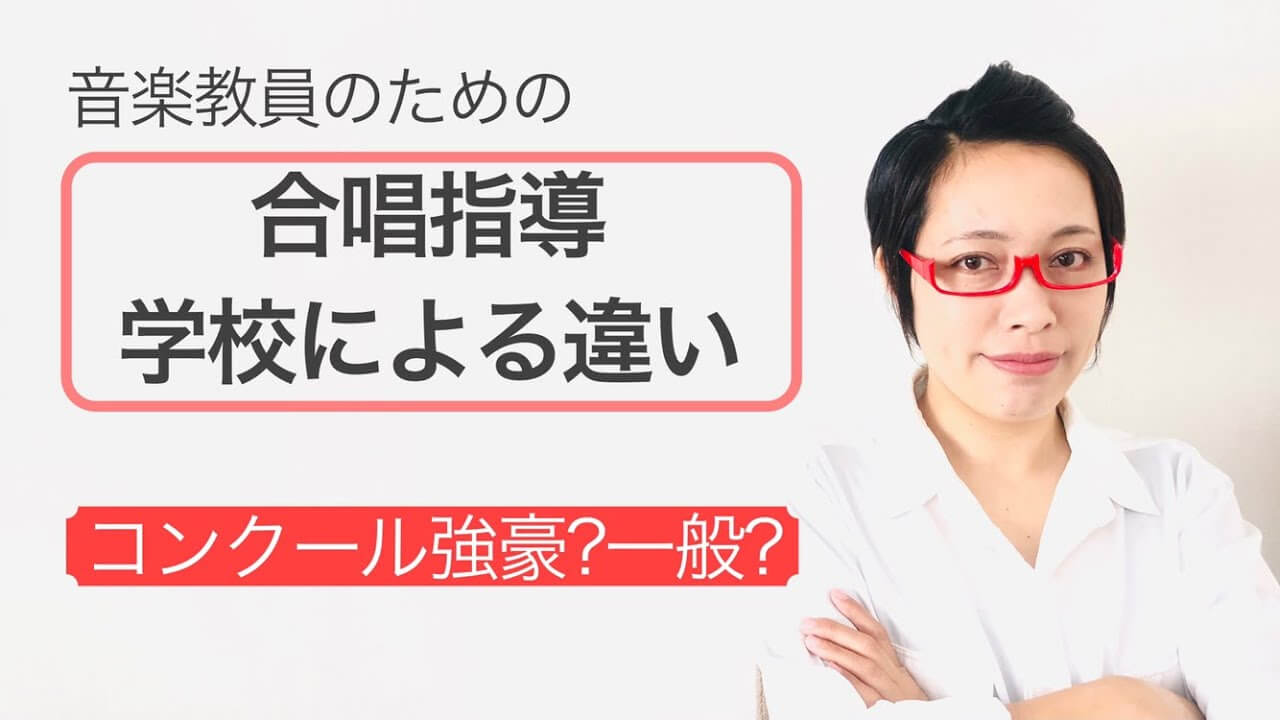








コメント