こんにちは。一歩先ゆく音楽教育、原口直です。学校での教育研究の経験を活かし、未来につながる新しい学びについて情報発信をしています。
この記事では、学校で実施される「歌のテスト」について、教育的な位置づけや評価方法、さらには生徒や保護者が抱える不安を解消するポイントを解説します。
「音痴だから成績が下がるのでは」といった悩みや、カラオケの点数と学校の評価基準の違いが気になる方に向けて、実際の評価基準や工夫した事例もご紹介します。
この記事は、次のようなことを知りたい方に是非ご覧頂きたい内容です。
▶歌のテストは苦手という方
▶何で歌のテストをするの?と思っている方
▶カラオケの点数と学校の歌テストの点数は何が違うの?と疑問に思う方。
この動画の他には
観点を伝えるタイミング・評価の時間を確保するタイムマネジメント・記録を取る理由などを話した動画があります。
入学式や卒業式、合唱コンクールなど学校行事、他から借りる楽器やアウトリーチ講師の予定などに左右される音楽科の年間指導計画の立て方について話しています。
併せてごらんください。
学校での歌テスト:その位置づけと評価のポイント
歌のテストについて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?
最近ではカラオケで点数が出たり、点数を競う音楽番組が人気ですが、学校での歌テストはそれらとは大きく異なるものです。
学校での歌のテストは、教育活動の一環として行われるもので、その目的や意義は評価方法にも反映されています。私は音楽科教員として歌のテストを実施してきました。その経験をもとに、歌のテストの位置づけや評価のポイントについてお話しします。
学校の歌テストで評価されるポイント
歌のテストは、単に「人前で歌う」経験ではなく、学習指導要領に基づいた学びの評価の一部です。評価の観点として、声の大きさや歌詞の正確さ、旋律やリズムの正しさなどが挙げられますが、これらは学校や教員の裁量によって工夫されています。
例えば、私は1年生の校歌テストで、以下のポイントに基づいて評価を行いました:
・声の大きさ
・歌詞の正確さ
・旋律やリズムの評価は省略
これは、変声期や羞恥心、緊張感といった要因を考慮し、生徒が安心してテストに取り組めるよう配慮したものです。
保護者の心配と現実
「音痴だから音楽の成績が下がるのでは?」と心配される保護者の声を耳にすることがあります。しかし、歌のテストだけで成績に大きく影響することはあまりありません。歌唱以外にもワークシートや発表など多様な評価方法が取り入れられており、生徒一人ひとりの努力や成長が評価されます。
歌のテストは、音楽科の評価方法の一つであり、実は必ずしも実施が義務付けられているものではありません。教育の中での位置づけを正しく理解し、適切に活用することが重要です。
新学習指導要領による評価基準の変更点
中学校では2021年度から学習指導要領が改訂され、評価の観点が大きく変わりました。この変更により、音楽科を含む全ての教科で、評価方法がより生徒の学びを深めるものへと進化しています。
新しい評価の観点
2020年度までの評価観点は4つでしたが、2021年度から以下の3つに統一されました:
・知識・技能
・思考・判断・表現
・主体的に取り組む態度
これにより、音楽科でも「単なる知識や技能の確認」だけでなく、生徒が自ら考え、表現し、主体的に学びに向き合う姿勢が重視されるようになりました。
教職員支援機構の解説動画
新学習指導要領に基づいた評価基準については、教職員支援機構(NITS)の動画で詳細に解説されています。この動画は次の4つの内容で構成されており、歌のテストにおける評価方法にも役立つ情報が含まれています:
・新学習指導要領に対応した学習評価
・学習評価の進め方
・「指導と評価の一体化」のポイント
・生徒への働きかけの例
「『指導と評価の一体化』のポイント」において演奏の評価(歌のテストの評価)について触れられています。
音楽科での評価方法の工夫
音楽科では、歌のテストをはじめとしたさまざまな評価方法が取り入れられています。例えば、以下のような方法が挙げられます:
・演奏(歌唱や器楽)
・作品(創作活動)
・ワークシートやノートの記録
・グループでの話し合い、発表、自己評価・相互評価
・ポートフォリオ(学習活動の記録)
これらの方法を通じて、多角的に生徒の学びを評価することが可能です。
新しい評価基準は、生徒の多様な学びを支えるための仕組みとして設計されています。歌のテストを含む音楽科の評価方法も、この観点に基づいて柔軟に運用されています。
評価方法の工夫と私の実践例
歌のテストは、多くの生徒にとって緊張する場面です。特に「音痴だから成績が悪くなるのでは」と心配する生徒や保護者の声を耳にすることもあります。
しかし、歌のテストは必ずしも歌唱力だけを評価するものではありません。その実施方法や評価基準を工夫することで、苦手な生徒にも配慮した評価が可能です。
苦手意識を軽減する指導のポイント
音楽科として評価を付ける際には、評価基準を事前に明示し、生徒が見通しを立てられるようにすることも大切です。評価の仕組みを理解することで、生徒自身がテストへの不安を和らげ、前向きに取り組むことができます。
歌のテストは頻繁に行われるものではありませんが、生徒の努力や成長を引き出すための貴重な機会です。評価方法を工夫し、苦手な生徒に配慮することで、音楽教育の質をさらに向上させることができます。

私の実践例
歌のテストを含む音楽科の評価では、生徒一人ひとりの努力や成長をしっかりと捉えることが重要です。そのために評価方法を工夫し、生徒が安心して学びに取り組める環境を整えることを心がけています。ここでは、私が実践してきた評価の工夫について紹介します。
多様な評価方法の活用
私が行っていた評価では、「演奏」「作品」「ノート」「ワークシート」「発表」「話し合いでの発言」など、さまざまな方法を組み合わせていました。これにより、生徒の学びを多角的に評価することが可能になります。
評価基準の明示とバランスの取れた設定
評価の基準を事前に生徒に示すことで、見通しを持って学習に取り組めるようにしています。また、評価の「重みづけ」についても工夫を凝らしました。
・他の項目で挽回できる仕組みを導入。
・学期ごとではなく年間を通じたバランスを考慮。
これにより、生徒が苦手分野を補う機会を得られると同時に、長期的な学びの成果を適切に評価できるようにしています。
私の実践例:校歌のテスト
1年生の校歌の歌テストでは、「声の大きさ」「歌詞の正確さ」を評価ポイントとしました。
旋律やリズムの正確さは評価対象外とすることで、変声期や羞恥心を抱える生徒にも配慮しました。これにより、音楽への苦手意識を和らげ、生徒が安心して取り組める環境を作ることができました。
まとめ:歌のテストの可能性
歌のテストの位置づけや評価について解説しました。
教科が定めている校種・学年の目標、評価方法・構造については、公表されています。
目標は文部科学省のサイトや書店で入手できる「学習指導要領」で確認できます。
評価の方法は今回紹介した教職員支援機構の動画や資料があります。これは国立教育政策研究所が公表している「「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料」が基となっています。
音楽科に限らず、どんなことがどのように評価されているのか知りたい場合は、気になる校種や教科について確認してみましょう。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「歌のテストが不安な人必見!音楽教員が教える評価方法と学習指導要領のポイント」も是非ご覧ください。




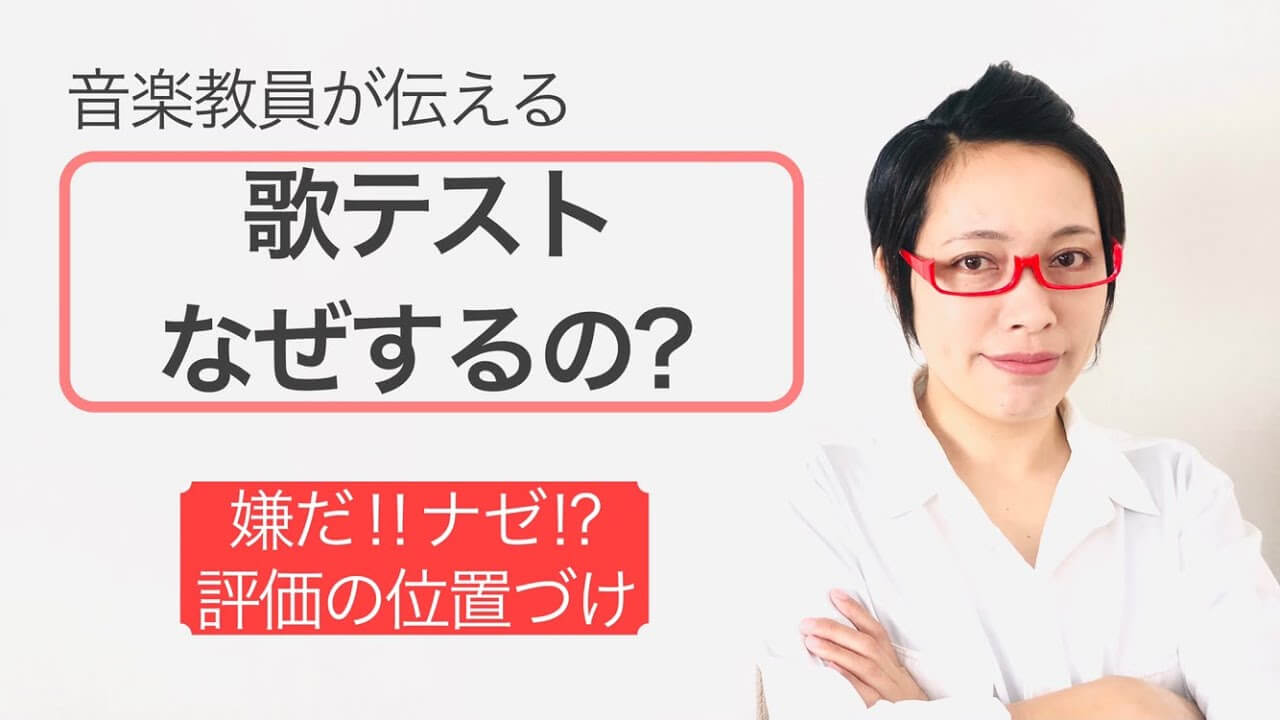


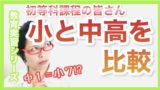


コメント