今日は「授業規律」について話をします。
「【1年間が劇的に変わる】初回授業のガイダンス&アンケート3つの鉄則」でも触れましたが、授業規律は非常に大事です。今後の音楽の授業がうまくいくかどうかは、どのように授業規律を設定し、それを生徒と共有するかにかかっています。

今回は、その授業規律をどのように作っていくかについてお話しします。
授業前の環境づくりと準備

授業規律は授業前から始まっています。
教室が規律を守る場であると示すには、椅子や譜面台、隊形の掲示などを整えることが大切です。隊形がわからない、椅子が並んでいないといった状態では、チャイムと同時に授業を始めるという規律も守られません。これは生徒のせいではなく、教員の責任です。
椅子を生徒の人数分きちんと整頓し、チャイム着席を徹底させましょう。チャイムに遅刻した生徒には厳しく叱り、二度と遅れさせないようにします。小さなほころびがやがて大きなキズ口となるため、始めが肝心です。
4月・5月中は、何度でもやり直させ、注意を繰り返すことが大切です。
授業中の基本的な規律
授業中は、まず挨拶を徹底させます。そして、私語についての規律も初めに提示することが必要です。
私語は「雑音」と捉え、音楽室には不要なものであると繰り返し伝えます。耳にタコができるほど、言う方が呆れて疲れるくらい、4月・5月の段階で徹底することが大事です。
対応として、「静かに」「うるさい」ではなく、「雑音やめて」「雑音なし」と言うほか、「口を閉じて」「耳を貸して」「こっちを見て」など、生徒に具体的な行動を伝えることが有効です。また、「shhhh」と音を出したり、私語が収まるまで無言で待つ、「喋りたいです」「しゃべります」「大事なことを言います」と宣言するなど、様々な工夫も取り入れましょう。

楽譜・楽器の扱いと授業規律
楽譜や楽器の扱いに関しても、初めに徹底しておく必要があります。
楽譜を粗末に扱わない、なくす、床に置く、丸めて人を叩くといったことを防ぐために、「楽譜はとても尊い、大切なものだ」と伝えましょう。誰か一人が不適切な行動をした時には、その場で楽譜の大切さについて話すのも良い方法です。
楽器も同様に、尊く大切なものです。
「楽器を大切に扱いましょう」と言いながら、先生のピアノの上が荷物でいっぱいでは説得力がありません。教員自身が態度で示すことが大切です。マレットやスティックを投げる、人を叩くといった行動があった時には授業を止めて全員を注目させ、「これはダメなことだ」と断言しましょう。
言葉遣い・身体の動きに関する規律
授業中の言葉遣いも重要です。
誰かの発言や歌、演奏に対して汚い言葉や罵る言葉を使う生徒がいれば、授業を止めて「その言葉はよくない」「聞いて心地よくない」と説諭することが大事です。
また、音楽の授業では立つ・座る・動くといった行動が他教科より多いため、ルールや目的を明確に共有する必要があります。
立つべき時に立たない、座るべき時に座らない場合には、それまで待つという徹底が必要です。
歌うべき時に歌わない、楽器の手を止めるべき時に止めないなども、初期段階から決して許さない姿勢を持ちましょう。
ルールを明確に示し、「あなたはこのルールを破ったから私は怒っている」と伝えることが重要です。ルールがなければ、生徒はなぜ怒られているのか分かりません。
授業後のフォローと報告
授業規律で最後に忘れてはいけないのが、授業後の生徒へのフォローです。
特に強く注意した生徒や、注意しても改善しなかった場合には、後で呼んで一対一で話をしましょう。
初めに提示したルールを再確認し、「このルールを破ったから注意をした」「こう直せば注意はしない、楽しい授業になる」というように、最後は必ずポジティブな話で終えるようにします。短い休み時間では声かけだけでも行い、後で時間を取って話をしましょう。次の授業にわだかまりを残さないように、最後まできちんとフォローすることが授業規律を守らせるコツです。
また、クラス担任の先生への報告も忘れてはいけません。
「今日音楽の授業でこのようなことをしたので、このような指導をしました」「これから指導をします」「こういうことに困っているかもしれません」などと伝えましょう。
改善された点があれば、それも併せて報告します。
担任の先生から「他の授業でもそう」「あの子にはこうすると分かりやすい」といったアドバイスをもらえることもありますし、音楽の授業だけでの態度なのか、他の教科でも同様なのか、また女の先生にだけその態度を取るのかなど、傾向が分かります。
怖がらず、「悪いなあ」と思わず、必ず担任の先生に伝えることが大切です。場合によっては管理職や保護者への連絡にもつながるかもしれません。落ちのないように必ず伝えておきましょう。
おわりに
今回は授業規律についてお話ししました。
私は女性で背も小さく、週に1回しか生徒と会わないため、なかなかすぐに信頼を得ることは難しいです。だからこそ、規律をきちんと作り、「ダメなものはダメ」「良い時はとっても褒める」という姿勢を持つことで、信頼関係を築いていけると思います。
この記事は動画「【4月が勝負】中学校音楽の授業規律づくり完全ガイド|信頼関係の土台を築く方法」をもとに作成しています。




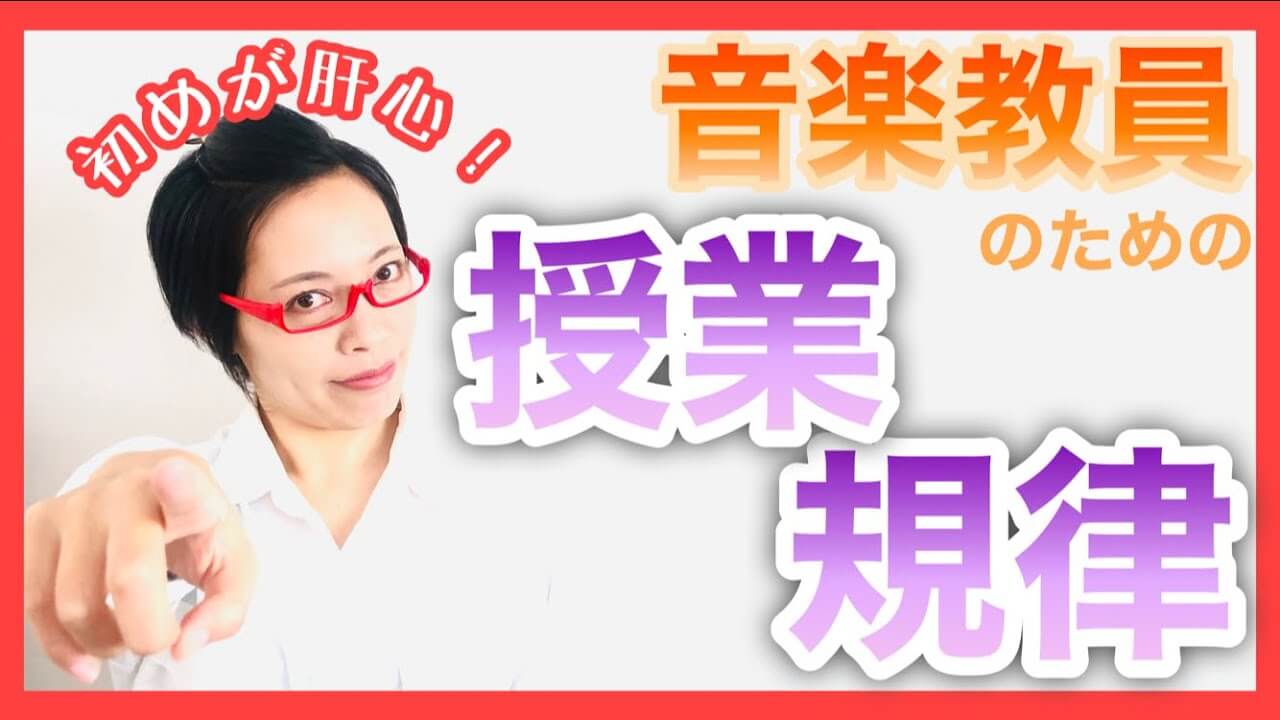








コメント
よくYouTubeでは拝見していましたが、コメントははじめてします。
とくに、ポップスの授業での展開についての動画、とても良かったです、
もしよかったら、先生とはまた違う教材、視点から授業に参考になる動画をだしているので、こちらにも遊びにいらしてください
https://youtu.be/gg08aywT6sI
古賀先生
コメントをいただき、ありがとうございます。
ポピュラー音楽については、先生方の興味関心の度合いや自身の体験、リスペクトする姿勢が大きく関わると感じています。
どのような実践をなさっているか興味があります。