今回は「校歌の指導」についてお話しします。
校歌は学校の象徴であり、年度当初には必ず指導が必要となる楽曲です。しかし、その指導が事務的になってはいないでしょうか。
式典や行事のためだけでなく、音楽的にも校歌をしっかり捉えて指導するにはどうすればよいかを、3つの視点から考えてみましょう。
作者や制作背景を明らかにする
校歌の指導でまず大切にしたいのは、「作った人を明らかにして大切にする」ことです。これは、私が重視している7つの項目のうちのひとつでもあります。

校歌についても同じで、作者が誰なのか、どのような経緯で作られたのかを明らかにすることで、生徒たちに学校への愛校心や曲への愛着が自然と芽生えてくると考えています。
まずは、校歌の成り立ちや制作者について、生徒たちと一緒に一度共有してみてください。
目標を明確にする
次に大切なのは、「目標を明確にする」ことです。
すなわち、校歌を披露する“本番”がいつなのかをはっきりさせることで、生徒たちのやる気がぐんと高まります。
例えば、学校によっては昼礼や朝礼で歌うことがあるかもしれません。春に運動会がある学校では、それを目標にするのもよいでしょう。また、1学期の終業式をゴールに設定する学校もあるでしょう。
「いつまでにここまで仕上げる」といった明確な目標があると、教員と生徒双方が努力しやすくなります。「その日までに歌詞を完璧に覚えよう」「暗譜をしよう」といった具体的な目標を立てることで、校歌への取り組みに対する意欲も高まっていくはずです。
音楽性を重視する
三つ目のポイントは、「音楽性を忘れない」ことです。
校歌を歌う場面では、つい事務的になりがちです。行事や式典、歌のテストのために歌うことが目的になってしまい、結果として無感情な“棒歌い”になってしまうケースもあります。
それを防ぐためには、子音をはっきり発音する、強弱を丁寧につけるなど、音楽的な工夫を忘れないことが大切です。他の合唱曲と同様に、校歌にも毎回しっかりと音楽性を込めて歌ってほしいと私は考えています。
このことは伴奏にも当てはまります。教員や生徒が何度も伴奏を繰り返していると、次第に指や口が“勝手に動く”状態、つまり事務的な演奏になりがちです。
そうしたときは、一度初心に立ち返りましょう。強弱記号を改めて見直したり、アナリーゼをしたりして、校歌のどこに音楽性があるのかを意識し直すことが大切です。一つひとつの演奏を丁寧に取り扱うよう心がけてください。
まとめ:校歌指導の再確認を
今回は、「校歌の指導」について3つの観点から考えてみました。
長年同じ学校に勤務していると、何度も、あるいは何百回と校歌を演奏することになり、どうしても作業的になってしまいがちです。しかし、校歌は立派な音楽作品ですし、新1年生にとってはその学校を象徴する、誇らしい音楽であるはずです。
だからこそ、音楽の先生自身が飽きずに、定期的に校歌の指導方法を見直すことが大切です。それが、生徒の心に届く校歌指導への第一歩となるのではないでしょうか。
この記事は動画「校歌指導の極意|「心に届く歌」を育てる3つの視点【音楽教員向け】」をもとに作成しました。









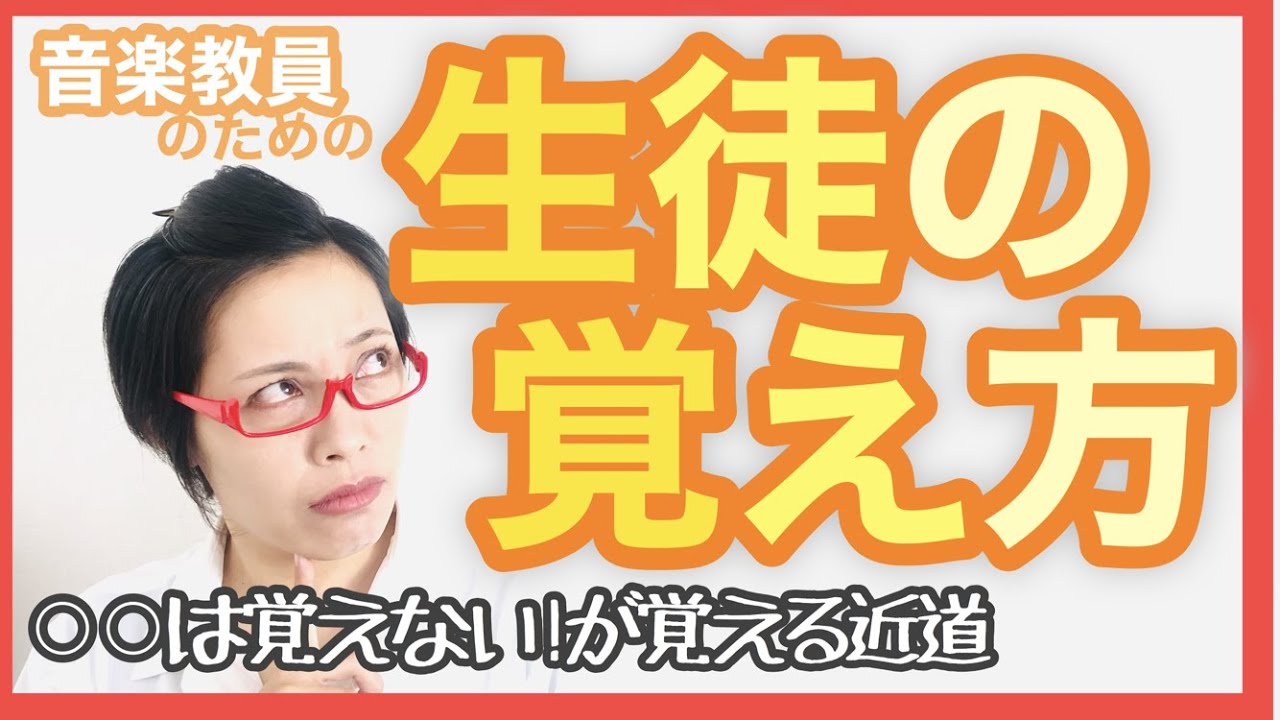
コメント