卒業式(卒業証書授与式)は、入学式と並び、学校の顔となる非常に重要な儀式です。在校生や保護者、来賓の方々など、学校規模によっては500人から1000人もの人々が集まります。これは、さながらコンサートホールに匹敵するキャパシティです。
その中で音楽科は、式の雰囲気を創り出す重要な役割を担います。子どもたちや保護者、そしてご自身の心にも残る一日を演出するために、丁寧な準備で本番に臨みましょう。
この記事では、卒業式を失敗なく、そして心配なく迎えるための準備のヒントを、5つのポイントに分けて具体的にお伝えします。
本記事の内容は、入学式の準備と重なる部分も多くあります。ぜひ関連する「【音楽教員の入学式】ピアノ・服装・BGM、何から準備する?新任・若手の不安を解消!」も併せてご覧ください
また行事運営という観点では以下の動画・記事もおすすめします。
行事運営としての「合唱行事に関わるやり方」というのもお話ししています。
併せてごらんください。
最も重要な音楽「校歌」指導のポイント
儀式的な行事において、校歌は最も重要な音楽といえます。卒業生にとっては最後の校歌となり、在校生にとっても卒業生と一緒に歌える最後の機会です。この1回の校歌が持つ意味をしっかり伝え、音楽に取り組ませることが大切です。
練習時間の把握
まず、卒業生と在校生、それぞれの練習時間を把握しましょう。特に、体育館で合同練習が何回できるのか、事前に確認しておくことが重要です。
多くの場合、予行練習が初めて全員で合わせる場となるため、それまでに在校生への指導と卒業生の仕上げをそれぞれ完了させておく必要があります。
「最後の校歌」というストーリー
いつも歌っている校歌の延長ではなく、「この1回が最後である」というストーリーを伝え、その重要性を生徒たちに理解してもらうことが、心を込めた斉唱につながります。
入退場曲から式歌まで|校歌以外の音楽準備
卒業式で演奏される音楽は校歌だけではありません。入退場曲や合唱曲など、すべてに気を配り準備を進めましょう。
入退場の音楽
入退場曲がCDなのか、ブラスバンドなどによる生演奏なのかを把握します。CDを使用する場合、その選曲担当が音楽科なのか、学年なのか、あるいは放送委員会なのかも確認しておきましょう。
「蛍の光」「仰げば尊し」の指導
学校によっては、「蛍の光」や「仰げば尊し」を歌う場合があります。しかし、この2曲は知らない生徒が非常に多いのが現状です。小学校で歌わなかったケースがほとんどのため、もし歌うのであれば早めに取り組むことをお勧めします。
特に、2曲とも歌詞が非常に難解です。歌詞の背景や言葉の意味を深く指導するために、国語科の先生に協力を仰ぐのも効果的です。
合唱曲の指導
「旅立ちの日に」や「大地讃頌」、あるいは「筑後川」の「河口」といった合唱曲を歌う学校もあるでしょう。卒業式での合唱は、これまでの練習の集大成であり、披露の場です。
より印象的な合唱にするためには、通常の指導に加え、以下のような卒業式ならではの指導を取り入れましょう。
- 当日は感極まって泣いてしまうことを前提とした練習
- 「別れ」や「新たな出会い」といったテーマと結びつけた歌詞の解釈
会場の特性を「音楽的視点」で再確認
ほとんどの学校では、自校の体育館や講堂で卒業式が行われます。普段から慣れている場所ですが、改めて「音楽をする」という観点で会場を見直してみましょう。
空間と響きの確認
体育館の広さ、奥行き、天井の高さなどを確認します。また、舞台の有無、階段の位置、ピアノの設置場所(舞台の上か下かなど)も学校によって様々です。
本番の環境をイメージする
当日は、卒業生、在校生、保護者、来賓など多くの人が会場に入ります。さらに、紅白幕などの飾り付けも行われるでしょう。これらの要素によって、普段の音の響き方とは変わる可能性があります。人が増え、布が増えることで音がどう変化するのか、事前にイメージしておくことが重要です。
伴奏用ピアノの事前チェックリスト
校歌などの伴奏を弾く場合、ピアノの準備は必須です。生徒が弾く場合も、ご自身が弾く場合も、使用するピアノについて正確に把握しておきましょう。
使用ピアノの確認
体育館に備え付けのピアノを使うことがほとんどですが、時には電子ピアノを持ち込む場合もあります。そのピアノが舞台の上にあるのか下にあるのか、具体的な設置位置まで確認が必要です。
電子ピアノの場合の注意点
電子ピアノと一口に言っても、その性能は様々です。特に以下の点に注意してください。
- 音質、音量
- ペダルやキーのタッチ
本番で使用するピアノを、本番と同じ位置にセッティングして練習することをお勧めします。ただし、会場設営後でないと練習できないため、練習できる期間やタイミングは非常に限られていると考えておきましょう。
音楽科教員の服装と演奏時の注意点
卒業式の主役は、もちろん3年生です。音楽科教員は脇役として、その場にふさわしい服装を心がける必要があります。
和服(袴)を着る場合
学校によっては袴を着用する慣例があります。ご自身が着用対象かを確認し、もし着る場合は早めに準備を始めましょう。
- 着付けとヘアメイク: 自分で着付けるのか、美容院にお願いするのかを決めましょう。近隣の美容院は保護者の予約と重なる可能性があるため、早めの予約が賢明です。
- 当日の移動: 式の朝は早いため、美容院への移動手段(タクシーや始発など)も考えておく必要があります。
- レンタル品の返却方法: レンタル業者によって返却方法(箱に入れて送る、店舗に持参するなど)が異なるため、事前に確認しましょう。
- 着物の選び方: 教員はあくまで脇役です。大学生向けパンフレットにあるような派手なものではなく、シンプルで落ち着いた色柄のものを選びましょう。
ご自身で着付けができると、レンタル予約の手間が省け、コストパフォーマンスも良くなるため、これを機に練習するのもお勧めです。周りの先生に着付けができる方がいらっしゃる場合もあるので、相談してみるのも良いでしょう。
洋服を着る場合
リクルートスーツというよりは、少し華やかなものを選ぶと良いでしょう。例えば、礼服用のワンピースにラメの入ったジャケットを羽織り、コサージュをつけるといったスタイルです。
ただし、卒業学年の先生より目立たないように配慮が必要です。取り外し可能なコサージュや、複数の候補を持って行きその場で決めるといった方法も有効です。
【最重要】演奏時の注意点
服装が決まったら、必ず本番と同じ格好で演奏や移動の練習をしておきましょう。
- 靴: 特に和服の場合、足袋と草履で体育館の階段を上り下りするのは、慣れていないと非常に緊張します。
- ピアノ伴奏: 着物を着たままピアノを弾くのも非日常的な行為です。袖が邪魔になることは意外とありませんが、一度練習しておくことで「案外いけるな」と分かり、本番の緊張を和らげることができます。
まとめ
卒業式という大きな行事を成功させるため、音楽科の先生が準備すべき5つのポイントをご紹介しました。多岐にわたる準備は大変ですが、一つ一つ着実に進めることが成功の鍵です。
ぜひ、早め早めの準備を心がけ、万全の態勢で素晴らしい卒業式を迎えてください。
この記事は動画「【音楽の先生向け】卒業式の準備で失敗しない5つのポイント|着物でピアノ伴奏、どうする?」をもとに作成しました。




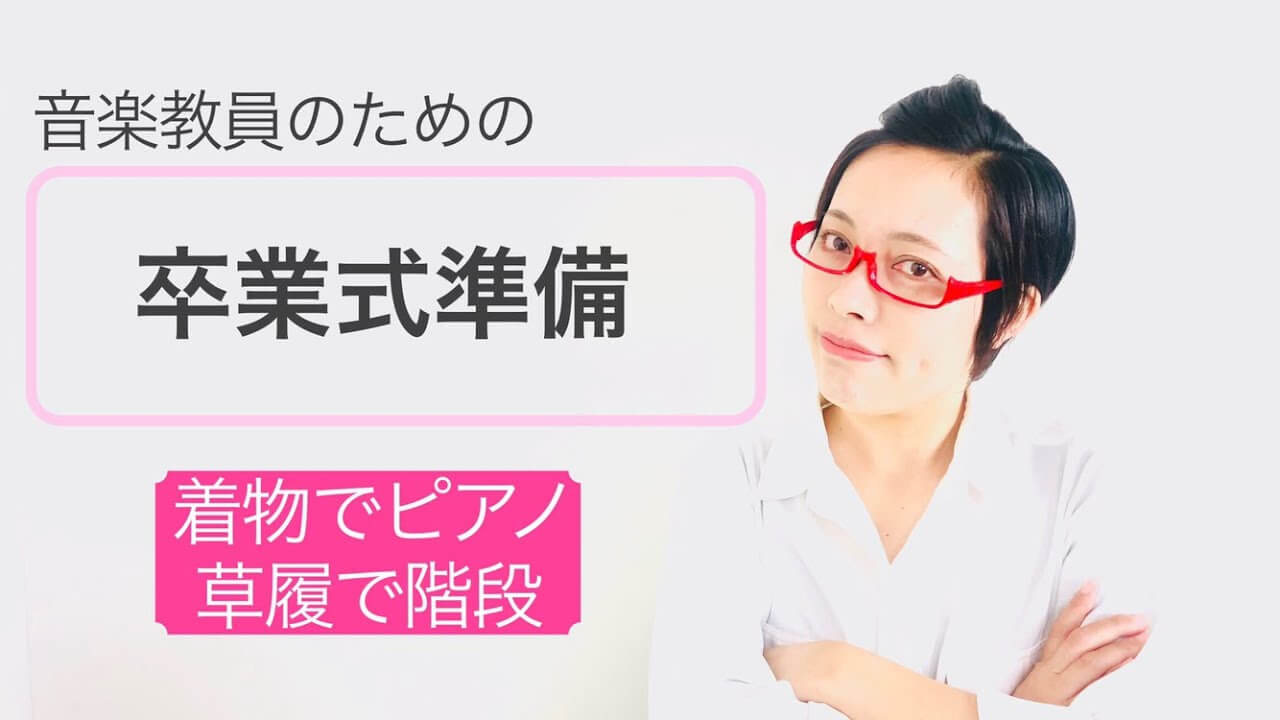







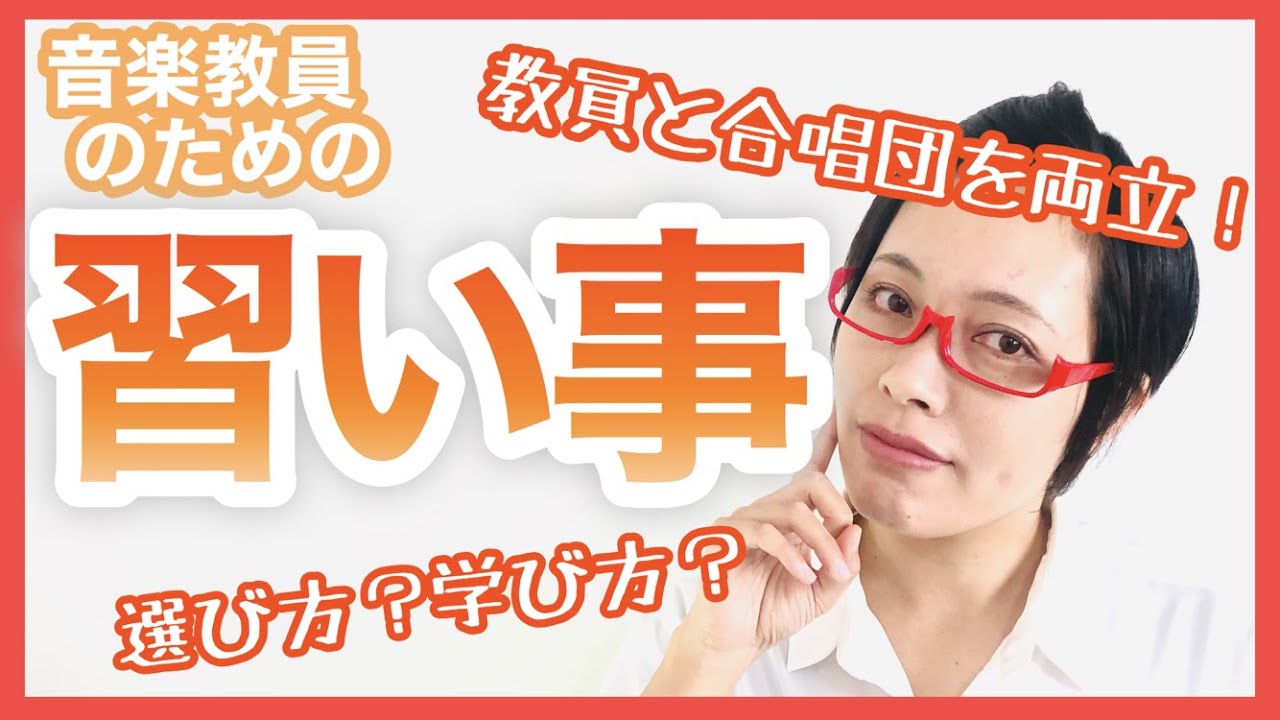


コメント