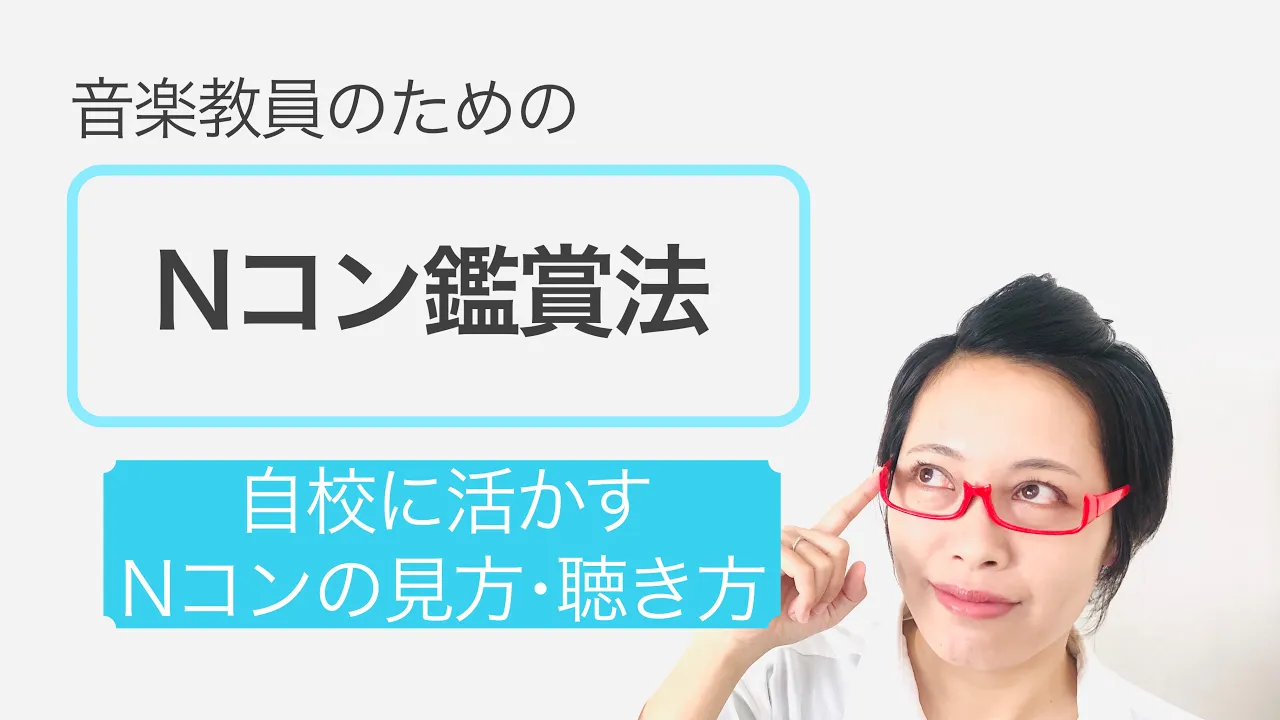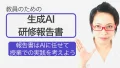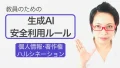毎年、多くの感動とドラマを生むNHK全国学校音楽コンクール(Nコン)。しかし、多忙な先生方にとって、その演奏をただ『すごい』と感動するだけで終わらせるのは、あまりにもったいない『学びの宝庫』です。Nコンの鑑賞は、優れた教材探しであり、ご自身の指導力をアップデートする絶好の機会となります。
しかし、テレビや動画で鑑賞していると、「すごいなあ」という感想だけで終わってしまいがちではないでしょうか。
この記事は、そんな先生方のために、
- Nコン鑑賞を「すごい」で終わらせず、一歩踏み込んだ視点を得たい方
- 歌唱表現だけでなく、多角的な鑑賞の観点を学びたい方
- Nコンを日々の授業や校内行事に活用する方法を知りたい方
に向けて、具体的な鑑賞のポイントを3つの視点からご紹介します。

視点①:「自由曲」の選曲から、指導者の『色』と教育方針を読み解く
Nコン鑑賞の第一歩は、各学校が選ぶ「自由曲」に注目することです。自由曲の選曲には、学校のカラー、生徒たちの個性、そして何よりも指揮者・指導者のカラーが色濃く反映されます。
選曲に表れる学校・指導者のカラー
まずは、ウェブサイトやプログラムで、どのような自由曲が選ばれているかを確認してみましょう。
数年分のプログラムを見比べてみると、「この学校はこういう雰囲気の曲が多いな」「この先生はこの作曲家が好きなんだな」といった、各校・各指導者の選曲の傾向や特徴が見えてきます。
注目校の絞り方
多くの学校が参加する中で、どの学校に注目すればよいか迷うかもしれません。その場合は、以下の視点で絞ってみると、より深く鑑賞できます。
- 同じ校種で比較する: ご自身が指導されている校種(小学校・中学校・高等学校)の学校がどのような曲を歌っているかを確認します。
- 同じ地区内で探す: 同じ地区の学校の選曲を知ることも重要です。
- 編成に注目する: 女声三部合唱、混声四部合唱など、合唱の編成にこだわって聴き比べてみるのも一つの方法です。
昨年度の金賞校や有名指導者をチェック
特にどの学校を見ればよいか分からない場合は、昨年度の金賞校に注目してみましょう。金賞の扱いは自治体やブロックによって異なりますが(例:東京都では予選と本選がある)、金賞を受賞した学校がどのような自由曲を歌っているかを見ることは、大きな参考になります。
また、「合唱といえばこの先生」というような有名な指導者や、最近増えている学校の先生以外の方が指揮を振るケースにも注目です。指導者・指揮者、そして伴奏者が誰なのかを意識して見ると、新たな発見があるでしょう。時には、一人の指揮者が複数の学校を指導している場合もあります。プログラムを見ながら、そうした関係性を探るのも面白い視点です。
鑑賞ポイント② 「演奏の分析」で表現の違いを学ぶ
Nコンでは、全部門で同じ「課題曲」が歌われます。同じ曲だからこそ、学校ごとの表現や演奏スタイルの違いが非常に分かりやすく、演奏を分析的に鑑賞する上で格好の材料となります。
映像から読み取る演奏技術
Nコンでは演奏映像が公開されることがあります。その映像から、以下のポイントに注目して分析してみましょう。
- ブレスの取り方
- フレーズの処理(特に課題曲でのフレージジングの違い)
- 子音や母音の処理
- 音量の設計(強弱のレンジの付け方)
- 表情・表現の付け方
これらの点は学校によって本当にカラーが出るため、じっくり比較することで表現の多様性を学ぶことができます。
指揮者から探る音楽表現の源泉
素晴らしい演奏には、優れた指揮者の存在が不可欠です。映像では指揮者の動きの全てを捉えることは難しいかもしれませんが、その表現方法に注目してみましょう。
もし機会があれば、ぜひ会場に足を運んでみることをお勧めします。
指揮者が音楽をどう捉え、それがどのように演奏として結実しているのかを目の当たりにすることは、何よりの学びになります。また、会場で生の音を聴くことで、指揮者がどのような声の作り方を目指して指導しているのか、その指導の違いが如実に読み取れます。
鑑賞ポイント③ 音楽は耳だけじゃない!「構成・演出」から学ぶ舞台表現
音楽の演奏そのものだけでなく、その演奏を支える舞台全体の構成や演出も、Nコンから学べる重要な要素です。
衣装・髪型に隠された工夫
多くの学校は制服で出場しますが、その着こなし方や髪型にも、指導の工夫や個性が表れます。「こういった工夫がされているんだな」という視点で見てみると、新たな発見があります。
立ち位置・立ち方で変わる印象
ステージ上の立ち位置や立ち方も非常に勉強になります。定められた広さの中で、
- 人と人の間隔
- パートの配置(SATBだけではない多様な配置)
- 指揮者への体の向き
- 足の広げ方・閉じ方
などをどのように決めているのか。これらの要素が、演奏の印象を大きく左右します。
入退場の所作と表情が語るもの
「うまい演奏は、もう入場してくるその様でわかる」と感じたことはありませんか?歩き方や並び方、「位置につく」という一連の所作の美しさも、演奏の一部です。
また、歌っている時の表情はもちろん大切ですが、入退場時の表情にも注目してみてください。自信に満ちた演奏をするチームは、ステージに上がる前からすでに自信あふれる表情をしています。その『スイッチ』がどこで入るのか、演奏前の生徒たちの様子を観察してみるのも面白いでしょう。
校内行事への応用
ここで紹介したような、舞台上の所作、配置、入退場の演出、移動の仕方、立ち方、歩き方、そしてそれらが聴衆に与える印象は、そのまま校内の合唱コンクールや合唱祭といった行事に応用できます。
耳から入る歌唱の情報だけでなく、こうした舞台全体の構成や演出という視点からもNコンを鑑賞することで、学びはさらに深まるでしょう。
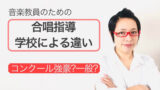
まとめ:Nコン鑑賞を、明日からの授業の第一歩に
今回は、Nコンを「鑑賞」するという視点から、具体的なポイントをお話ししました。
自校が出場する・しないにかかわらず、Nコンは学校の合唱活動にとって非常に役立つ教材の宝庫です。まずは先生方自身が『今年のNコンから何を学べるだろう?』という探究心を持って鑑賞することが、ご自身の授業を豊かにするための大切な第一歩です。
ぜひ、今回ご紹介した視点を持って、Nコンの鑑賞を楽しんでみてください。
この記事は動画「【プロはココを見る】Nコン鑑賞であなたの授業が劇的に変わる3つの視点」をもとに作成しています。