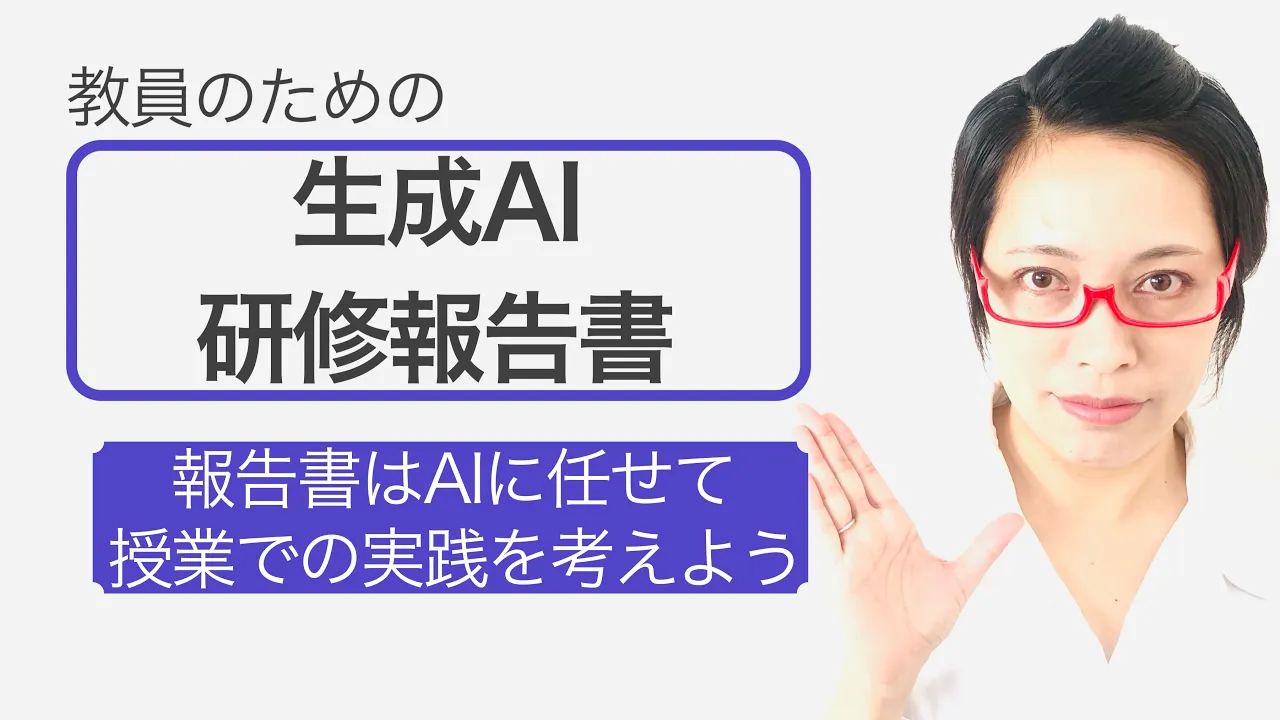日々の多忙な校務に加え、研修や出張後の報告書作成に「正直、ちょっと面倒…」と感じた経験はありませんか?
皆さん、こんにちは。一歩先ゆく音楽教育、原口直です。
この記事では、そんな先生方の悩みを解決する方法についてお伝えします。何から書けばいいのか、どんな構成にすれば良いのか分からず、つい後回しにしてしまいがちです。
しかし、ご安心ください。この記事を読めば、報告書作成の憂鬱な時間が、学びを深めるクリエイティブな時間へと変わります。
今回は、生成AIを活用して研修報告書や出張レポートを効率的に作成する、まさに目から鱗の活用術をご紹介します。研修で得たメモやキーワードをAIに渡すだけで、論理的な構成案や具体的な文章の叩き台をサクッと作成する方法が分かります。
これで、報告書作成も締め切りも、もう怖くありません。
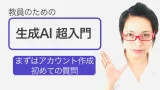
◆はじめに:生成AIに関する情報の取り扱いについて
この記事をご活用いただくにあたり、以下の点にご留意ください。
- 情報の鮮度について
この記事は、元となる動画の公開時点の情報に基づいています。生成AIは日々進化しており、精度、機能、利用規約が変わる可能性があります。ご自身で最新の情報を確認するようにしてください。 - 解釈の多様性について
生成AIに関する考え方や受け取り方には個人差があります。この記事は一つの理解のための資料であり、必ずしも唯一の正解を提示するものではありません。現場での運用方法は、所属する学校や自治体の方針にも左右されます。 - ご自身の教育観との照らし合わせ
この記事は、生成AIの可能性と課題を分かりやすく伝えることを目的としています。ご自身の教育観や教科の特性、児童生徒との関わり方を踏まえながら、活用方法を考えてみてください。
なお、学校現場における生成AIの利用については、文部科学省の専用サイトが6月30日にスタートし、ガイドラインの概要も公開されています。ぜひそちらもあわせてご覧ください。


報告書作成における生成AIの強みとは?
なぜ生成AIは、おたよりだけでなく報告書の作成も得意なのでしょうか。その理由は、報告書にはある程度決まった「型」や「構成」が存在するからです。
例えば、多くの報告書は以下のような流れで構成されています。
- 研修概要
- 内容
- 考察
- 今後の活用
生成AIは、このような型に沿って情報を整理し、論理的な文章を組み立てるのが非常に得意です。先生方が研修中に取った断片的なメモやキーワードも、AIが自動で分かりやすい構成に整理してくれます。
つまり、私たちは「何を伝えるか」という研修の中身に集中でき、面倒な体裁を整える作業から解放されるのです。これこそが、報告書作成で生成AIを活用する最大のメリットと言えるでしょう。
では、この強力なメリットを具体的にどのように活用すればよいのでしょうか。ここからは、簡単なステップで実践方法を見ていきましょう。
【実践】キーワードから研修報告書を自動生成する方法
それでは、実際にキーワードから報告書を自動生成するプロセスを見ていきましょう。
今回は、「中学校音楽科の教員がICTを活用した合唱指導法についてのオンライン研修に参加した」という設定で進めます。
ステップ1:研修の要点・キーワードをメモする
まず、研修で学んだことや感じたことを、綺麗な文章でなくても全く問題ないので、箇条書きでメモします。
【メモの例】
- 研修名・日時:(具体的な研修名と日時)
- 目的:ICTで表現の幅を広げること
- 内容:
- 録音機能を使った客観的な振り返り
- ハーモニー練習アプリの紹介
- 学んだこと(成果と考察):
- 生徒の主体的な練習につながる可能性
- 自分の指導の癖に気が付いた
- 今後の課題:
- 機材の準備
- 生徒のスキル習熟
本当にこれだけのメモで大丈夫です。
ステップ2:生成AIに報告書の作成を依頼する
次に、ステップ1で作成したキーワードのメモを使って、生成AIに報告書の作成をお願いしてみましょう。
その際、以下のように「一般的な報告書のフォーマットで、指定した項目で構成してほしい」とはっきりと指示を出すことがポイントです。
【プロンプト入力例(全文)】
あなたは中学校の音楽科教員です。
以下のキーワードをもとに、「ICTを活用した合唱指導法研修」についての出張報告書を作成してください。
一般的な報告書のフォーマット(目的、内容、成果、今後の課題など)で構成してください。# 報告書の概要
– 研修名:オンライン研修「ICTを活用した合唱指導法」
– 日時:2025年6月28日 14:00-16:00
– 目的:ICT機器の活用により、生徒の表現の幅を広げる指導法を学ぶ
– 内容:(1)タブレットの録音機能を使った客観的な歌声の振り返り指導、(2)ハーモニー練習アプリ「ハーモニーチューター」の紹介と活用事例
– 成果と考察:生徒自身の気づきを促し、主体的な練習につながる可能性を感じた。自分の指導の癖(特定のパートへの指示の偏り)にも客観的に気づけた。
– 今後の課題:全生徒が使用できるタブレット端末の準備。アプリ操作のスキル習熟のための時間確保
Google Geminiのような生成AIにこの指示文とキーワードを入力すると、あっという間に構成に沿った出張報告書の文章が作成されます。
AIの『叩き台』から『価値ある報告書』へ仕上げる一手間
生成AIが作成した文章は、体裁が整っており非常に便利ですが、あくまでも「叩き台」です。そのまま提出するのではなく、少し手直しを加えるだけで、読む人により伝わる価値ある報告書になります。
生成AIが作った文章は、そのままだと少し無機質な印象を与えてしまうことがあります。そこで、先生自身の「声」を加えて、血の通った文章にしていくのです。
- 具体的な感想や発見を追記する
- 例:「学んだこと」のセクションに、「特に●●というアプリを使えば、これまでパート練習が苦手だった生徒もまるでゲームのように楽しみながら取り組めると感じた」といった、現場をイメージした具体的な感想を加える。
- 具体的な行動計画を示す
- 例:「今後の活用」の部分で、「まずは2学期の合唱コンクールの練習で自分のクラスから試してみたい」というように、具体的な行動に落とし込む。
このような手直しを加えることで、報告書を読む側にも先生の本気度が伝わります。
なぜ「自分自身の言葉」を加える必要があるのか?
なぜなら、報告書の本当の価値は単なる『記録』ではなく、学びを組織に還元し、次へと繋げる『コミュニケーション』にあるからです。
生成AIが作った骨子(叩き台)に、先生自身の体温が感じられる言葉を載せることで、初めて価値のある報告書が完成します。
同じ研修を受けても、先生一人ひとりが持つ感想やアイデアは異なり、自分のクラスの子供たちを思って具体的に考えを巡らせるからこそ、その報告書は独自の価値を持つのです。
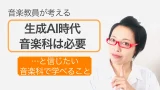
まとめ:AI活用で生まれた時間を、より有益な活動へ
今回は、生成AIを活用した研修報告書の作成術についてお話ししました。
- 生成AIは報告書の「型」を作るのが得意
- キーワードのメモ書きから「叩き台」を自動で生成できる
- 叩き台に先生自身の具体的な感想や計画を加えることで「価値ある報告書」に仕上がる
この記事を読んで、研修報告書に対する気持ちが少し楽になったのではないでしょうか。
まずは研修で取った箇条書きのメモを、そのまま生成AIに入れてみてください。きっと、その時短効果に驚くはずです。成果物が形としてハッキリ見えるので、生成AI活用の成功体験として非常に実感しやすいテーマだと思います。
こうして生まれた貴重な時間を、生徒一人ひとりと向き合う時間や、より良い授業を創造するための準備に充てる。AIの活用は、先生方が教育という本質的な活動にさらに集中するための、強力なパートナーとなるでしょう。
この記事は、動画「【もう後回しにしない】先生のための生成AI活用講座③|研修報告書をサクッと時短作成」をもとに作成しました。