毎月の学級通信やおたよりの作成に、思ったより時間がかかっていませんか?
特に合唱コンクールなどの大きな行事の後は、伝えたいことがたくさんあるのに、忙しくて文章を練る時間がない…そんな悩みを抱える先生も多いのではないでしょうか。
今回は、具体的な校務での活用方法として、生成AIで書く学級通信・おたよりの文案作成術についてお話しします。
定期的に発行する学級通信やおたより、学年だよりの原稿。
「季節の挨拶からどう書き出そうか」
「どんな言葉を選べば丁寧な印象になるか」
など、いざ書こうと思うと意外と時間がかかってしまいませんか?
特に大きな行事の後などは、書きたいことはたくさんあるのに、忙しすぎてじっくり推敲する時間が取れない、ということもあるでしょう。
この記事を読めば、そんな文章作成の悩みが劇的に軽くなります。
生成AIは文章を作成するのが得意です。伝えたいことの要点を渡すだけで、あっという間に丁寧な文章のたたき台を作る方法が分かります。文章をゼロから考える時間を短縮し、その分、内容そのものをより豊かにする時間に使いましょう。
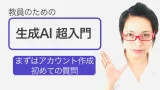
◆はじめに:生成AIに関する情報の取り扱いについて
この記事をご活用いただくにあたり、以下の点にご留意ください。
- 情報の鮮度について
この記事は、元となる動画の公開時点の情報に基づいています。生成AIは日々進化しており、精度、機能、利用規約が変わる可能性があります。ご自身で最新の情報を確認するようにしてください。 - 解釈の多様性について
生成AIに関する考え方や受け取り方には個人差があります。この記事は一つの理解のための資料であり、必ずしも唯一の正解を提示するものではありません。現場での運用方法は、所属する学校や自治体の方針にも左右されます。 - ご自身の教育観との照らし合わせ
この記事は、生成AIの可能性と課題を分かりやすく伝えることを目的としています。ご自身の教育観や教科の特性、児童生徒との関わり方を踏まえながら、活用方法を考えてみてください。
なお、学校現場における生成AIの利用については、文部科学省の専用サイトが6月30日にスタートし、ガイドラインの概要も公開されています。ぜひそちらもあわせてご覧ください。

なぜ「たたき台作り」が有効なのか?
いきなり生成AIに完璧な文章を作ってもらおうとするのではなく、まずは「たたき台(下書き)」を作ってもらうのが、うまく付き合うコツです。
なぜなら、白紙の状態から文章を考えるのはとても大変ですが、すでにある文章を修正したり、自分らしい言葉に書き換えたりするのは、ずっと簡単だからです。
AIが作ったたたき台を元にすれば、先生方のオリジナルの文章やクラスの具体的なエピソードなどを盛り込む作業に集中できます。これにより、文書作成の心理的なハードルがぐっと下がり、時間も大幅に節約できるのです。
【実践編】たった3ステップで完成!合唱コンクール後のおたより文案作成術
ここでは、中学校の音楽科の担任の先生が、合唱コンクール後に発行する学年だよりの原稿を書くという場面を想定して、具体的な3つのステップを見ていきましょう。
ステップ1:AIに役割を与える
まず、生成AIに「あなたは中学校の音楽科の教員です」と役割をお願いしてみましょう。
役割を与えることで、生成AIはその立場にふさわしい言葉遣いや視点で文章を考えてくれるからです。
ステップ2:伝えたい要点を箇条書きで伝える
次に、伝えたい内容の要点を箇条書きで伝えます。詳しい文章にする必要はなく、キーワードのメモ書きのような形で十分です。
【入力例】
- 合唱コンクールが無事に終わったことへの感謝の気持ち
- 本番に至るまでの練習の中で生徒たちが大きく成長したこと
- 音楽を通してクラスの団結が深まっていった様子
- この素晴らしい経験を今後の音楽の授業や学校生活全体に生かしていきたいという決意
ここが、先生が生成AIに伝えたい一番大事な部分になります。
ステップ3:文章のトーンを指定する
最後に、文章の雰囲気を指定します。
「保護者向けに、生徒たちの頑張りを具体的に称える温かい雰囲気の文章にしてください」といった形でお願いしましょう。
この3つの要素を組み合わせることで、AIは意図を汲み取った文章を生成してくれます。実際にAIに入力するプロンプト(指示文)の例を以下に示します。コピーして、ご自身の状況に合わせてアレンジしてみてください。
【プロンプト入力例(全文)】
あなたは中学校の音楽科の教員です。 以下の要点を含めて、合唱コンクール後に保護者へ向けたおたよりの文章を作成してください。
# 要点
– 合唱コンクールが無事に開催できたことへの感謝
– 練習を通して生徒たちが大きく成長したこと(技術面、精神面)
– 音楽を通してクラスの団結が深まった様子
– この経験を今後の学校生活活かしてほしいという思い# 条件
保護者向けの、生徒たちの頑張りを具体的に称える、温かい雰囲気の文章にしてください
もっと良くする!生成AIへの追加指示のコツ
生成された文章は、あくまで「たたき台」です。そのままコピー&ペーストするのではなく、ここから対話するように追加でお願いをして、さらに理想の文章に近づけていきましょう。
- 文字数の調整: 「全体をもう少し短く400字程度にまとめてください」
- 表現の変更: 「もっと生徒たちの表情が目に浮かぶような生き生きとした表現を加えてください」
このように、対話を通じて理想の文章に仕上げていくことができます。
また、各クラスの練習の具体的なエピソードなどを加えるのも良いでしょう。こういった具体的な内容は生成AIは知りませんので、ここは人間の腕の見せどころです。
【最重要】最終チェックは必ずご自身の目で
AIが作った文章は、必ず先生ご自身の目で最終チェックをしてください。
- クラスの事実と合っているか?
- ご自身の言葉として違和感はないか?
これらを確認し、ご自身の心を込めた言葉で修正を加えて完成させてください。
生成AIは時短のパートナーですが、最後の仕上げとそこに込める思いは先生自身が行うというスタンスが大切です。文部科学省のガイドラインでも「人間中心の利活用」が基本的な考え方として示されています。

まとめ:頼れるアシスタントとしてAIを活用しよう
今回は、生成AIを使った学級だよりの作成術についてお話ししました。
- ポイント1: 完璧を目指さず「たたき台」を作ってもらう。
- ポイント2: 「役割・要点・トーン」の3ステップで簡単にお願いできる。
- ポイント3: 対話するように追加指示で調整し、最後は必ず自分でチェックする。
いかがでしたでしょうか。これなら、次の学級通信からすぐに試せそうだと感じていただけたかと思います。
最初は、今回ご紹介した例文を真似するところからで大丈夫です。箇条書きで伝えたいことをメモするだけで、あの面倒だった文章作成がぐっと楽になる感覚を、ぜひ味わってみてください。
生成AIは、先生方の創造性を奪うものではありません。むしろ、文章作成のような業務から解放されることで生まれた時間と心の余裕を、生徒一人ひとりと向き合う、より本質的な教育活動に注ぐための強力なサポーターです。この頼れるアシスタントを、ぜひ活用してみてください。
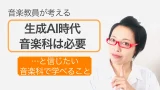
この記事は動画「【時短術】先生のための生成AI活用講座② 学級通信・おたよりを3ステップで作成!」をもとに作成しました。






