「授業を進めていると、自分のスキルに物足りなさを感じる…」
「教員として、もっと成長したいけど、何から始めればいいんだろう?」
日々の業務に追われる中で、ふとこのように感じる瞬間はありませんか。大人になったから、教員になったからといって、学びを止めてしまうのはもったいないことです。むしろ、大人になったからこそ見えてくる世界があり、自身の専門性をさらに高めるチャンスが広がっています。
この記事では、音楽教員歴10年の経験をもとに、先生が習い事を始める際に大切にしたい考え方や、具体的な選び方について、実体験を交えながら詳しく解説します。
先生が習い事を始めるための考え方①:諦めない心
まず大切にしたいのが、「教員になったから」「大人になったから」という理由で学びの可能性を閉ざさない、という気持ちです。
実際に、教員になってから社会人の合唱団に所属し、仕事と両立させながらコンクールや演奏会に出場していた経験があります。当時は土曜日にも授業がありましたが、事前にスケジュールを共有して協力をお願いするなど、家族の理解を得ることで、合唱団の活動を続けることができました。
両立のためには、以下の点が重要になります。
- 体調管理とスケジュール管理を徹底する
- 周囲の理解を得る(家族、同僚の先生方など)
- 例:土曜の午後の練習に間に合うよう、午前中の授業後にすぐ出発できるように準備しておく。
- 例:合唱団の練習で午後の部活動ができないことを、生徒に理解してもらう。
また、現代では学び方も多様化しています。必ずしも教室に通う必要はありません。
- オンラインサービスの活用: インターネット上には、学習のためのサービスが数多く存在します。オンラインでどのように学べるかを模索するのも一つの方法です。
- 単発での受講: 長期間通うのが難しくても、単発や数回で完結する講座を探すこともできます。ウェブ上のサービスを使えば、自分に必要なスキルをピンポイントで身につけることが可能です。
先生が習い事を始めるための考え方②:2種類の選び方
習い事を選ぶ際には、大きく分けて2つの種類があると考えられます。
- 音楽教育に関する習い事
- 音楽教育に全く関係のない習い事
一つ目は、楽器のレッスンや合唱団への参加など、自身の専門分野に直結するものです。二つ目は、専門とは全く異なる分野の習い事ですが、これも非常に重要です。可能であれば、この両方を両立させるのがベストです。
音楽教育に全く関係のない習い事の実践例
一見、音楽教育とは無関係に見えるかもしれませんが、視野を広げるために、長期休みなどを利用して様々なことに挑戦してきました。以下にその一例を紹介します。
- 自分を知る・磨く講座
- パーソナルカラー診断(自分に似合う色を多角的に判断してもらう)
- 腸もみ
- ネイル、メイク
- ものづくり・食文化
- 桜餅作り
- スターバックス主催「カスタマーコーヒーマスター」
- アクセサリー作り(YouTubeで習得)
- デジタル・クリエイティブ
- LINEスタンプ作り(YouTubeで習得)
- 動画編集
- 身体・パフォーマンス
- 循環呼吸(YouTubeで習得)
- タイ古式マッサージ
- DJ体験
- ゴルフ体験
このように、一見音楽教育とは関係ないように思える分野でも、新しい発見や学びがあります。
【お金をかけない授業動画作りのコツ:撮影編】100円ショップの三脚・スマホで編集・撮影は浴室
【お金をかけない授業動画作りのコツ:動画編集・アップロード編】YouTube動画作成方法はYouTube動画から学ぼう
【お金をかけない授業動画作りのコツ:サムネイル作成編】サムネイル画像の作成過程を実況解説
先生が習い事を始めるための考え方③:人との関わりを大切にする
習い事の価値は、スキルを習得することだけではありません。そこで出会う「人との関わり」も、非常に大きな意味を持ちます。
- 多様な人々との出会い: 講座の先生や、一緒に学ぶ他の生徒さんたちとの出会いは貴重です。学校という環境の中にいると、どうしても音楽や教育という枠の中で物事を考えがちになります。しかし、異なる背景を持つ人々と接することで、自分の考えがいかに小さなものだったかに気づかされたり、学校のことを客観的に考えるヒントをもらえたりします。
- 指導者から学ぶ指導法: 自分が「習う側」になることで、教えてくれる先生の指導の仕方を客観的に見ることができます。そこには、自身の指導にも反映できるヒントがたくさん隠されています。
習い事を通じて、その分野の知識だけでなく、周りの人々からも多くのことを学べるのです。
まとめ:興味のアンテナを広げ、学び続ける姿勢を
今回は、先生が習い事を始める際の考え方についてお伝えしました。
先生も、子どもたちと同じように学び続ける姿勢が大切です。そして、その学びは必ずしも音楽や教育の分野にこだわる必要はありません。
自分が「面白そうだな」と興味を持ったことに積極的に挑戦してみてください。先生自身が学びを楽しむ姿は、子どもたちの知的好奇心を刺激する最高の教材にもなります。経験の一つひとつが人間的な幅を広げ、日々の教育活動をより豊かなものにしてくれるはずです。
この記事は動画「「学び続ける教員は、かっこいい。」専門性と人間性を磨く大人の習い事。」をもとに作成しました。




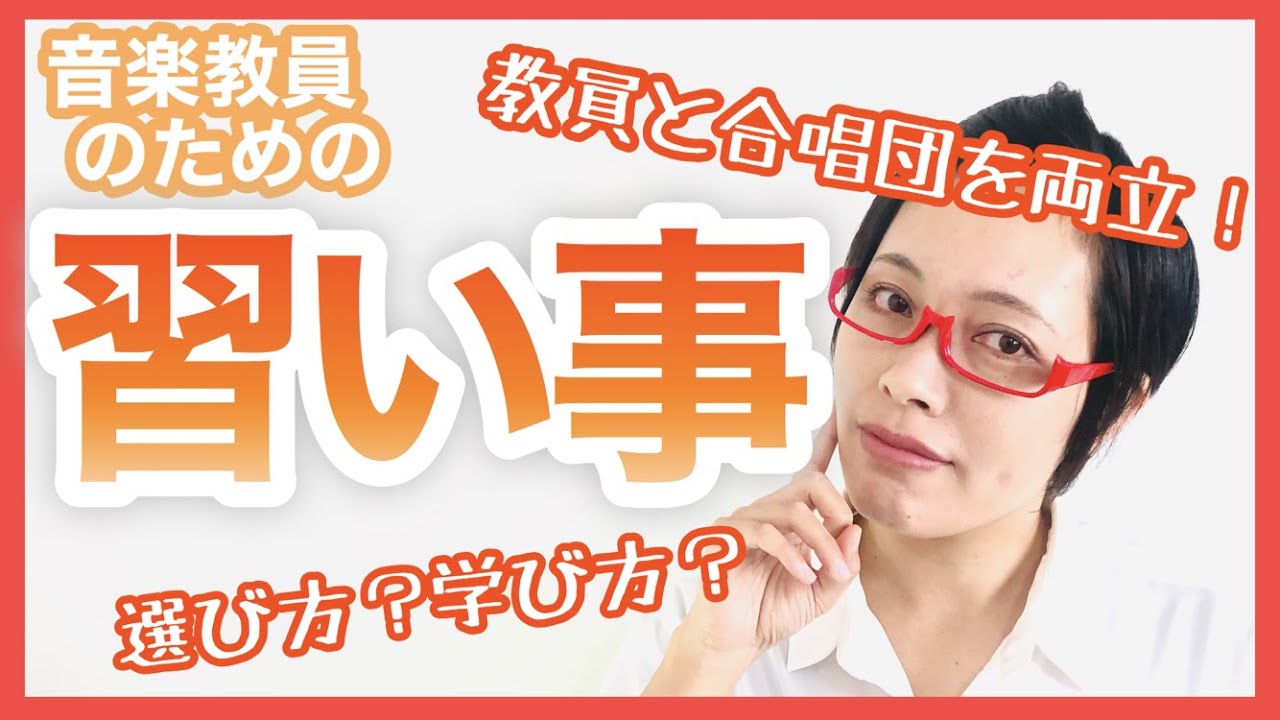







コメント