今回のテーマは、音楽授業における「ワークシートの作り方」です。ワークシートは、授業の記録だけでなく、生徒の知覚・感受・批評といった個々の表現を受け止める大切なツールです。また、評価においても非常に重要な役割を果たします。
この動画では、効果的なワークシート作成のコツを3つご紹介します。PowerPointの作り方や板書の方法、板書とPowerPointの使い分け方については、別の記事でも解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
ポイント1:「不親切さ」が生徒の主体性を引き出す
ワークシート作成の最初のポイントは「不親切さ」です。
これは教育実習生にもよく伝えている考え方です。授業や生徒への不安から、つい親切すぎるワークシート、つまり見ただけで内容が分かるものを作りがちです。
しかし、細かく項目が書かれていたり、文章の穴埋め形式になっていると、生徒は教科書を見ながら機械的に記入してしまい、その時間に本当に聞いてほしい話や考えてほしいことに集中できません。
「1.」「2.」「3.」と番号を振るだけ、大きな四角や線だけを描くといった、何を書けばいいかが明確でないワークシートの方が、生徒は話を聞きながら自分の考えをまとめ、授業と連動してワークシートを進めるようになります。
私も初任の頃には、「ベートーヴェンは●年にドイツの●に生まれた」「●歳から●が悪くなった」といった、教科書を見れば答えられる穴埋め形式のワークシートを作っていました。しかし今では、「1.」とだけ書き、「ベートーヴェンの生涯について特徴を書きなさい」とするだけで十分だと考えています。
ポイント2:フォーマットの統一で分かりやすく整理
2つ目のポイントは「同じフォーマット・形式」で作ることです。
私は副教材としてファイルを年度初めに配布しており、その際にサイズを統一することが求められます。
フォントや全体のデザインも統一しておくことで、後からまとめて見返す際に整理しやすく、重要な点が一目で分かるようになります。また、他教科のワークシートと混ざった場合でも、音楽のものだとすぐに識別できるのが利点です。
Wordなどのソフトを使って「規定に設定」機能を活用すれば、作業時間を短縮しながら、毎回同じ形式で作ることが可能になります。
ポイント3:「後で見やすい」ことで授業の継続性を確保
3つ目のポイントは「後で見やすいワークシート」にすることです。
音楽の授業は週に1〜2時間程度しかないため、生徒が前回の授業内容を覚えているのは困難です。
その間に他教科の学習、塾、習い事、家庭の用事、部活動など多くのことが挟まります。だからこそ、ワークシートが前回の授業内容を思い出すきっかけになります。
前回の内容を思い出しやすいように構成されたワークシートは、授業のつながりを保ちやすくし、復習の時間を節約できます。
おわりに:ワークシートを活用してより良い授業へ
今回は、音楽授業でのワークシート作成に関する3つの秘訣をご紹介しました。
- 「不親切さ」で生徒の主体性を育てる
- 「フォーマットの統一」で整理と識別を助ける
- 「見返しやすさ」で授業の継続性を支える
これらを意識してワークシートを作成することで、より効果的な授業が可能になります。PowerPointや板書に関する解説も今後の動画でご紹介していきますので、ぜひそちらも併せてご覧ください。
この記事は動画「音楽教師必見!生徒が集中する『ワークシート作り』3つの秘訣」をもとに作成しました。










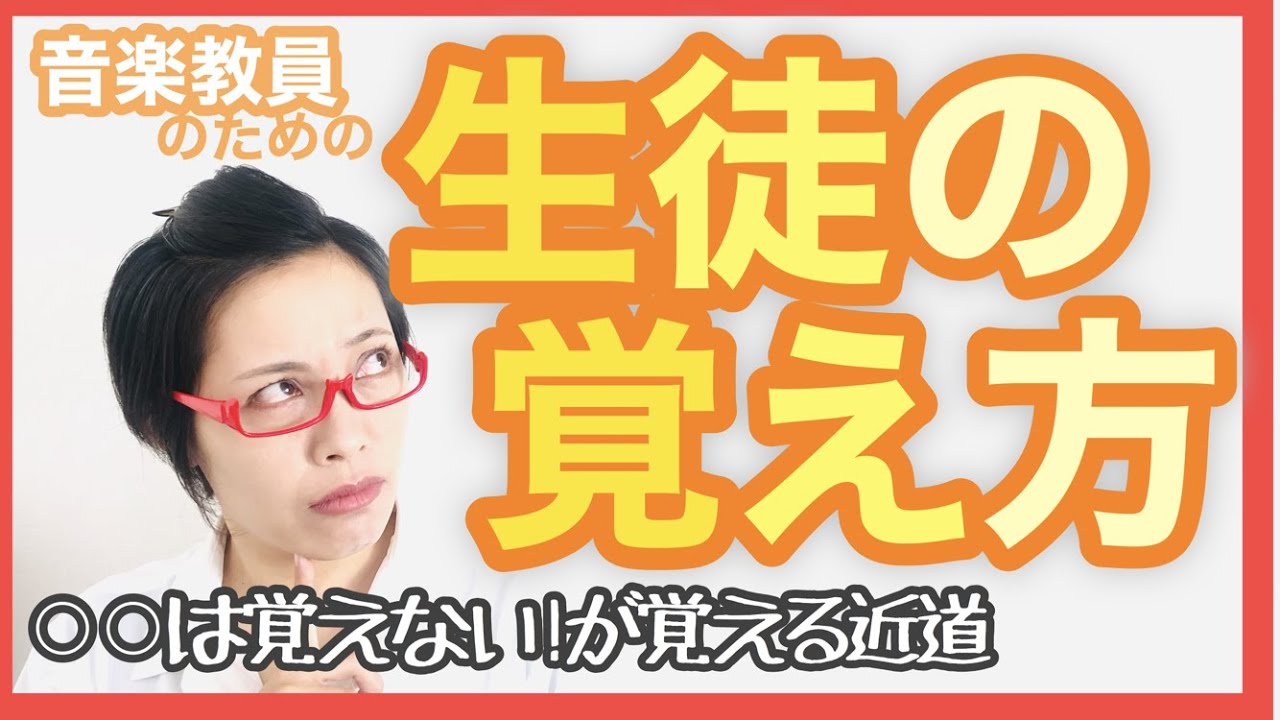
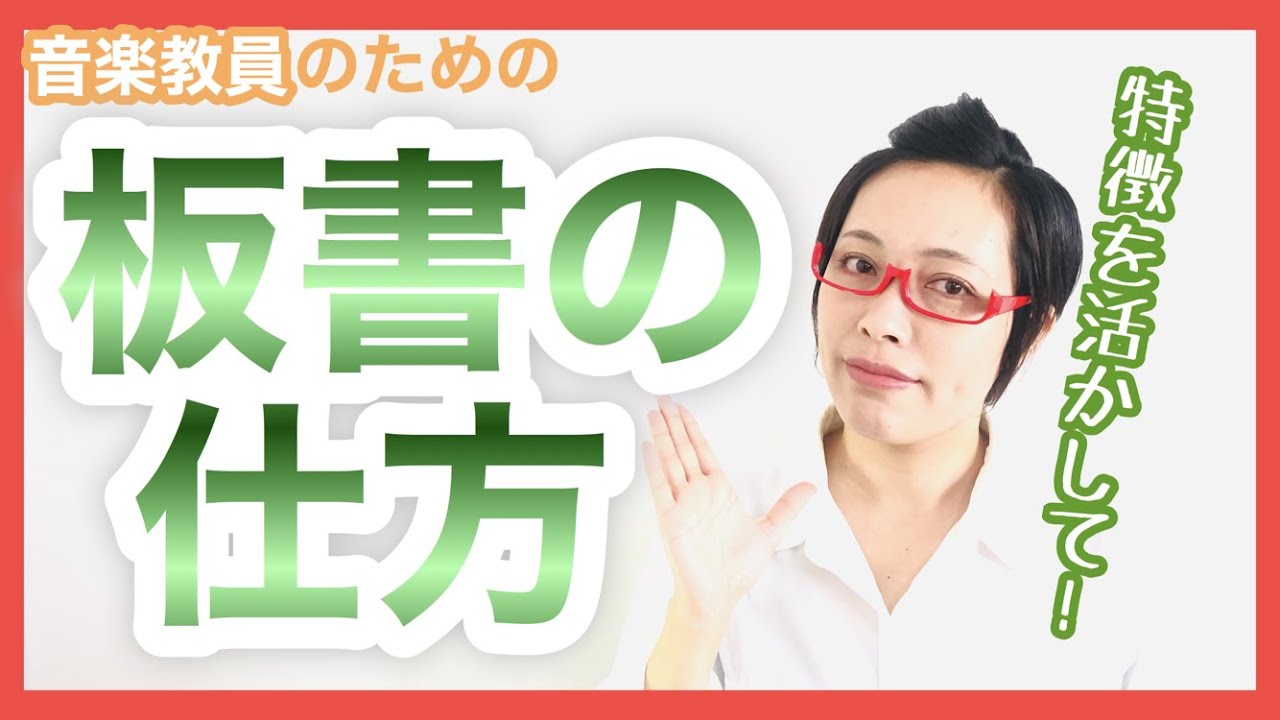
コメント