「家のピアノを調律しに来てくれる人」。多くの人が持つ調律師のイメージは、このようなものではないでしょうか。しかし、学校という教育現場において、調律師は少し異なる、そして非常に重要な役割を担っています。
「半年に一度、家に来てピアノを分解し、何かを弾いている人」——音楽教員になる前の私も、調律師に対してそのような漠然としたイメージしか持っていませんでした。
しかし、学校の調律師の役割を正しく理解し、良好な関係を築くことは、日々の授業で使うピアノを最適な状態に保ち、音楽教育の質を高める上で不可欠です。
この記事では、学校における調律師の役割と、先生方が知っておくべき付き合い方のポイントを、準備編として解説します。
音楽室のピアノを最も知る「音楽室の父」
「音楽の父」といえば、もちろんヨハン・セバスティアン・バッハですが、「音楽室の父」は調律師さんであると言っても過言ではありません。
多くの場合、一つの学校には特定の調律師が長年にわたって担当としてついています。たとえ担当者が変わっても、同じ会社が引き継ぐことが多く、その学校の状況や歴史を深く理解しています。
教員以上に、学校のピアノについて熟知している存在、それが調律師です。
- それぞれのピアノのクセ
- 複数台あるピアノの個体差
- ピアノの歴史(いつ学校に来たか、使用頻度など)
音楽室だけでなく、校内に点在するすべてのピアノの「今」と「これまで」を一番知っているのが調律師なのです。
【実践編】ピアノの性能を最大限に引き出す「伝え方」
家庭にピアノが1台だけある状況とは異なり、学校のピアノは使用環境や目的が多岐にわたります。調律を依頼する際には、単にタッチや音色の好みといったリクエストだけでなく、より具体的な情報を伝えることが重要です。
弾く頻度・弾く人・目的を伝える
調律の効果を最大限に高めるため、特に複数台のピアノがある場合は、以下の点を具体的に伝えましょう。
- 弾く頻度: 「このピアノは毎日使いますが、あちらはあまり使いません」
- 弾く人: 生徒がメインで弾くのか、教員がメインで弾くのか
- 目的: 合唱伴奏で使うのか、パート練習で使うのか
よく弾く期間や普段の状態も共有する
特定期間の使用頻度や、ピアノが置かれている環境を伝えることも大切です。
- よく弾く期間: 「9月、10月は合唱コンクールに向けて、このピアノを非常によく弾きます。それ以外の時期は、正直あまり弾いていません」
- 普段の状態: ピアノが置いてある場所に空調が効くか、普段は誰も触らない状態か
こうした細かい情報共有が、学校という特殊な環境に合わせた最適な調律につながります。
予約忘れは命取り?調律師とのスケジュール調整術
調律師は一人の担当者が複数の学校を掛け持ちしていることがほとんどです。そのため、スケジュール調整は教員にとって非常に重要な業務となります。
1年越しのスケジュール確保が基本
私の場合、調律が終わったその日に「来年もこの時期でお願いします」と1年後の予約を仮で入れていました。 そして、新年度が始まり4月に年間行事予定が確定したら、すぐに正式な日時を連絡するという流れを徹底していました。
多忙な業務の中で、つい調律の段取りを忘れ、調律師からの連絡でハッとした経験がある先生もいるかもしれません。
スケジュール管理の失敗談
私の学校では、毎年夏休みに校内すべてのピアノを調律してもらうのが恒例でした。しかし、一度だけその手配を完全に忘れてしまい、大変な事態に陥ったことがあります。
授業が始まってしまった2学期、合唱コンクールまでの限られた時間の中で、すべてのピアノの調律を終えなければなりませんでした。そのため、部活動を休みにしてもらったり、体育館の授業や部活動と利用時間の交渉をしたりと、各方面に調整が必要となり、非常に大変な思いをしました。
この経験からもわかるように、スケジュールの早期確保は、調律師のためだけでなく、私たち音楽科教員自身のために、絶対に欠かせないことなのです。
まとめ:調律師は授業を共創する「伴走者」
今回は、学校における調律師との付き合い方について、準備段階で知っておくべきことを解説しました。
調律師は、単にピアノを修理する技術者ではなく、日々の授業を陰で支え、共に創り上げていく『伴走者』です。ピアノの状態を深く理解し、適切なタイミングで必要な情報を共有して連携することで、その価値は最大限に引き出されます。
調律師の専門性や役割を深く理解し、良好なコミュニケーションを築くことで、日々の授業で使うピアノを最大限に活かしていきましょう。
この記事の内容は動画「【音楽教員の仕事術】調律師との連携が劇的に変わる3つの準備|ピアノの性能を最大限に引き出す方法」をもとに作成しました。




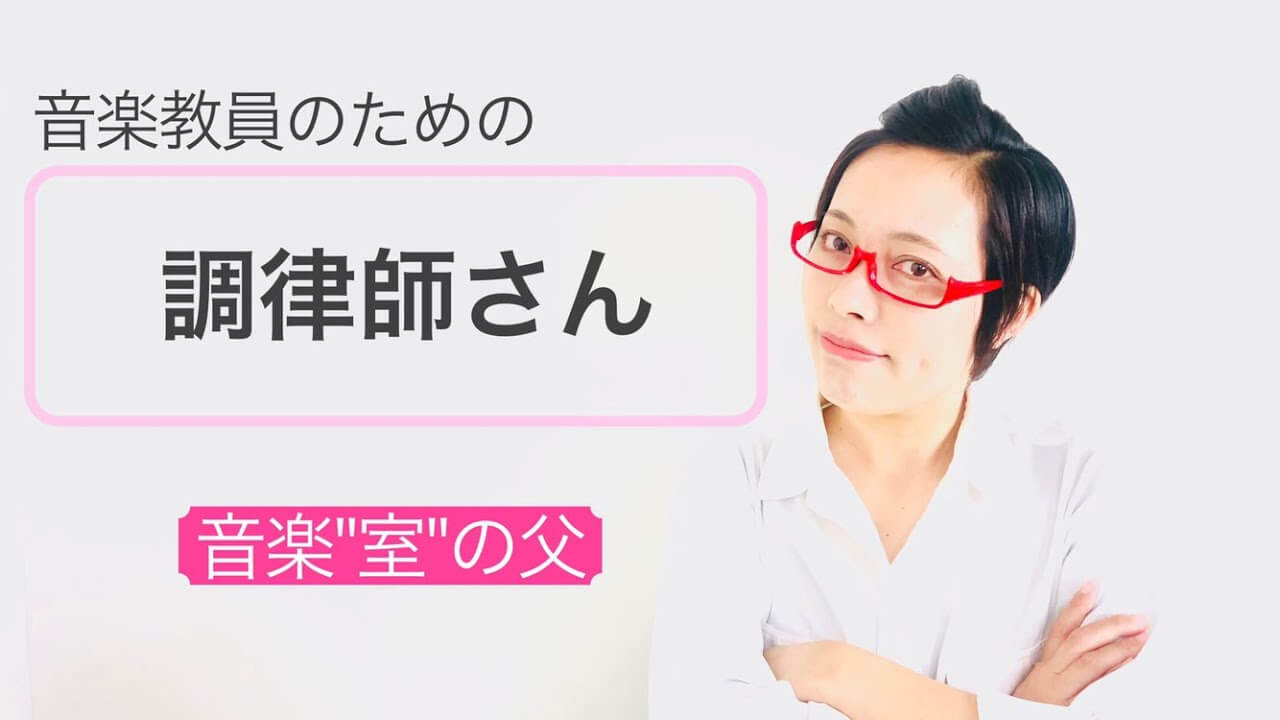







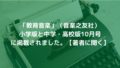
コメント