今回は「常時活動」についてお話しします。
常時活動とは、授業の始めに5分から10分程度をかけて行う、毎回の授業で行う活動のことをいいます。その日の授業の導入や、導入の前に行うことで、授業を円滑に進められるように常時活動を行う先生も多くいます。
この記事では、私が実際に見てきた常時活動をいくつかご紹介したいと思います。
校歌を歌う:発声練習と規律の定着
紹介する常時活動の一つ目は「校歌を歌う」ことです。
授業の始めに校歌を全員で歌うという活動を見たことがあります。
校歌を歌うことで得られる効果は、発声練習になるということ、最初に注目を集められるということ、そしてそこからきちんと規律を守らせることができるという点です。
毎回の授業ごとに指揮者が変わったり、伴奏を担当する生徒がいたりと、さまざまなバリエーションがありました。
発声練習・体操:アイスブレイクと集中の促進
常時活動の二つ目は「発声練習や体操」です。
特に合唱の授業の場合、常時活動として非常に有効だと思います。アイスブレイクも兼ねて、心や体をほぐすために、いろいろな発声練習や体操をしているのを見たことがあります。
発声練習や体操には多くの種類があり、目的別にメソッドがたくさん出ていますので、本などで実践を学ぶと良いでしょう。この活動が効果的なのは、注目を集められること、規律を守らせることができることが挙げられます。
鑑賞活動:「本日のオーバーチュア」
三つ目に紹介する常時活動は、私自身が行っていた「鑑賞」です。「本日のオーバーチュア」「本日のMステ」という名前で行っていました。
■音楽のオンライン授業実践編《教材:ブルタバ(モルダウ)》
■音楽のオンライン授業実践編《教材:交響曲第5番ハ短調(運命)》
■音楽のオンライン授業実践例《教材:春 第1楽章》
毎回授業のはじめに、私がおすすめする1曲を生徒と一緒に鑑賞する時間を設けていました。目的は、音楽を形作っている要素の言葉を使えるようにすることでした。
曲は季節行事などによって変えており、例えば次のような例があります:
- 4月:「桜」というタイトルの曲の比較
- 梅雨の時期:「ショパンの雨だれ」
- 運動会時期:「クシコスポスト」
- 年末:「紅白」「グラミー賞」「流行語大賞」などに関連した音楽
- その他:「パプリカ」の子供バージョンと米津玄師さんバージョン など
曲を聴かせるときには批評を書かせ、その際、必ず音楽を形作っている要素の言葉を使わせていました。
1年生の場合は、曲を聴かせる前に「これとこれを使ってね」というように、2つの要素の言葉を提示していました。
たとえば、「クシコスポスト」を聴かせるときには「音色」と「速度」の2つの言葉を使ってください、と伝え、言葉の意味も「これこれこうです」と説明しました。
また、「雨だれ」の場合には「リズム」と「旋律」という言葉を使って批評を書くよう指示し、それぞれの意味も丁寧に説明していました。
「テクスチュア」や「構成」といった要素の言葉は初めはわかりにくいため、具体的な音楽を示したり、音楽の場所を示したりして、
- 「ここはテクスチュアが変化したね」
- 「この曲はこのような形式になっています」
- 「このような構成になっています」
- 「構成の中の反復を使っています」
といったような具体的な説明も、この常時活動の中で行っていました。
2、3年生になると、説明がなくても、また言葉を限定しなくても、自分たちで言葉を選んで説明できるようになります。
たまに言葉が混ざって間違って使ってしまうこともありました。たとえば「リズムが早い」と言うべきところを「速度が速い」、「リズムが細かい」などと言うべきであることもあります。そのようなときには、指摘したり修正したりすることもありました。
この鑑賞活動は、授業のはじめに5分から10分ででき、自分の音楽の幅を広げていくのにも、とても適していたと思います。
3年生に最後の授業で「印象に残っている活動は何ですか?」と尋ねると、「本日のオーバーチュアが良かった」と書いた生徒が何人もいました。私にとってはたった5分の常時活動でしたけれども、生徒たちにとっては新しい音楽に出会うきっかけになっていたと思います。
おわりに:常時活動の意義と可能性
今回は常時活動についてお話ししました。必ずしなければならない活動ではありませんが、この常時活動をうまく利用できると、授業の展開部分・まとめの部分につなげることができます。
常時活動がうまくいくと、授業全体がうまくいくかもしれません。ぜひ、自分の授業の中で取り入れることを考えてみてください。
この記事の内容は動画「5分で授業が整う!中学校音楽『常時活動』実践アイデア3選」をもとに作成しました。











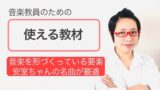



コメント