「合唱コンクールや文化祭で、専門外の学級担任の先生とどう連携すればいいのだろう?」
「担任の先生から合唱指導のアドバイスを求められたけど、何を伝えればいいか分からない…」
学校の音楽科教員の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
「学校全体で取り組む合唱行事。音楽科として嬉しい反面、担任の先生方との連携には毎年気を使う…」そんな悩みを抱えていませんか?専門外の先生との関わり方を少し工夫するだけで、行事はもっとスムーズに、そして子どもたちの音楽体験はより豊かなものになります。
この記事では、学校行事としてクラスで合唱に取り組む際に、音楽科教員が担任の先生とどのように関わっていけばよいか、具体的な3つのポイントをご紹介します。
この記事は、次のようなことを知りたい方に是非ご覧頂きたい内容です。
- 行事運営の中で音楽科とどのように関わればいいのか知りたい方
- 担任の先生にアドバイスを求められたが、何を伝えればいいのか分からず困っている方
- 担任の先生の力を上手に借りて、行事・合唱・クラスを盛り上げたい方
▼おすすめの関連動画
音楽科教員は文化祭前には、通常授業・教育実習生指導・授業外の合唱指導・部活の指導・校務分掌としての行事リーダーなど複数の役割を担います。そのための心構えをお話しました。
音楽科が担任を持った時に合唱コンクールにどう関わるか。私が実践していた、年度初めから始める自分のクラスの合唱コンの準備について紹介しています。
【ポイント1】「音楽科のこだわり」を明確に伝え、指導の主導権を握る
合唱コンクールの指導において、音楽科の授業として行う以上、音楽科教員として「譲れない部分」や「こだわり」を明確にし、事前に全体へ伝えておくことが重要です。
特に、合唱経験が豊富な先生や熱心な先生ほど、ご自身のやり方を持っている場合があります。もちろんそれは素晴らしいことですが、指導の根幹に関わる部分については、音楽科が主導権を握る必要があります。
授業で行う以上「音楽科としての評価」を明確に
まず、行事の練習を授業に盛り込む以上、それは評価の対象となります。大切なのは、合唱コンクールの順位(金賞など)がそのまま音楽科の成績になるわけではない、という点を子どもたちに明確に示すことです。
「金賞を獲ったから評価が良い」「指揮者や伴奏者だから評価が良い」といった単純な評価にならないよう、その歌唱の単元を通して「何をできるようにしたいか」という音楽科としての目標を明確に設定し、伝えましょう。
楽譜は音楽科が準備し、配布する
熱心な担任の先生ほど、善意からではありますが、曲が決まるとすぐに練習を始めたくなるものです。しかし、楽譜の準備と配布は音楽科の重要な役割です。「楽譜は音楽科教員が、いつ配布します」とあらかじめ伝えておきましょう。その際、担任の先生の分の楽譜も忘れずに準備します。
楽譜選びは、音楽科の知識と技能の見せ所です。以下の点に配慮して選定しましょう。
- 出版社の選定
- フォントやページ割り
- 大譜表の書き方(特に男性パートがヘ音記号を読み替えずに済むかなど)
- 譜めくりのタイミング
- 音符や文字の詰まり具合
- 縦書きの歌詞の有無(なければ追記する)
- ページ番号の振り直し(曲集のコピーだと指導しにくいため、通し番号を振り直す。配置場所も統一すると良い)
- 練習番号(A, B, C…)の有無(なければ指導しやすいように追記する)
これらの点にこだわって楽譜を選びたいのに、先生が独自に印刷してしまうと、指導方針と異なる指示が書き込まれている場合もあり、指導がやりにくくなる可能性があります。
模範演奏の音源は、使い方を明確に指示する
CDやYouTubeなどで手に入るパート別音源やピアノ伴奏音源も、音楽科で選定し、その使い方や位置づけを明確にしてから生徒に使わせるようにしましょう。
音源によっては、音楽科の指導の狙いに合わないものも存在します。
- 完全な打ち込み音源
- 過度なビブラートがかかっているもの
- 速度変化のある曲で、模範通りにしか歌えなくなるようなピアノ伴奏
これらの音源は、使い方を誤ると、生徒の表現の幅を狭めてしまう「劇薬」にもなり得ます。音源自体が悪いわけではなく、誰が、どのタイミングで、どう使うかが重要です。安易に模範演奏に頼らないよう注意を促しましょう。
【ポイント2】担任との「連携」で役割分担を明確にする
クラスでの合唱練習には、揉め事がつきものです。本番が近づくにつれ、クラス内で衝突が起きたり、悩み事が生まれたりすることもあるでしょう。その際に重要なのが、担任の先生との役割分担と連携です。
音楽的な問題は音楽科、人間関係は担任へ
まず、問題の種類によって窓口を分けましょう。
- 音楽科が関わること:
- 指揮・伴奏・合唱が合わない
- 拍子、速度、強弱の変化がうまくいかない
- 高音が出ない など
これら音楽的な課題には、個別レッスンや具体的なトレーニング方法をアドバイスするなど、専門家として積極的に関わっていきます。
- 担任にお任せすること:
- 練習に人が集まらない
- 真面目に歌わない生徒がいる
- 指揮者と他の生徒が揉めている など
このような音楽以外の問題については、生徒の日々の様子を最もよく知る専門家として、担任の先生の力を借りましょう。
音楽科教員は週に1回程度の関わりですが、担任は毎日生徒と接しており、クラスの人間関係や家庭環境など、圧倒的に多くの情報を持っています。何が原因で合唱に前向きになれないのか、担任の先生の方が的確に判断できる場合が多いのです。
情報共有で連携体制を築く
もちろん、担任の先生に任せきりにするわけではありません。指揮者や運営委員の生徒、そして担任の先生からクラスで何が起こっているのか情報を得て、常に連携することが大切です。
情報共有を進める中で、結果的に音楽的な課題が揉め事の原因になっていると分かれば、そこではじめて音楽科として介入していきます。担任の仕事と音楽科の仕事。この線引きと連携が、円滑な行事運営の鍵となります。
【ポイント3】担任の「教科の特性」を活かした指導を促す
経験の浅い先生や音楽が専門でない先生から、「生徒に大きな声を出させることはできても、それ以上何を指導すればいいか分からない」とアドバイスを求められることがあります。そんな時は、担任の先生の強みを引き出すチャンスです。
クラス内での復習・反復練習を依頼する
最も手っ取り早いのは「音楽科の指導を見てもらう」
担任の先生にはクラスでの復習や反復をお願いすることです。
音楽科の指導の中では、「もっとこうなってほしい」「そのためにはこれを注意して欲しい」「これを続けて欲しい」と成長への種まき、ヒントを話して、実践や積み重ねはクラスで行ってもらいましょう。
例えば強弱の幅について、サビの部分を丁寧に授業内でおこなって、「あとはクラスで、他の場所もしておいてください」と任せる。
音楽科の指導を見せ、クラスでの反復練習を依頼する
最も手軽で効果的なのは、音楽科の授業での指導を見てもらうことです。
授業の中で、表現のポイントとなる部分(例:サビの強弱の幅など)を重点的に指導し、「この部分をクラスでの練習で続けてみてください」と、復習や反復練習を担任の先生にお願いするのです。音楽科が成長への「種まき」をし、クラスでの実践や積み重ねを担ってもらうという形です。
担任の専門性を引き出すユニークなアプローチ
さらに、担任の先生の専門教科の特性を合唱指導に活かしてもらうよう促すのも非常に有効です。
- 国語科の先生: 歌詞の解釈
- 社会科の先生: 曲の歴史的・地理的背景
- 理科の先生: 音の高低や音圧の数値化
- 英語科の先生: 子音や母音の発音
- 美術科の先生: 音楽以外の表現力
- 保健体育科の先生: 発声のための筋力トレーニング
このように、先生方の専門性を活かせる場面がないか、積極的に相談を持ちかけてみましょう。思いがけないアイデアが、合唱指導の新たな突破口になるかもしれません。
自分の専門分野であれば、先生方も「待ってました!」とばかりに張り切ってくれるはずです。音楽科では考えつかないような知識や技能、解釈が飛び出すかもしれません。
【ユニークな実践例】 以前、トライアスロンが趣味だという先生が、「声量を上げるには下半身だ!」と言って、曲の始めから終わりまで生徒にスクワットをさせながら歌わせていたことがありました。歌い終わった生徒たちはクタクタでしたが、とても面白がって取り組んでおり、微笑ましい光景でした。
このように、先生方に自分の役割や立ち位置を認識してもらうことで、俄然やる気を引き出すことができます。
まとめ:感謝の気持ちを忘れず、学校全体で合唱行事を成功へ
合唱コンクールは、音楽科の授業だけで完結するものではありません。学級経営やクラス活動の一部と捉え、ある程度は割り切って指導することも必要です。
音楽科の授業では、全体の軌道修正や目標設定、具体的なトレーニング方法の提示に留め、細かい練習は学級に任せる部分があっても良いでしょう。
何よりも大切なのは、学校全体で合唱という文化に取り組むために足並みをそろえ、音楽のために多くの時間や労力を割いてくれる担任の先生方や生徒たちに感謝の気持ちを持つことです。
この記事で紹介した3つのポイントを、ぜひ明日からのコミュニケーションにご活用ください。先生が担任と手を取り合うことで、合唱行事は単なるイベントではなく、生徒の心に深く刻まれる豊かな学びの機会となることでしょう。
この記事は動画「【音楽科の悩み解決】合唱コンクール、担任との連携どうしてる?プロが教える関わり方の3つのコツ」をもとに作成しました。




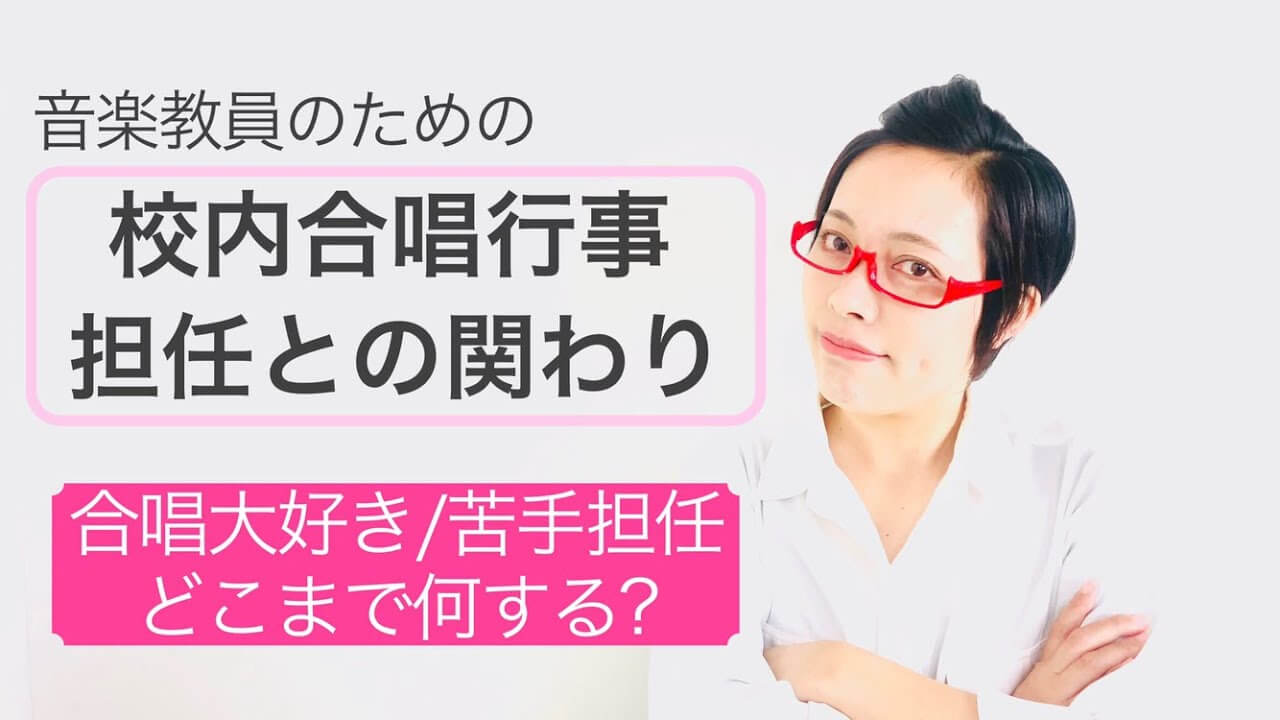






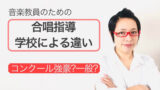
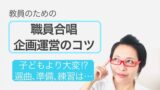


コメント