卒業式や3年生を送る会など、卒業関連の行事は、児童・生徒にとっても、教員にとっても、思い出深い大切な節目です。その感動的な雰囲気を演出し、心に残るものにするために欠かせないのが「BGM」の存在です。
しかし、いざBGMを選ぼうとすると、
「どんな曲を選べばいいんだろう?」
「児童・生徒の希望をどう取り入れたらいい?」
「CDをコピーしたり、BGMとして流したりするのは著作権的に大丈夫?」
といった疑問や不安を感じる放送担当の先生や音楽科の先生も多いのではないでしょうか。
この記事では、学校行事、特に卒業関連行事におけるBGMの選曲方法から、意外と知られていない著作権のルールまで、教育現場で役立つ情報と提案を分かりやすく解説します。
誰の心に届けたい?BGM選曲で最も大切な2つの視点
行事のBGMを選ぶ上で最も重要なのは、誰のためのBGMなのか、その「対象」を明確にすることです。特に卒業関連行事では、以下の2つの対象の意向を汲み取ることが、成功への第一歩となります。
最優先は卒業生の「学年の意向」
何よりもまず優先すべきは、主役である卒業生、つまり小学校なら6年生、中学校なら3年生の意向です。
- 学年の思い出の曲 3年間あるいは6年間の学校生活で、歌ったり、合奏したり、運動会で踊ったりと、様々な場面で使われた曲があるはずです。そうした学年全体の思い出と関連付けて選曲することで、卒業生たちの心に深く響くBGMになります。
- 学年のテーマソング 学年によっては、「この学年のテーマソングはこれ」というように、特別な一曲を決めている場合もあるかもしれません。そうした曲を適切なタイミングで流すことで、一体感のある感動的な雰囲気を生み出すことができます。
見落とせない「担任の思い入れ」
学年の意向と同じくらい重要なのが、卒業生を一番近くで見守ってきた担任の先生の思い入れです。
- クラスの思い出の曲やテーマソング 学年だけでなく、クラス単位での思い出の曲やテーマソングがあるかもしれません。
- 先生が伝えたい曲 たとえクラスで歌ったり演奏したりしたことがなくても、「この歌詞を伝えたい」「この曲が好きなんだ」と先生が語っていた曲や、先生の好きな歌手の曲なども候補になります。
学級を持つ担任の先生方がどのような曲を流したいと考えているか、ぜひ事前にヒアリングしてみてください。
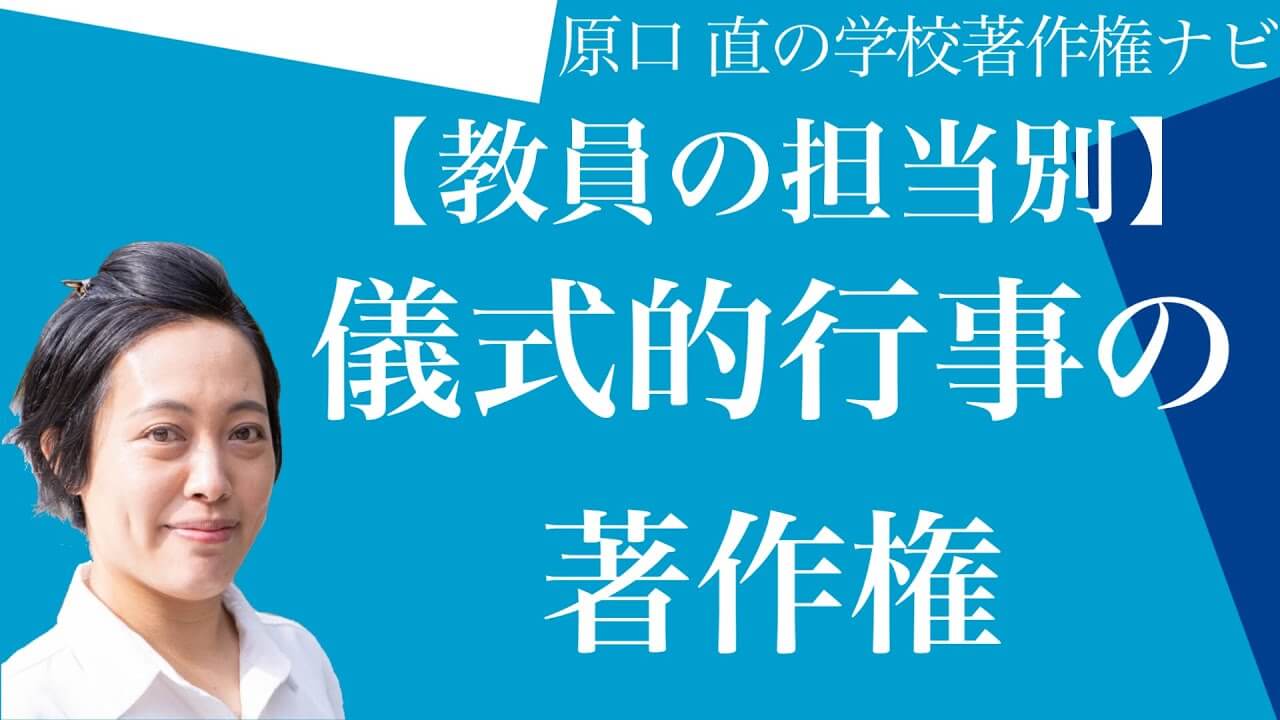
「何でも良い」と言われたら?音楽の要素から考えるBGM選曲法
学年の先生や管理職の先生から「BGMは何でも良いよ」「何か案を出してほしい」と依頼されることもあるでしょう。そんな時に役立つ、BGM選曲の3つの視点をご紹介します。
押さえておきたい「定番曲」の探し方
世代を超えて愛される卒業ソングの「定番」は、多くの人が共有できる感動を生み出します。定番曲を探すには、以下のような方法があります。
- 音楽科教員向け雑誌を参考にする 音楽の友社が発行する「教育音楽」(小学校版/中高版)では、時期になると卒業式で歌う曲や演奏する曲のアンケート結果が発表されます。これは信頼性の高い情報源です。
- WebやSNSで検索する Googleで「卒業式 定番曲」と検索したり、SNSで「#定番卒業ソング」といったハッシュタグで調べたりすると、たくさんの候補が見つかります。
- オムニバスCDの収録曲を確認する 「卒業式にかけたい」といったテーマで編集されたCDのラインナップを確認するのも、定番曲を探す上で非常に有効な方法です。
今どきの「トレンド曲」を知るには?
定番だけでなく、その年ならではの「トレンド」を取り入れるのも良いでしょう。
- 検索ワードに工夫を加える 定番曲と同様にWeb検索が有効ですが、その際に「#令和」や「#トレンド」といった言葉を加えて検索すると、より現代的な選曲のヒントが得られます。
- 児童・生徒に直接聞く 最も効果的なのは、やはり子供たちに直接聞くことです。
「子供の希望」を聞く際の重要なポイント
子供たちの希望を募る際には、単なる人気投票で終わらせないための工夫が必要です。
- 対象と場面を具体的に提示する 「どんな曲を流したい?」と漠然と質問するのではなく、「卒業生が入場してくるとき」「花道を作って卒業生を送るとき」など、誰のために、どの場面で流すのかを具体的に示して質問しましょう。
- 選曲の理由を添えさせる なぜその曲を選んだのか、理由をきちんと説明させることが大切です。その際、次に紹介する「音楽を形作っている要素」の言葉を使って説明するように指導すると、より深い学びにつながります。

BGM選曲の根拠を示す「音楽を形作っている要素」とは
「なんとなく雰囲気が良いから」といった曖昧な理由だけでなく、音楽の専門家として選曲の意図を明確に説明できれば、他の教員や保護者からの理解も深まります。
そこで役立つのが、学習指導要領にもとづく『音楽を形作っている要素』という視点です。 これは音楽の授業で日常的に使われている言葉であり、放送担当の先生にもぜひ知っていただきたい視点です。
| 要素の言葉 | 具体的な例 |
|---|---|
| 音色 | 声、楽器の種類 など |
| 速度 | 曲の速さ(設定された速さ、その変化) など |
| テクスチュア | 音の重なり、組み合わせ など |
なぜ定番?「カノン」を音楽の要素で説明する
例えば、卒業式の定番曲であるパッヘルベルの「カノン」は、なぜ卒業式にふさわしいのでしょうか。この「音楽を形作っている要素」の言葉を使って説明すると、以下のようになります。
「弦楽器の音色がとても美しく、複数の弦楽器の旋律が重なり合っている(テクスチュア)。また、ゆったりとした速度の設定が厳かな卒業式に合っている。同じようなコードの繰り返し(反復)がある点も特徴だ。」
このように説明することで、漠然としたイメージが具体的な根拠を持った選曲理由になります。ぜひ、同じように「G線上のアリア」がなぜ卒業式にふさわしいのか、これらの言葉を使って考えてみてください。
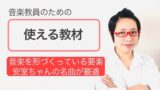
これだけは知っておきたい!行事BGMと著作権のルール
BGMを利用する上で避けては通れないのが「著作権」の問題です。最後に、学校行事における著作物の扱いについて、法律に照らして考えてみましょう。 (※著作権法第35条や第38条の基本については、「原口直の学校著作権ナビ」のYoutube動画・ウェブサイト、著作権情報センター(CRIC)・JASRACなどの情報を参考にしてください。。)
重要なのは「どの音源か」「誰がどの場面で流すか」「映像や音声を形に残すか」という点です。卒業式という学校行事は「授業」の一環と見なされるため、授業での利用を定めた著作権法第35条が適用される場面が多くあります。
許諾が「不要」なケースと「必要」なケース
【許諾が不要な場合】
- BGM用に市販のCDをコピーする 学校行事の範囲内であれば、教員や児童・生徒がBGMとして利用するために、学校で購入したCDなどをコピーすることは許諾不要で行えます。(著作権法第35条)
- 市販のCDを入退場BGMとして流す 非営利・無料・無報酬の演奏に該当するため、許諾は不要です。(著作権法第38条)
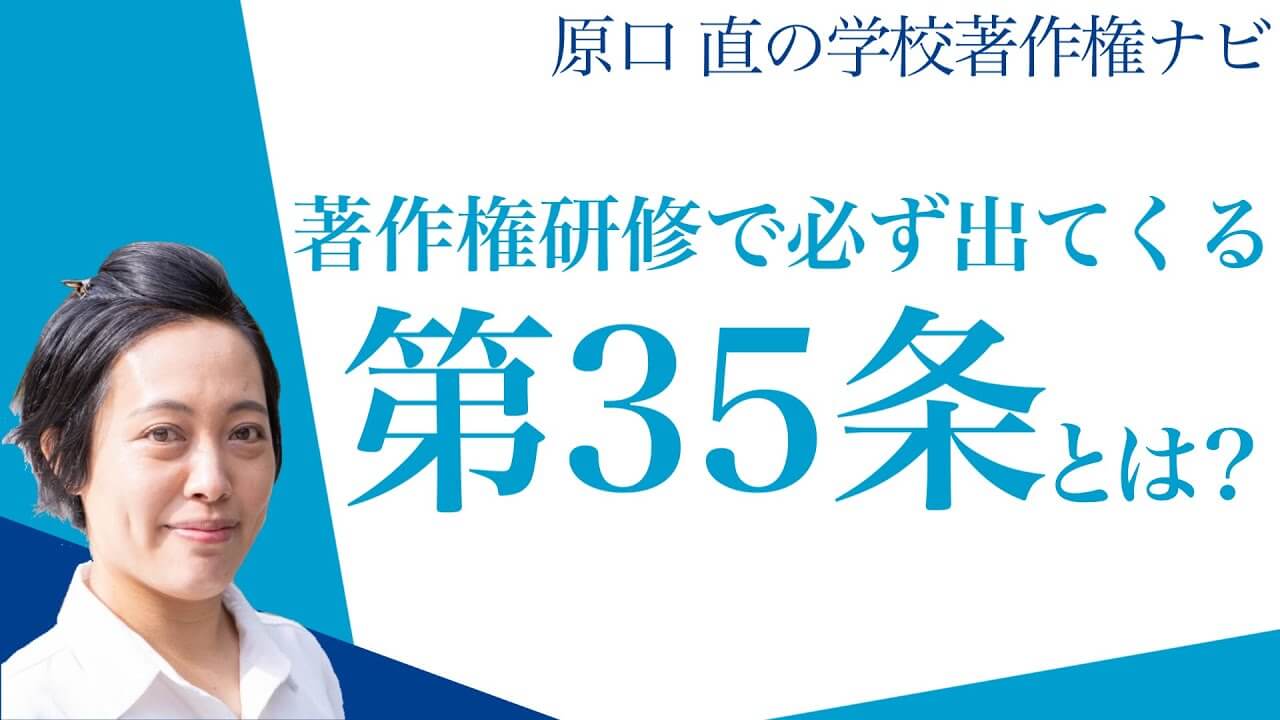
【許諾が必要な場合】
- 記念DVDなどにするために録画・録音する
- 式の動画を学校のホームページにアップする
これらのケースは、不特定多数への公開や、授業の範囲を超えた利用(複製物の配布)と見なされるため、著作権者の許諾が別途必要です。無断で使用すると著作権侵害にあたる可能性もありますので、使用料などを事前に確認・申請しましょう。
【要注意】YouTubeやサブスク音源の利用
近年質問が多い音源の取得方法についても確認が必要です。
- YouTubeからのダウンロード これは違法です。絶対に行わないでください。
- サブスクリプションサービス(Spotify, Apple Musicなど) これらのサービスは、基本的に個人が楽しむために契約し、料金を支払っています。学校のような場で利用できるかどうかは、各サービスの利用規約で定められています。必ず自身が契約しているサービスの利用規約を確認し、「個人での利用に限る」と記載されている場合は、学校で利用できない可能性があるため、十分注意してください。
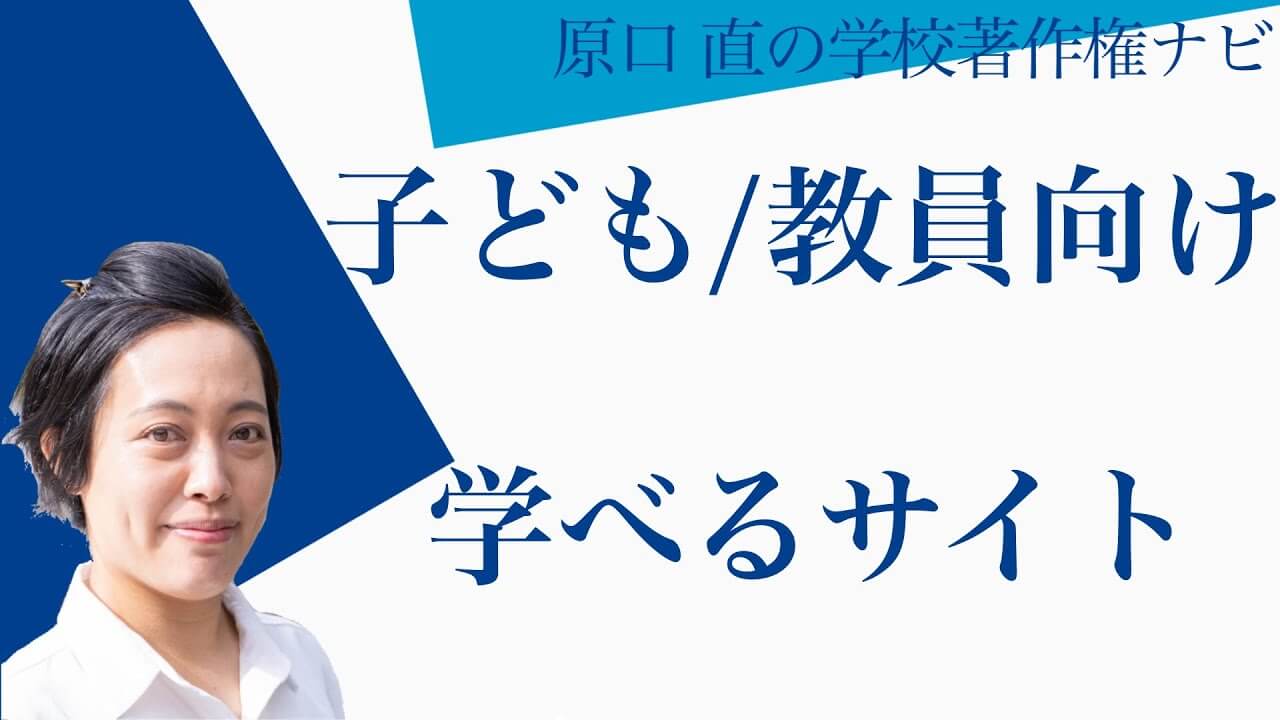
まとめ
卒業式は、卒業生はもちろん、学校全体にとっての晴れの舞台です。音楽は、その舞台を感動的に盛り上げたり、時にはしんみりとした雰囲気を作ったりと、大切な演出の役割を担います。
適切な選曲と正しい知識は、先生方が安心して卒業式の演出に集中するための土台となります。この記事でご紹介した視点を参考に、子どもたちの心に深く刻まれる、世界に一つだけの素晴らしい卒業式を創り上げてください。
この記事は動画「卒業式の感動を演出!学校行事のBGM選びと著作権ルール解説」をもとに作成しています。





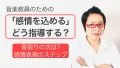

コメント