文化的行事や卒業関連行事で恒例となっている「職員合唱」。生徒たちは毎年楽しみにしている一方で、企画を担当する先生にとっては、子どもたちへの指導とは全く違う準備や気遣いが求められ、頭を悩ませることも多いのではないでしょうか。
この記事では、多忙な業務の合間を縫って担当することになる先生方のために、企画する立場・出演する立場の両面から、負担を減らしつつ成功させるための具体的なコツを解説します。
この記事の他には以下もおすすめです
文化祭や合唱コンクールといった文化的行事で気を付けるべきこと…マルチタスクを意識したスケジュール管理、「郷に入っては郷に従え」の気持ち、音楽科の関わり方について話しています。
「儀式的行事の著作権」を教員の担当別に解説した動画です。行事に欠かせない著作権の知識を解説しました。
併せてご覧ください。
職員合唱を成功させるための大前提
まず、職員合唱の企画を始める前に押さえておきたい3つの前提についてお話しします。
結論:何をやっても絶対にウケる!
演目選びで悩む必要はありません。結論から言うと『何をしたって受けます』。
普段は真面目で厳しい先生が、急に真剣に歌ったり、仮装やダンス、コントをしたりすれば、それだけで間違いなく盛り上がります。生徒たちは、先生方のいつもとは違う一面を見ることを楽しみにしているのです。
まずは目的を明確に。「笑い」か「感動」か?
演目を選ぶ上で最初に考えたいのは、「何を求めるか」です。
子どもたちを笑わせたいのか、それとも泣かせたい(感動させたい)のか。もし両方を求めるのであれば、そのバランスと、プログラムの最初と最後を何にするかが重要になります。
また、高いクオリティの合唱やダンスを目指す場合は、曲数を絞って集中できる環境を作りましょう。先生方はアイデアが豊富なため、あれもこれもと演目が増えてしまいがちですが、まずは目的を一つに定めることが成功への鍵です。
演目は「時事ネタ」と「時間厳守」を意識する
複数の演目を考えたい場合におすすめなのが「時事ネタ」です。
YouTubeやSNS、あるいは生徒たちに直接聞くなどして、今どんな曲やダンス、お笑いが流行っているかをリサーチしましょう。パロディーは元ネタを知っているからこそ共感し、笑いが生まれます。ただし、あまりにハードルが高いものではなく、すぐに真似できるものを選ぶのがポイントです。
そして、最も重要なのが「時間」です。行事において、予定時間が延びることは最も避けたい事態です。タイムスケジュールが厳密に決まっている文化的行事では、一つの遅れが後の演目や下校時刻にまで影響を及ぼします。
職員合唱では、
- 準備に時間がかかりすぎる
- 集合時間に全員が集まらない
- 盛り上がりすぎて収拾がつかなくなる
といったことが起こりがちです。持ち時間が20分と決まっているなら、登場から退場、準備、片付けまで、すべてを含めて時間を計算しましょう。
成功の鍵を握る「企画」の進め方
前提を押さえたら、具体的な企画に入ります。ここでは、企画を円滑に進めるための3つのコツをご紹介します。
主導権は1人か2人の少人数で握る
初めて担当になったり、「毎年盛り上がるから」というプレッシャーを感じたりすると、広く意見を求めたくなりますが、主導権は1人か2人の少人数で持つことをお勧めします。担当者が多いと、その都度相談や承認が必要になり、小回りが利きません。
文化的行事の準備期間中、先生方は学級や教科、委員会、部活動のことで非常に忙しく、子どもたちの活動が最優先です。そのため、職員合唱の優先順位は自然と低くなります。しかし、それでもクオリティを求めてしまうのが職員合唱。だからこそ、主導権を持つ人を絞り、迅速に動ける体制を作ることが重要なのです。
選曲とパート分けのコツ
選曲:流行曲より「定番曲」がおすすめ
合唱曲を選ぶ際は、初見の流行曲よりも、先生方自身や生徒たちがすでに知っている曲を選ぶと良いでしょう。例えば、「大地讃頌」「旅立ちの日に」「翼をください」といったクラシカルな合唱曲です。
定番曲を選ぶメリット
- 年齢層の幅に対応できる
- 練習時間が少なくて済む
- 生徒の練習を何度も聞いているため、先生方も曲をよく知っている
- 生徒のパート練習に付き合って、すでに歌える先生もいる
カラオケ形式の少人数での歌唱や、ダンス・コントを伴う演目であれば流行曲も良いですが、全員で歌うのであれば定番曲が確実です。
パート分け:自己申告を尊重しつつ、最終的には企画者が割り振る
先生方の中には、歌が好きな人もいれば苦手な人もいます。「歌は下手だから」と謙遜する方もいますが、実は先生方は歌が上手な人が多い傾向にあります。普段から大きな声を出しているため、腹式呼吸ができているのです。
パート分けは、まず自己申告を尊重しましょう。その上で、それぞれの技量を見極め、企画者や音楽科の先生が最終的に割り振るのがスムーズです。
企画内容は「8割」固めておく
企画を提案し、練習を進めていると、他の先生方から「こうしたらどうか」「これも入れたらどうか」「これはできない」といった様々なアイデアや意見が出てきます。これは、より良いものにしたいという気持ちや、先生方自身のクリエイティブな力が溢れ出てくるためです。
しかし、100%完璧に企画したものが次々と変更されると、企画者は「考えた時間は何だったのか…」と悲しくなってしまいます。
そこで、企画の骨子は『8割方』固めておき、残りの2割を『皆で作り上げる余白』と捉えましょう。この進め方が、企画者の精神的な負担を減らし、チームの満足度も高めるコツです。
最も大変な「準備・練習」を乗り切る方法
企画が固まったら、いよいよ準備と練習です。しかし、ここが最も大変な段階かもしれません。
心構え①:『全員が揃うのは本番だけ』と割り切る
まず、心構えとして「全員が揃うのは本番だけ」と思っておきましょう。リハーサルもゲネプロもありません。
文化的行事の準備期間中、先生方は日々の授業に加え、展示の準備、委員会の活動、部活動の指導など、多くの校務を抱えています。さらに、行事にはつきものの学級の揉め事(練習に来ない、締め切りを守らない等)の対応にも追われます。学級担任、学年の先生、教科担任、部活の顧問…皆が生徒指導で大変な状況です。
職員合唱の優先順位は一番下。練習日時を決めても、音楽室に来たのが一人だけ、ということもあり得ます。また、時短勤務の先生や、勤務時間内(17:00まで)での活動を希望する先生もいるため、全員が集まるのは極めて困難です。
指導の難しさ②:参加できない人への個別フォローが必須
練習に参加できない人や、歌が苦手な人へのフォローも重要です。個別でレッスンをしたり、練習用の音声や動画を作成したりといった対応が必要になります。
先生方は忙しいため、「教えてください」と自ら来てくれるのを待つのではなく、企画者側から積極的に動く必要があります。
指導の難しさ③:相手は「子ども」ではなく「同僚」
練習中の指導も大変です。
集まって私語がやまない、段取りを説明していても聞いていない、楽譜を失くす、歌った後すぐに喋る…。相手が子どもであれば注意できますが、同僚である先生方にはそれができません。企画者としては、限られた時間で焦る気持ちもありますが、なかなかうまくいかないのが現実です。
企画者のための自衛策:ハードルを下げ、クオリティは求めすぎない
このような状況を乗り切るためにも、演目の選択が重要になります。企画者の首を締めないためにも、なるべくハードルの低いものを選びましょう。
- フォーメーションが複雑なダンスは避ける
- セリフの掛け合いが多いコントは避ける
「何をやってもウケる」のですから、過度なクオリティは求めないことが大切です。
まとめ:音楽科教員の最適な関わり方
これまで職員合唱の企画から準備までのコツをお伝えしてきましたが、最後に、特に音楽科の先生がどう関わるべきか、そして今後の職員の出し物のあり方について触れます。
文化的行事において、音楽科の教員は多くの場面で中心的な役割を担います。そのため、職員合唱の企画担当からは外してもらうことが最善策かもしれません。「担当は外れるけれど、合唱指導やパート音源作りは手伝います」といった関わり方が理想的です。
また、オンラインで行事を行うことが増えた昨今、職員の出し物のあり方も変化しています。動画を作成するのも一つの手ですが、企画・撮影・編集には膨大な時間がかかり、担当者の負担は計り知れません。もし動画にする場合は、リレー形式で歌を繋いだり、各自で撮影した動画を集約したりするなど、編集の手間がかからない工夫が必要です。
そして、オンラインで配信する際は、著作権への意識を忘れてはなりません。行事のオンライン配信に関する著作権の知識は、これからの学校行事に不可欠です。
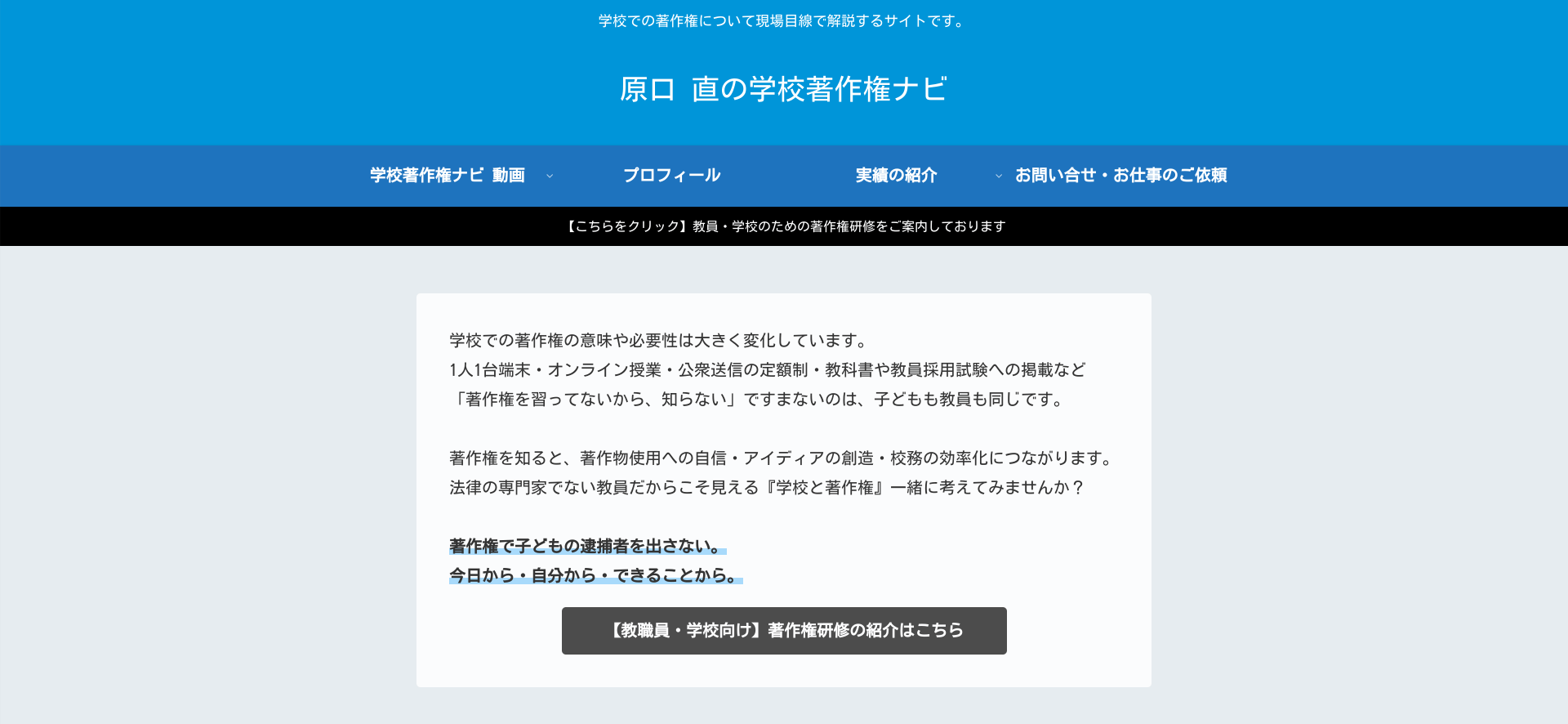
職員合唱は、生徒たちにとって先生方の意外な一面に触れる貴重な機会であり、忘れられない思い出の一つになります。完璧を目指す必要はありません。この記事で紹介したポイントを参考に、先生方自身がまず楽しみ、その楽しさを生徒たちに届けるつもりで、最高の出し物を作り上げてください。
この記事は動画「【あるある】「練習に誰も来ない…」職員合唱の担当者が絶望する前に見る動画」をもとに作成しました。




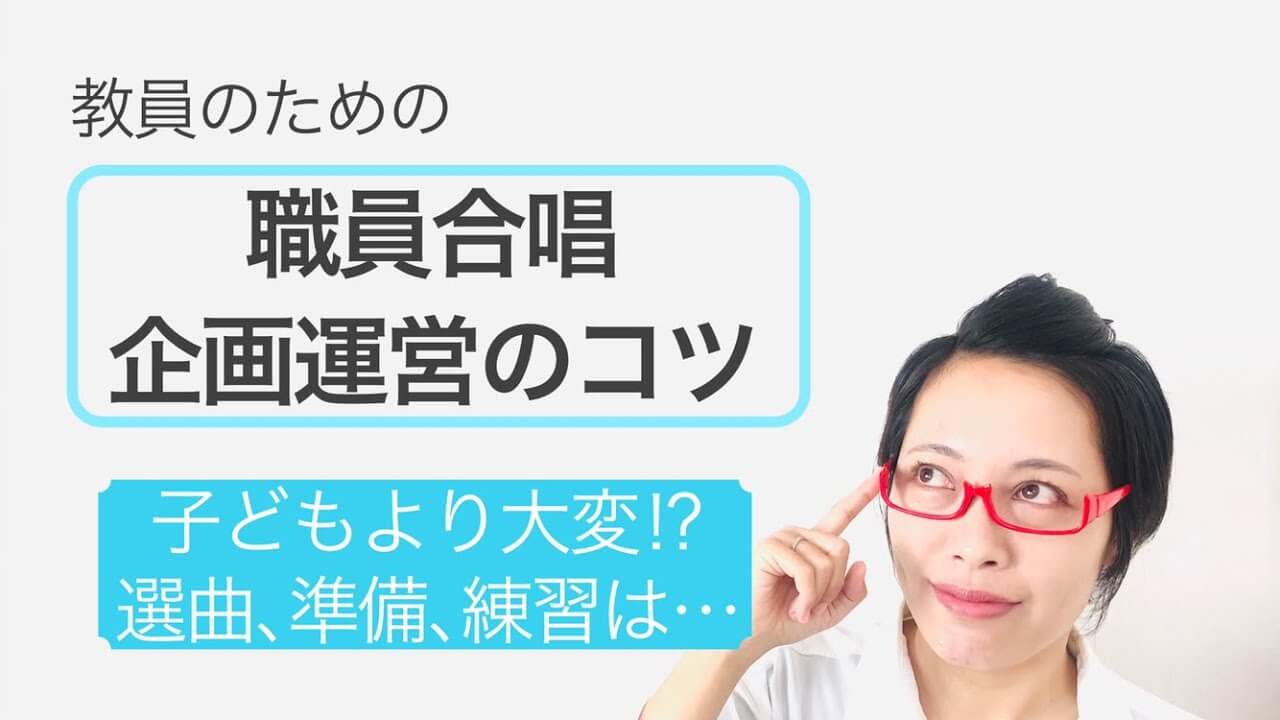

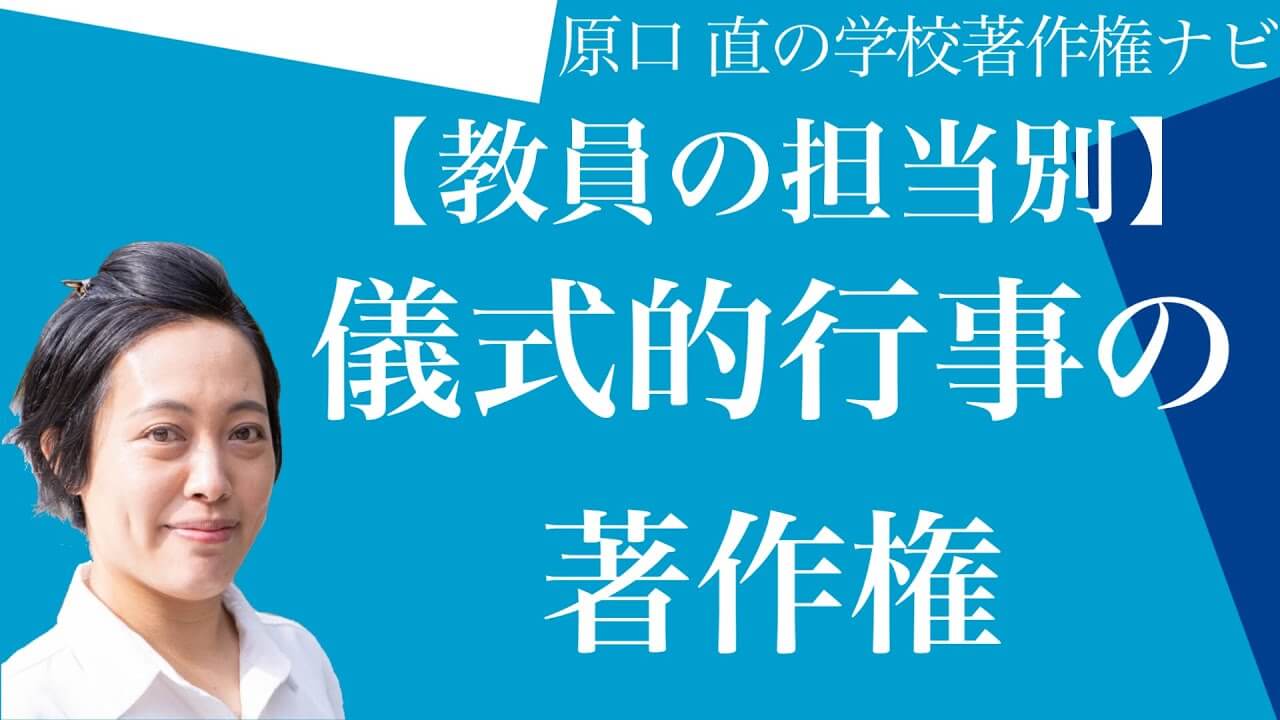
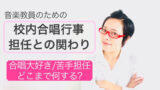


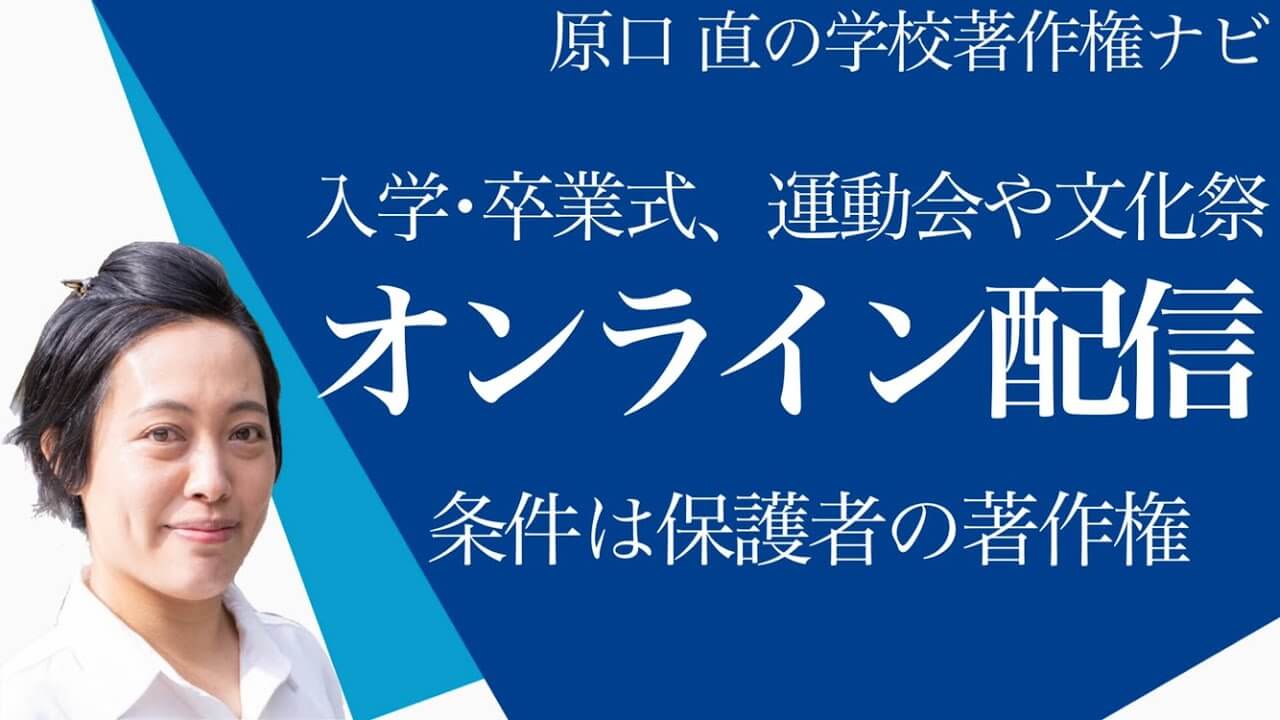


コメント