今回は、音楽教育・音楽学・作曲などを専攻する学生の皆さんに向けて、教育実習において気をつけてほしいポイントをお話しします。
合唱指導に対する心構え
教育実習では合唱指導が入る場合があります。歌やピアノにあまり自信がないという方もいるかもしれませんが、ぜひ自信を持って取り組んでください。
普段、声楽専攻の学生の独唱や合唱を聞く機会が多いため、自信をなくしてしまうかもしれませんが、生徒よりはもちろん上手いんです。努力をきちんとして、自信を持って生徒の前に立って歌ってください。
自信がないと思ってしまうと、それは行動や表情に必ず表れます。そして生徒はそれを敏感に察知します。自分なりに努力をして、自信を持って歌う姿勢が大切です。
鑑賞授業での注意点:語りすぎない
次にお伝えしたいのは「語りすぎない」ことです。
特に鑑賞の授業では、自分が専攻してきたことや研究してきた内容を授業に活かそうとするあまり、熱がこもって語りすぎてしまうことがあります。
このとき注意すべきなのが、ワークシートや板書、PowerPointの作り方です。文字をたくさん使いすぎずに、「不親切なワークシート」「不親切なPowerPoint」を作ってほしいと思います。これについては他の動画でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
■音楽教員のためのワークシートの作り方
■音楽教員のための板書の仕方
■音楽教員のためのパワポの使い方
■音楽教員のための板書とパワポの使い分け
好きなことだからこそ語りすぎてしまうのですが、一つの授業で教える内容は1つ、あっても2つ程度と考えてください。学習指導案を作成する際は、自分のしゃべりと生徒の活動が、50分の授業のうち半々ぐらいであるかというのがひとつの目安です。
生徒が主体的に考えたり、話し合ったり、意見を発表したりする時間がきちんと授業内で確保されているかを意識して、指導案を作ってみてください。
生徒との関わり方:積極的に飛び込む
3つ目のポイントは、生徒の中に積極的に飛び込むということです。普段研究をしていると、どうしても一歩引いて俯瞰して見たり、分析しようとしたりする傾向がありますが、実習の期間中はその視点を一旦脇に置きましょう。
子どもと同じ目線で接し、時にはハメを外してバカなことを言って笑い合うことも大切です。研究や分析だけでは身につけられないこと、わからないことが学校にはたくさんあります。それをぜひ楽しんで体験してみてください。
「全員に好かれなくてOK!信頼される先生になる3つのヒント」
少ない授業数での生徒との関わり方、距離の取り方について話をしました。「音楽教員のキャラクターづくり5つの秘訣|生徒との距離をグッと縮める方法」
どのようなポイントでキャラクターを作ったらいいか、もしくは持っているキャラクターを活かしたらいいか、ということを話しています。
おわりに
今日は、音楽教育・音楽学・作曲などを専攻する皆さんに向けて、教育実習で気をつけるべき3つのポイントをお話ししました。
- 合唱指導に自信を持つこと
- 鑑賞授業で語りすぎない工夫をすること
- 生徒の中に積極的に飛び込むこと
これまでに身につけてきた知識や技術、そして専門的な視点は、教育実習でも必ず活かされます。自分の専門性を発揮できるよう、しっかりと準備を進めていきましょう。
この記事は動画「【教員を目指す人へ】音楽教育・音楽学・作曲などを専攻する教育実習生に送るアドバイス」をもとに作成しました。










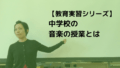
コメント