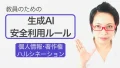この記事では、学校教育現場で生成AIをより効果的に活用するための「プロンプト作成」に焦点を当て、その基本から実践までを解説します。
生成AIをまるで自分の思い通りに動かす車のように乗りこなすための「運転技術」を身につけ、日々の業務に役立てていきましょう。
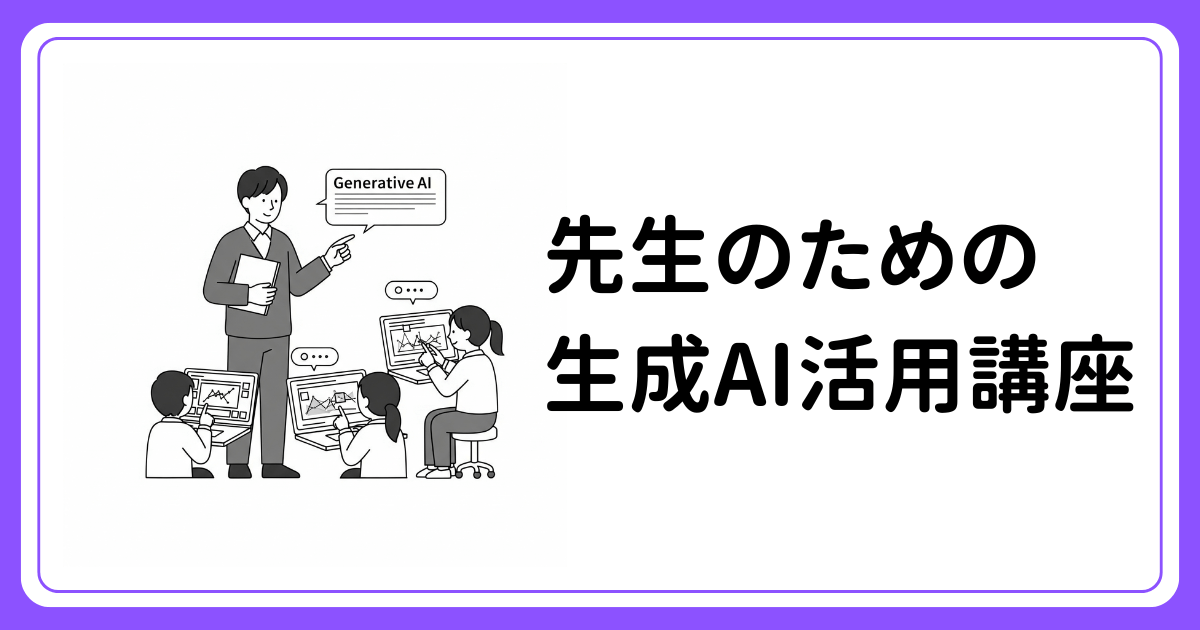
授業や校務で使える実践的な生成AI活用法を紹介。コピペして使えるプロンプトやリスク対策も含めて、生成AI初心者でも生成AIがすぐに使えるよう分かりやすく解説しています。
プロンプトとは何か?AI活用の効果を飛躍的に高める鍵
プロンプトとは、生成AIへの「お願いの仕方」や「指示の出し方」のことです。
AIに質問しても期待外れの答えしか返ってこない、もっと気の利いた答えが欲しいけれどどう頼めばいいか分からない、といった経験はありませんか?
それは、生成AIの能力が低いのではなく、私たちの「お願いの仕方」に工夫の余地があるだけかもしれません。
この記事でご紹介する効果的なプロンプトの作り方を習得すれば、生成AIから質の高い回答を引き出すことが可能になり、今後のAI活用の効果が文字通り飛躍的に高まります。
【重要】生成AI利用にあたっての注意点
- 情報の鮮度: 生成AIは日々進化しており、精度、機能、利用規約が変わる可能性があります。常に最新情報を各自で確認するようにしてください。
- 解釈の多様性: 生成AIに関する考え方や受け取り方には個人差があります。本記事は理解を助けるための一資料であり、現場での運用方法は所属する学校や自治体の方針にも左右されます。必ずしも正解を提示するものではない点にご注意ください。
- ご自身の教育観との照合: 動画の内容は生成AIの可能性と課題を分かりやすく伝えることを目的としています。ご自身の教育観、教科の特性、児童生徒との関わり方を照らし合わせながら、活用方法を検討してみてください。
良いプロンプトの3つの基本要素:役割・文脈・条件
AIを自在に操るための最初のステップとして、良いプロンプトに共通する3つの基本要素を理解しましょう。AIへの指示が上手な人は、無意識のうちに以下の3つの要素を取り入れています。
役割(Role)
生成AIに「あなたはプロの編集者です」「あなたは経験豊富な小学校の先生です」といった具体的な「役割」を与えることで、その立場にふさわしい専門的な視点で回答を引き出すことができます。
文脈(Context)
これから何について話すのか、どんな状況で使うのかといった「前提となる背景の情報」を伝えることで、生成AIと目的意識が共有され、回答のずれが少なくなり、的確な答えを得やすくなります。
条件(Condition)
生成AIに守ってほしい「ルールや制約」を具体的に指示することです。「箇条書きで」「300字以内で」「小学生にも分かる言葉で」といった条件を設けることで、出力の形式をコントロールし、求める形式の回答を得ることができます。
この「役割」「文脈」「条件」の3つを意識するだけで、生成AIの回答は劇的に向上します。
実践!悪い例と良い例で比較するプロンプト作成術
実際にプロンプトの質で回答がどう変わるのかを見ていきましょう。
ここでは、中学校の音楽の先生が鑑賞の授業で生徒の興味をひくような発問を考えたい場面を例に比較します。
悪いプロンプトの例:「魔王の鑑賞の授業で使える発問を考えて」
この漠然としたプロンプトでは、「この曲は物語、声の使い分け、緊張感の高まりがポイント」といった一般的な解説と、いくつかの発問がテーマごとに3問ずつ提案されました。
これでも一定の回答は得られますが、より具体的なニーズには応えきれません。
良いプロンプトの例:役割・文脈・条件を明確に設定
次に、役割・文脈・条件の3要素を明確に示したプロンプトを見てみましょう。
【プロンプト例】
あなたは経験豊富な中学校の音楽の先生です。
生徒たちはクラシック音楽にあまり馴染みがなく、集中力が続きにくい傾向があります。
シューベルトの歌曲『魔王』の鑑賞授業で使える発問を考えてください。生徒たちが登場人物の気持ちに入り込み、情景をイメージしやすくなるような発問を5つ、難易度が低い順に提案してください。
【役割】 「あなたは経験豊富な中学校の音楽の先生です。」
【文脈】 「生徒たちはクラシック音楽にあまり馴染みがなく、集中力が続きにくい傾向があります。」
【条件】 「シューベルトの歌曲『魔王』の鑑賞授業で使える発問を考えてください。生徒たちが登場人物の気持ちに入り込み、情景をイメージしやすくなるような発問を5つ、難易度が低い順に提案してください。」
この具体的なプロンプトに対して、ChatGPTは難易度を5段階に分けて、易しい方から難しい方へ段階的に発問を提示してくれました。
「どんな人が出てきましたか?」「子供の声を聞いた時にどんな気持ちが伝わってきますか?」といった導入しやすい質問から、「ピアノの伴奏から馬の疾走感や緊張感をどう感じますか?」「父親と子供の気持ちはどう変わったと思いますか?」といった深い考察を促す質問まで、授業の流れを意識した具体的な発問が生成されました。
さらに、ChatGPTは「授業をするのは1年生・2年生どちらでしょうか?」「発問の言葉遣いをさらに調整できますよ」といった、次の質問を提案してきました。
ここで「1年生」と答えると、「できるだけ短く優しい言葉、イメージが湧くような問い」に調整された発問が提供されます。また、「3年生」と聞くと、その学年に応じた2つの異なる発問例を提示し、「どちらがお好みですか?」と選択を促すなど、対話を通じてより適切な回答を導き出すことが可能です。
このように、プロンプトに役割、文脈、条件を加えることで、生成AIは目の前の生徒の実態や授業形態に合わせた、より具体的で質の高いアイデアを提供してくれます。
応用例:体育指導での活用
この「役割・文脈・条件」のフレームワークは、音楽科だけでなく全ての教科に応用可能です。例えば小学校の体育指導であれば、以下のように活用できます。
【プロンプト例】
あなたは小学校の体育指導の専門家です。雨で体育館が使えない日のために、教室でできる楽しくて安全な運動のアイデアを、準備物が少ないものから3つ提案してください。
【役割】あなたは小学校の体育指導の専門家です。
【文脈】雨で体育館が使えない日のために、
【条件】教室でできる、楽しくて安全な運動のアイデアを、準備物が少ないものから3つ提案してください。
ぜひ、ご自身の校種・教科でこのフレームワークを試してみてください。
困った時のお助けプロンプト:AIに質問させる裏技
そもそも、どんな条件を指示すれば良いか分からない、という時もあるかもしれません。そんな時は、生成AIに質問させるという「裏技」を活用しましょう。
【プロンプト例】
私は中学校の教員です。
これから生成AIを使って、定期テストの問題作成を効率化したいと考えています。
質の高い問題を作成するために、私があなたに与えるべき指示や情報には、どのようなものがありますか?箇条書きで教えてください。
お助けプロンプトの箇所: 「質の高い問題を作成するために、私があなたに与えるべき指示情報にはどのようなものがありますか?箇条書きで教えてください。」
このように質問すると、生成AIは指示項目をリストアップしてくれます。例えば、音楽科のテスト問題作成について尋ねると、「出題の範囲・形式・配点・難易度」や「重要な評価の部分」、あるいは「避けたい出題形式や内容」など、多岐にわたる項目を提示します。さらに、生徒の特徴や模範解答の有無、年度ごとの条件といった、細かな設定についても問いかけてくれることがあります。
ChatGPTが具体的に単元とテストに入れたい問いの種類を聞いてくれるので、そこから試作問題を作成してもらうことも可能です。例えば、単元名を「シューベルトの歌曲」、学年を「1年生」、問いの種類を「記述式」と設定すると、記述式問題の出題例を具体的に提示してくれます。
このように、生成AIは「壁打ち相手」として非常に優れています。自分が出した問いに対して疑問をぶつけてもらい、それに応えることで、さらに質の高いアイデアや問題を共に作り上げていくことができます。分からなくなったら、まず生成AIに質問してみることから始めてみましょう。
まとめ:プロンプト作成は「最強の武器」
この記事では、生成AIを効果的に活用するための「プロンプト作成」について、良いプロンプトの3つの基本要素(役割・文脈・条件)、実践的な良い例と悪い例の比較、そして困った時のお助けプロンプトをご紹介しました。
プロンプトの作成スキルは、一朝一夕で完璧になるものではありません。しかし、今回ご紹介したフレームワークを意識して2、3回試していただければ、必ずコツがつかめてきます。これらのプロンプトスキルは、今後の動画で紹介するような複雑な業務を生成AIで活用していくための「最強の武器」となります。
ぜひ今回の「魔法の呪文」であるプロンプトを使いこなし、生成AIをもっと頼れるパートナーに育てていってください。そして、空いた時間を教材研究や子どもたちとの関わり、そのための時間として有効に活用しましょう。
この記事は、動画「【AIが期待外れ?】AIの回答が劇的に変わるプロンプト術|先生のための生成AI活用講座⑤」をもとに作成しました。