『もっと感情を込めて歌って』
『気持ちを込めて演奏しよう』
——音楽の授業で誰もが耳にするこの言葉。しかし、いざ『感情を込める』ことを具体的にどう指導すればよいか、悩んだ経験はありませんか?」
しかし、いざ「感情を込める」ことを、特に中学生に具体的に指導するとなると、どのように伝えればよいか悩む場面も少なくありません。
この記事では、学校での教育研究の経験を持つ筆者(声楽専攻、合唱・吹奏楽経験者)が、歌唱指導における「感情を込める」ための具体的な指導法を3つのステップで考えていきます。
音楽経験や専門によって様々な考え方があると思いますが、日々の授業のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
この記事は、こんな先生・学生さんにおすすめです。
- 歌唱指導で、音取りの次のステップに悩んでいる方
- 楽譜に書かれた強弱記号の理由を深く考えたい方
- 「感情を込める」とはどういうことか、中学生に具体的に指導する方法を知りたい方

感情を込めるための指導ステップ1:5W1Hでストーリーを考える
感情を込める指導の第一歩は、歌詞の「ストーリーを考える」ことです。その際に有効なのが「5W1H」というフレームワークです。
なぜ『5W1H』が感情表現の第一歩になるのか?
5W1Hは、国語の作文や社会科のプレゼンテーションなどでも用いられる、情報や物事を整理・伝達するための6つの基本要素です。
- When(いつ)
- Where(どこで)
- Who(誰が)
- What(何を)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
この6つの視点で歌詞を読み解き、「作詞者は、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにしてこの詩を書いたのか」「どのような情景なのか」というストーリーを具体的に描いていきます。
教科書の歌詞で実践!5W1Hの活用例
生徒たちに実際に考えてもらうことで、歌詞の世界がより鮮明なストーリーや情景として浮かび上がってきます。
- 【中学1年生】赤とんぼ(三木露風 作詞)
夕やけ小やけの 赤とんぼ 負われて見たのは いつの日か
- この詩の情景は「いつ」のことだろう?
- 「どこで」見ている風景だろう?
- 「誰が」見ているのだろう?
- 【中学2年生】夏の思い出(江間章子 作詞)
夏がくれば 思い出す はるかな尾瀬(おぜ) 遠い空
- この詩の季節は「いつ」だろう?
- 「どこ」の思い出だろうか?
- 「誰が」思い出しているのだろう?
- 【中学3年生】花(武島羽衣 作詞)
春のうららの 隅田川 のぼりくだりの 船人が
- この詩は「いつ」の季節を歌っている?
- 舞台となっている場所は「どこ」?
- 「誰が」何をしている様子だろう?
このように、まずは5W1Hを使って歌詞を客観的に読み解くことが、感情を込めて表現するための大切な土台となります。
感情を込めるための指導ステップ2:歌詞の世界を「自分ごと」にする
5W1Hで歌詞のストーリーを整理できたら、次のステップは、それを生徒たち自身の体験や経験に置き換える、つまり「自分ごと」にさせることです。
教材別「自分ごと」にするための問いかけ例
生徒自身の経験と歌詞の世界を結びつけることで、「どのように歌いたいか」という主体的な表現意欲を引き出します。
- 【赤とんぼ】
- 「赤とんぼを実際に見たことはありますか?」
- 「最近、夕やけを見たのはいつですか?それを見てどう感じましたか?」
- 「この詩は作者の幼い頃の思い出です。皆さんが思い出す小さい頃の風景はどんなものがありますか?」
- 【夏の思い出】
- 「歌詞では水芭蕉が夏の象徴ですが、皆さんは何を見ると『夏が来た』と感じますか?」
- 「皆さんが思う『夏を象徴する花』は何ですか?」
- 「この夏、行ってみたい場所や、してみたいことはありますか?」
- 【花】
- 「歌詞には隅田川が出てきますが、みんなの学校から一番近い大きな川はどこですか?最近そこへ行きましたか?」
- 「歌詞は春の川の風景ですが、皆さんが知っている春の川はどんな風景ですか?」
- 「『ながめを何にたとうべき』(例えようがないほど美しい)とありますが、今まで見た中で『例えられないほど美しい』と感じた風景はありますか?」
「どのように歌いたいか」から技術へ
生徒たちが歌詞を「自分ごと」として捉え、自身の体験と重ね合わせることで、「どのように歌いたいか」という表現の方向性が生まれます。
この『どのように歌いたいか』という内面的な欲求こそが、表現に必要な知識や技術を学ぶための最も強力な動機付けとなるのです。
どのように歌いたいか(表現意欲)
⇒そのために(知識・技術の探求)
- 呼吸の方法、腹筋の使い方、母音の口の形
- 強弱、リズム、抑揚の付け方
- 歌詞の背景、作詞者や作曲者のこと
音楽の指導では、つい技術的な側面が先行しがちですが、「どう歌いたいか」という内面的な欲求を先に引き出し、その実現のために知識や技術を身につける、という流れを大切にすることが、「感情を込める」ことへの理解を深める鍵となります。
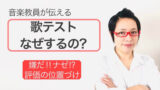
感情を込めるための指導ステップ3:「知覚」と「感受」を使い分ける
最後に、学習指導要領にも記載されている「知覚」と「感受」という言葉を用いて、感情表現の指導を考えてみましょう。
- 知覚:音楽を形作っている要素や仕組みを聴き取ること。
- 感受:その働きが生み出す良さや美しさ、雰囲気などを感じ取ること。
「知覚」は客観的な事実、「感受」は主観的な感情
「知覚」は、誰が聞いても同じ客観的な事実を指します。
例えば、「この曲は弱く演奏されている」「この曲は短調だ」といった、音楽を構成する音色、強弱、速度、旋律などの要素は、誰が聴いても変わりません。
一方で『感受』は、その音楽的な事実から何を感じ取るかという、人それぞれ違ってよい主観的な部分です。
例えば、『弱く静かな曲』という事実(知覚)に対し、ある生徒は『心が落ち着くようで明るい気持ちになる』と感じ、別の生徒は『寂しくて切ない気持ちになる』と感じるかもしれません。この感じ方の違いこそが『感受』であり、どちらの意見も尊重されるべきものです。
音楽の授業では、つい「長調は明るい」「短調は暗い」と指導しがちですが、短調の曲を聴いて明るさを感じる生徒もいます。聴き取った事実(知覚)から、何を感じるか(感受)は、生徒一人ひとり違って良いのです。
この「知覚」と「感受」という言葉を指導者がきちんと使い分け、生徒に伝えることが、「感情を込める」という指導の質を高めることに繋がります。
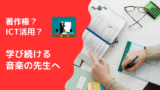
まとめ
今回は、「感情を込める」とはどういうことか、特に歌唱指導における具体的なアプローチを3つのステップでご紹介しました。
- 5W1Hでストーリーを考える
- 歌詞の世界を「自分ごと」にする
- 「知覚」と「感受」を使い分ける
もちろん、ピアノ、声楽、その他の楽器など、専門によって表現の方法や感情の込め方、必要とされる技術や知識は大きく異なります。
この記事で紹介したアプローチは歌唱が中心でしたが、その本質は器楽指導にも通じます。ぜひご自身の専門分野で、抽象的な『気持ち』を具体的な『問い』と『技術』に分解し、生徒一人ひとりの表現力を引き出す指導を考えてみてはいかがでしょうか。
この記事は動画「【音楽の授業】「感情を込めて」が伝わらない…を解決!中学生の表現力を引き出す具体的な指導法3選」をもとに作成しています。




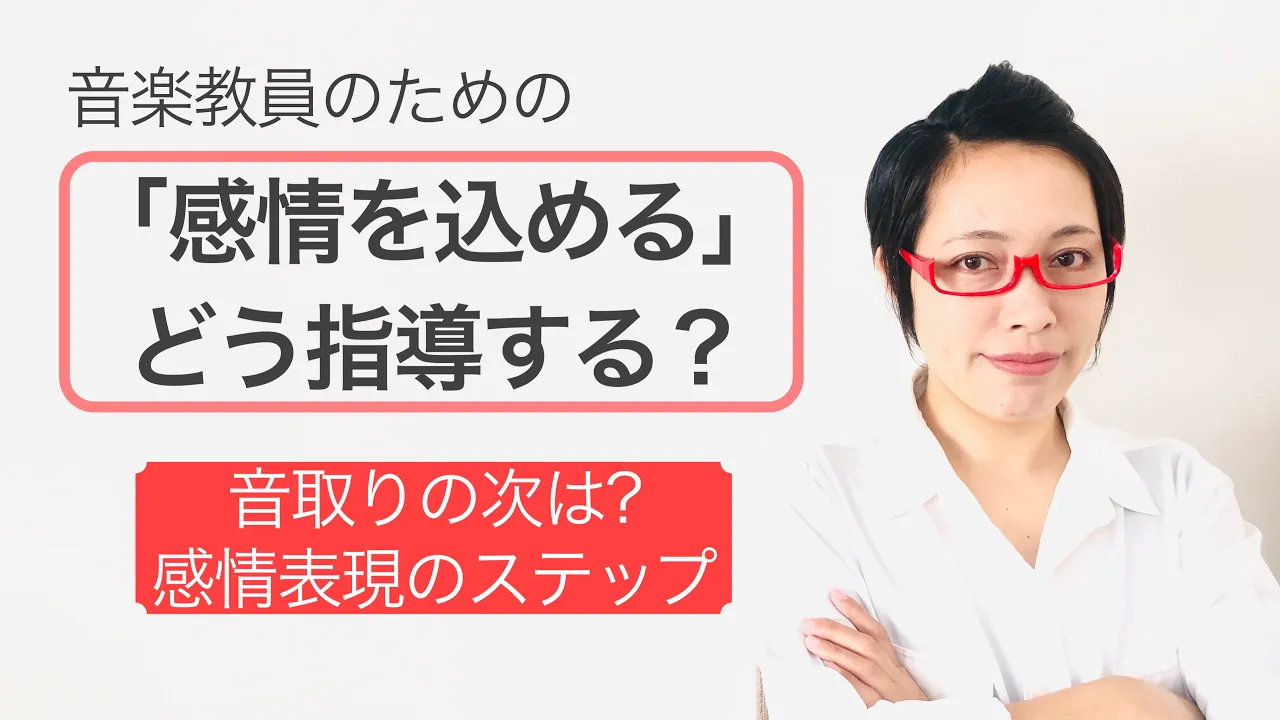
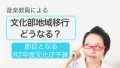

コメント