学校の規模は様々で、近年では少人数の学級を担当する先生も増えています。特に音楽科の授業では、人数の違いが指導法に大きく影響します。
「初めて少人数学級を持つことになった」 「少人数ならではの特徴的な指導法が知りたい」 「大人数の指導経験と比較して、どんな点に注意すれば良いのだろう?」
この記事は、そんな先生方や学生さんのために、少人数学級における音楽指導の重要なポイントを3つにまとめて解説します。公立校での少人数指導と、国立中学校での大人数指導の両方を経験した視点から、少人数学級ならではの課題と良さをお伝えします。
少人数学級の音楽指導では、特に意識したいポイントが3つあります。一つずつ見ていきましょう。
生徒一人ひとりの「能力を見極める」重要性
生徒一人ひとりを個別に見ることは、学級の人数に関わらず基本です。しかし、少人数の場合、この「能力の見極め」が極めて重要になります。
なぜなら、合唱でも器楽でも、少人数では生徒全員がソロの状態になるからです。各パートに一人が割り当てられる重唱・重奏では、一人ひとりが重要な役割を担います。
大人数の学級であれば、一つのパートに何人かを振り分けることができます。そうすれば、一人が間違えても他の生徒がフォローし合ったり、学び合ったりしながら音楽を進めることが可能です。
しかし、全員がソロの状態では、いやが応でも「失敗が許されない」という環境になりがちです。生徒の気持ちを考えても、適材適所で能力をきちんと見極め、役割を与えることが不可欠です。
特に、以下のパートを担当する生徒の見極めは、音楽全体の成否に関わるため重要です。
- 指揮者
- バスの音を担当する生徒
- ドラムパートなど、そのパートがないと音楽全体が止まってしまう役割
これらの重要なポストには、能力をしっかり見極めた上で生徒に役割を与えると良いでしょう。これは大人数でももちろん重要ですが、少人数では特に意識すべき点です。
「自信を持たせる」ための具体的なアプローチ
一人ひとりの役割が重く、「失敗が許されない」というプレッシャーは、生徒にとって大きな負担になり得ます。だからこそ、生徒が伸び伸びと、持てる能力を十二分に活かせる環境づくりが重要になります。そのために欠かせないのが「自信を持たせる」ことです。
褒めることの重要性
指導者が一方的に指示を出す「レッスン型」の授業では、どうしてもダメなところばかり指摘してしまいがちです。音楽科の教員自身、ピアノや歌のレッスン、部活動などでたくさんのダメ出しをされ、「もっと良くしよう」と努力してきた経験があるかもしれません。
しかし、少人数学級の授業では、肯定的に褒めてあげることが非常に重要です。
教育実習生の指導でよく言われるのが、「褒める部分と指摘する部分を同じぐらいの分量で伝えましょう」ということです。意識しないと、どうしても指摘の方が多くなってしまいます。褒める部分を特に重要視し、「ここが良かったね」「あなたのこの部分がとてもいいね」と伝えてあげましょう。
具体的に褒める
褒めるときは、具体性も大切です。
全体的な感想だけでなく、「ここのパートのこのフレーズがとっても良かったな」とか、「誰々さんの活躍がとても良かったですね」というように、人や場所を特定して、生徒が聞いて理解できるような褒め方をすると効果的です。
担任や他教科との連携
生徒に自信を持たせるためには、他者との連携も鍵となります。
- 小学校の場合: 担任の先生と連携し、「今日の合唱で、誰々さんのこういうところがすごく良かったですよ。ぜひ褒めてあげてください。場合によっては、ご家庭の方にも伝えてあげてくださいね」といった形で情報を共有します。
- 中学校の場合: 他教科の先生方との連携が重要です。少人数での合唱や合奏で生徒が感じがちなプレッシャーを、様々な場所に分散させることができます。もし生徒が不安を感じて誰かに吐き出したいと思った時に、「周りの大人たちが全員で支えてくれているんだ」と知っていることは、生徒の安心に繋がります。
このように、周りの大人と連携して生徒を支え、自信を持たせてあげることが、少人数指導では特に重要です。
視野を広げる「外部との関わり」
学級の中が少人数だと、人間関係や関わりが固定化しやすくなります。そのため、意識的に外に目を向けさせる機会を作ることが大切です。
学校内・学校外での交流
- 他学年との交流: 中学1年生が合唱をしているなら、3年生の合唱を見せたり聞かせたりする機会を作ります。
- 他校の演奏を聴きに行く: 学校単位で、他の学校の演奏会に足を運ぶのも良いでしょう。
- 地域の団体との関わり: 地域で活動している合唱団体など、大人の演奏に触れる機会も有効です。小さな地域であれば関わりも密接な場合が多く、練習風景を見学させてもらうのも良い経験になります。
オンラインの活用
現代ならではの強みとして、オンラインの活用が挙げられます。YouTubeなどには、様々なコンクールや演奏会の動画がアップされています。
「同じ歳の子たちの全国レベルの合唱はこんなにすごいんだ」ということを見せ、自分たちとの違いに気づかせることが重要です。「どういう点を注意したらいいかな?」「どんな違いがあるかな?」といった問いかけを通じて、生徒自身に考えさせます。
教員は上手い演奏を見せる際に優劣を考えがちですが、生徒にとっては「違いを知る」という観点が非常に有益です。
特におすすめなのが、NHK全国学校音楽コンクール(Nコン)の公式サイトにあるアーカイブです。予選・本選を含めて多くの曲が音声や動画で公開されており、「全国レベルの合唱はこんなに素晴らしいんだ」「自分たちとどう違うんだろう」という視点を授業に取り入れることができます。

まとめ:少人数だからこそできる音楽教育を
今回は、少人数学級における音楽科の指導について、3つの重要なポイントをお話ししました。
- 生徒一人ひとりの能力を正確に見極める
- 褒めることや連携を通じて、生徒に自信を持たせる
- 外部との関わりを意識的に作り、生徒の視野を広げる
少人数だからこそ、一人ひとりの生徒と深く関わり、その成長をきめ細かくサポートすることができます。また、地域の合唱団や吹奏楽団といった特性を活かし、どう関わっていくかを考えることも大切です。
学校の中だけで閉じずに、ぜひ積極的に外に目を向ける機会を作り、少人数ならではの豊かな音楽教育を実践してみてください。
この記事は動画「【音楽の先生向け】少人数クラスの指導、3つのコツ|生徒の能力を見極め、自信を育む方法」をもとに作成しました。




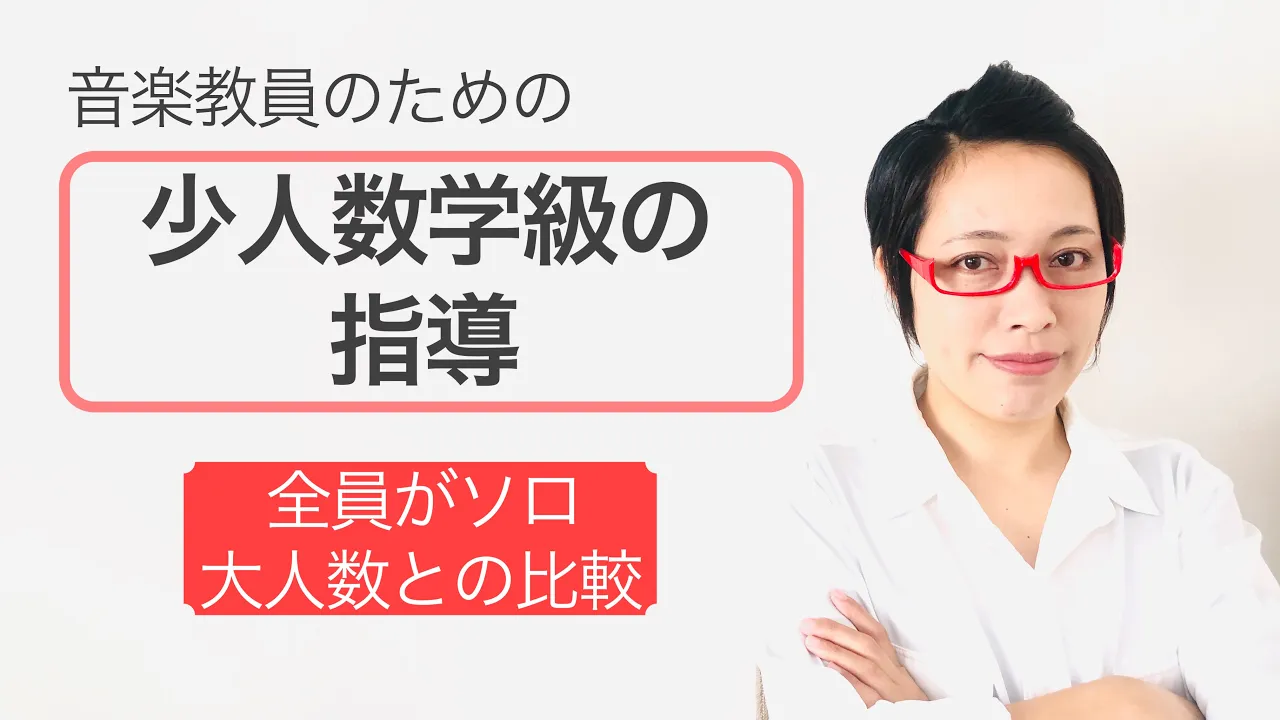
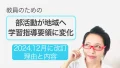
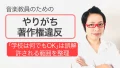
コメント