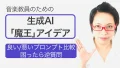皆さん、こんにちは。「一歩先ゆく音楽教育」の原口直です。学校での教育研究の経験をもとに、未来につながる新しい学びについて情報発信をしています。
さて、日々の報告書やおたよりの作成などで生成AIを使ってみて、その圧倒的な便利さに驚かれた先生も多いのではないでしょうか。
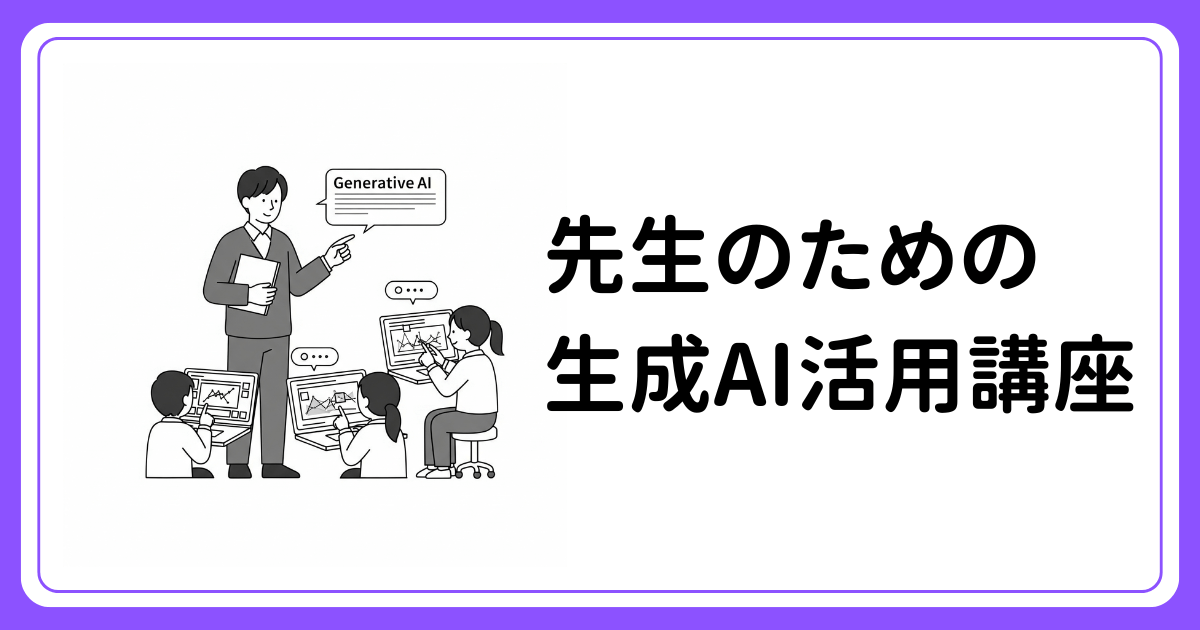
授業や校務で使える実践的な生成AI活用法を紹介。コピペして使えるプロンプトやリスク対策も含めて、生成AI初心者でも生成AIがすぐに使えるよう分かりやすく解説しています。
便利な車のアクセルの踏み方を覚えた今、次に絶対に知っておかなければならないのが、安全に運転するための「交通ルール」、つまりブレーキのかけ方です。
この記事では、「著作権・個人情報は?」というテーマで、先生方が生成AIを使う上で最も気になるであろう3つの大きな疑問にQ&A形式でお答えしていきます。
「生徒の情報をどこまで入力していいの?」
「先生が作ったものは自由に使っていいの?」
そんな不安をすっきり解消し、自信を持って生成AIを活用するための土台となる知識をお伝えします。先生方自身と大切な子どもたち、そしてその情報を守るために非常に重要な内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
◆はじめに:生成AIに関する情報の取り扱いについて
この記事をご活用いただくにあたり、以下の点にご留意ください。
- 情報の鮮度について
この記事は、元となる動画の公開時点の情報に基づいています。生成AIは日々進化しており、精度、機能、利用規約が変わる可能性があります。ご自身で最新の情報を確認するようにしてください。 - 解釈の多様性について
生成AIに関する考え方や受け取り方には個人差があります。この記事は一つの理解のための資料であり、必ずしも唯一の正解を提示するものではありません。現場での運用方法は、所属する学校や自治体の方針にも左右されます。 - ご自身の教育観との照らし合わせ
この記事は、生成AIの可能性と課題を分かりやすく伝えることを目的としています。ご自身の教育観や教科の特性、児童生徒との関わり方を踏まえながら、活用方法を考えてみてください。
- 情報の鮮度について
なお、学校現場における生成AIの利用については、文部科学省の専用サイトが6月30日にスタートし、ガイドラインの概要も公開されています。ぜひそちらもあわせてご覧ください。


【Q1】生徒の個人情報や成績はどこまで入力していい?
結論:個人が特定できる情報は「絶対」に入力しない
まず結論からお伝えします。生徒や保護者の氏名、住所、成績、具体的なエピソードなど、個人が特定できる情報は絶対に入力してはいけません。
なぜなら、入力した情報はAIの学習データとして使われ、意図せず外部に漏洩してしまうリスクがゼロではないからです。ひとたび情報が漏洩すれば、生徒や学校に予期せぬ被害が及ぶ可能性も考えられます。これは文部科学省のガイドラインでも最も注意喚起されている点です。
※生成AIの種類によっては、学習させない設定が元々なされているものや、自分で設定できるものもあります。
【NGな入力例】
「鈴木花子さんは合唱コンクールの練習でソプラノのパートをよく頑張っている。彼女への励ましの言葉を考えて」
このような入力は完全にNGです。
安全に使うためのポイント:質問を「一般化」する
では、どうすれば安全に活用できるのでしょうか。重要なポイントは、個人を特定できないように質問を「一般化」することです。
先ほどの例であれば、以下のように言い換えます。
【OKな入力例】
「合唱コンクールの練習で高い声が出ずに悩んでいる生徒がいます。自信を持たせるような前向きな声かけの言葉をいくつか提案してください」
これなら、「鈴木花子さん」という個人情報を含まずに、先生が欲しいアドバイスを得ることができます。
国語の先生の例で見てみましょう。
- NG: 「●●さんが漢字の書き取りが苦手です」
- OK: 「漢字の反復練習が苦手な児童が、楽しく取り組めるようなアイデアを5つ教えてください」
このように、具体的な「個人の悩み」から「指導上の一般的な課題」へと視点を変えることが、安全な活用のための鉄則です。
【Q2】生成AIが作った文章や音楽の著作権は誰のもの?
原則:生成AI「だけ」が作ったものに著作権は発生しない
生成AIが作った文章、音楽、イラストなどの著作権は一体誰のものになるのでしょうか。これも非常に重要なポイントです。
原則として、生成AIが作っただけの生成物に著作権は発生しないとされています。つまり、教員が生成AIに作らせた文章、イラスト、音楽の旋律などは、著作権フリーの素材のようなものと考えることができます。
【授業で活用するOK例】
- 音楽の授業で「『夏の思い出』の歌詞のような雰囲気でオリジナルの歌詞を作って」と生成AIに作らせ、授業内で鑑賞したり、教材として印刷したりする。
- 生成AIに作らせた鑑賞カードのフォーマットを、授業で印刷して使う。
- 生成AIに作らせた「春」がテーマの短い旋律を、音楽の授業の中で聴く。
注意点①:元の著作物との類似リスク
ただし、注意点が2つあります。
1つ目は、生成AIが学習データにした元の著作物に酷似してしまうリスクです。生成AIが、どこかの誰かの作品そっくりのものを偶然作ってしまう可能性はゼロではありません。特に「有名なアーティスト風の曲」を作らせるような場合には注意が必要です。
注意点②:教員による大幅な創作的修正
2つ目は、先生が生成物に大幅な手を加えた場合です。
生成AIが作った「たたき台」に、教員が大きく創作的な修正を加えた場合、その創作部分には教員の著作権が認められる可能性があります。
【著作権侵害リスクのあるNG例】
- 生成AIに有名J-POPアーティスト風の曲を作らせて、学校の公式PR動画のBGMに使う。
- 生成AIに描かせたイラストを、学校の公式キャラクターとしてグッズ販売する。
これらの例は学校の範囲を超えてしまっているため、著作権の許諾が必要になる可能性があります。
結論として、学校の授業の範囲で教材として使う分には多くの場合問題ありません。しかし、それを学校のウェブサイトなどで広く公開したり、コンクールに応募したりする際には、著作権侵害のリスクがないか慎重に確認する必要があります。
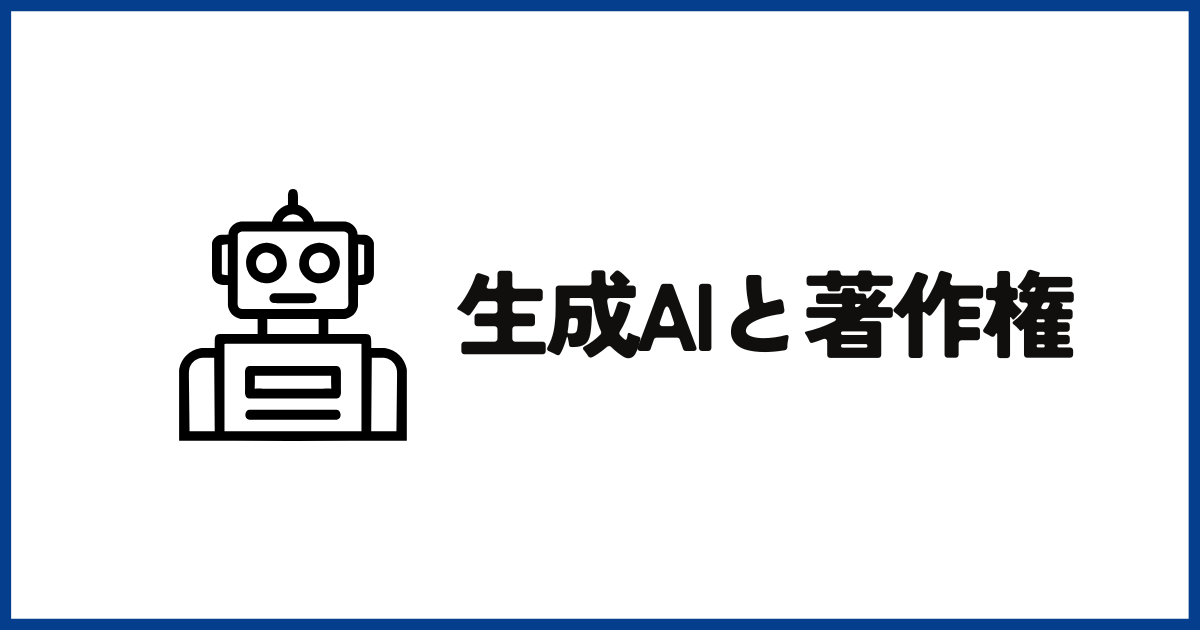
【Q3】生成AIの答えはすべて正しい?
答えはノー:「ハルシネーション」という“もっともらしい嘘”に注意
生成AIの答えは、すべて正しいのでしょうか?
答えは「ノー」です。生成AIは、事実でないことを事実であるかのように、もっともらしい嘘を自信満々に答えることがあります。これは専門用語で「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれています。
【ハルシネーションの例】
- 社会科の授業で「平賀源内が発明したものを教えて」と聞くと、エレキテルなどに加えて、存在しない発明品を創作して答えるかもしれない。
- 音楽科の授業で「ベートーヴェンの交響曲第10番について詳しく教えて」と聞くと、存在しないはずの曲について、もっともらしく解説を始めてしまうことすらありうる。(ご存知の通り、ベートーヴェンの交響曲は第9番までです)
賢い付き合い方:ファクトチェックの徹底
ですから、生成AIの答えは絶対に鵜呑みにしてはいけません。
特に、歴史的な事実や科学的な根拠など、正確性が求められる内容については、必ず教科書や信頼できる資料で裏付けを取る(ファクトチェックする)癖をつけましょう。
生成AIは、あくまで思考の壁打ち相手や、アイデアの叩き台として使うのが賢い付き合い方です。
まとめ:安全利用の3つの鉄則を覚えて活用しよう
今回は、生成AIの安全な利活用についてお話ししました。最後に、安全活用のための3つの鉄則を振り返りましょう。
- 個人情報は絶対に入力しない
- 質問は必ず「一般化」する。
- 生成AIの著作物はグレーゾーンと認識する
- 学校内での活用(著作権法第35条の範囲)は問題ない場合が多いが、外部公開には要注意。
- 生成AIは嘘をつく(ハルシネーション)
- 必ずファクトチェック(事実確認)をする癖をつける。
ルールを知ると、少し窮屈に感じたかもしれません。しかし、交通ルールを知っているからこそ、私たちは安全にドライブを楽しむことができます。生成AIもそれと同じです。
今日学んだ知識は、先生方ご自身と子どもたちを守り、この便利な道具をこれからも安心して使い続けるためのものです。この知識を味方につけて、自信を持って日々の校務や授業に生成AIを取り入れ、教育の可能性をさらに広げていきましょう。
この記事は、動画「【10分で解説】先生のための生成AI安全マニュアル|授業で使う前に知るべき個人情報・著作権の3つのルール」をもとに作成しました。