「自分のあの一言は、もしかしたら生徒を傷つけてしまったかもしれない…」 日々の授業の中で、生徒にかける言葉について、このように悩んだ経験はありませんか?
こんにちは。音楽教員歴10年の原口直です。私自身、ジェンダーに関する研究をきっかけに、過去の生徒への発言を省み、これは良くなかったと反省することが多々ありました。
そこでこの記事では、私自身の経験と調査から見えてきた『授業におけるNGワード』を共有します。明日からの授業で、生徒一人ひとりが安心して自分を表現できる教室をつくるため、ご自身の言葉かけを振り返るきっかけとしてお役立てください。
授業は、台本通りに一字一句決まった言葉を話すわけではありません。だからこそ、教員が普段から持っている知識や考え方が、ふとした言葉に表れます。ここでは、特に注意が必要なNGワードを3つのカテゴリに分けて見ていきましょう。
人権に関わる言葉
まず最も注意すべきなのは、人権に関わる言葉です。法務省と文科省が共同で出している「人権教育・啓発白書」では、人権問題について以下のように分類されています。
- 女性
- 子供
- 高齢者
- 障害のある人
- 同和問題
- アイヌの人々
- 外国人
- HIV感染者・ハンセン病患者など
- 刑を終えて出所した人
- 犯罪被害者など
- インターネットによる人権侵害
- 北朝鮮当局による拉致被害者等
- その他の人権問題
生徒も教員も、それぞれが多様なバックグラウンドを持っています。これらの事柄について、授業の中で不用意に発言したり、差別的な言動をしたりすることは絶対にあってはなりません。何かを発言する前には、自分の言葉に問題がないか、一度冷静に自分自身を分析する習慣が不可欠です。
音楽の能力に関する言葉
次に、音楽の授業特有のNGワードについてです。例えば、以下のような言葉には注意が必要です。
- 音程がとれない(いわゆる「音痴」)
- 声が小さい
- リズム感がない
これらの言葉をかける前に、「もしかしたらこの生徒は変声期の途中で、自分で声をコントロールしにくいのかもしれない」「今はまだ成長の途中なのかもしれない」といった配慮が必要です。
もちろん、これは指導そのものをためらうべきだという意味ではありません。生徒のやる気や以前からの変化など、状況に応じて的確な指摘が求められる場面もあります。重要なのは、発言する前に『その生徒の心理状態はどうか』『クラス全体の雰囲気はどうか』といった点を的確に把握し、言葉を選ぶことです。
特に小・中・高校は、誰もが心身ともに成長の真っ只中にいます。だからこそ生徒の音楽的な能力に関する言葉かけは、その子の成長段階や私たち教員との信頼関係を十分に考慮しなくてはなりません。『自分がその子の成長をサポートするんだ』という気持ちを常に持ちたいものです。
宗教や政治に関わる言葉
3つ目は、宗教や政治に関する話題です。特に音楽史を扱う授業では、音楽と宗教は切っても切り離せない関係にあります。
しかし、これも人権の問題と同様に、生徒や教員はそれぞれ異なるバックグラウンドを持っています。宗教や政治に関する話題に触れる際には、自分の発言が特定の価値観に偏っていないか、平等性を保てているかを、授業の前に教材や指導案の段階で十分に確認しておく必要があります。
まとめ:全ての生徒と教員が気持ちのよい授業を作るために
今回は、授業におけるNGワードを「人権」「音楽」「宗教・政治」の3つの観点から確認しました。
授業で私たちが使う言葉は、自身の知識や考えを直接映し出す鏡です。だからこそ、自らの言葉に常に意識的であり、学び続けることは、教員としての責務であり、また専門職としての誇りでもあるでしょう。
全ての生徒が、そして教員自身も気持ちよく参加できる授業。その実現は、私たち自身が日々の『言葉かけ』を見直すことから始まります。
「【配慮事項】学校での子どもの多様性(外国籍・聴覚過敏・LGBTなど)」
「【配慮事項】生活指導の必要な生徒への対応」
の動画で解説しているので是非ご覧ください。
この記事は動画「【音楽の先生必見】「音痴」の一言が生徒を傷つける。授業で絶対使ってはいけないNGワード3つの原則」をもとに作成しました。






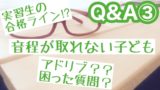





コメント