教育実習を目前に控え、期待と同時に『うまくやれるだろうか』という不安で胸がいっぱいの学生さんも多いのではないでしょうか。初めての経験はもちろん、2回目以降でも校種や環境が変われば、新たな緊張感が生まれるのは当然のことです。
この記事では、多くの教育実習生がつまずきやすいポイントを事前に知ることで、不安を解消し、実習をさらに有意義なものにするためのヒントをご紹介します。教科指導教員として50人以上の実習生を見てきた経験から、共通してみられる「つまずき」とその対策をまとめました。
この記事は、次のようなことを知りたい方に是非ご覧頂きたい内容です。
▶「教育実習に不安がある」「緊張する」と感じる方
▶2回目以降の教育実習であっても、校種・時期・地域が違うことで「始めの一歩に戻りたくない」「きちんと復習をしておきたい」という方
この動画の他にはYouTubeチャンネル内に再生リスト「【元指導教員が解説】教育実習に役立つ動画」というのを用意しています。主に教育実習生に役立つ動画をまとめて1つの再生リストにしてありますので、ぜひそちらをご活用ください。
また、おすすめの動画10本として「【初の教育実習に臨む実習生向け】校種・科目不問のおすすめの10本」という再生リストにしてありますので、ぜひご活用ください。
教育実習では、立場を変えて学校へ行くため、誰でも最初は緊張しますし、失敗も当然です。
しかし、誰もが共通してつまずきやすいポイントをあらかじめ知っておくことで、不要な不安を減らし、さらに上を目指すことができます。
ここでは、特に多くの実習生が直面する3つの課題について解説します。
声の大きさ:意識すべきは「普段の1.5倍」
最初のつまずきポイントは「声の大きさ」です。
先生という職業の人は、音楽科に限らず声が大きい方が多い傾向にあります。実際に生徒へ「学校で一番声の大きい先生は?」と尋ねた際、音楽科の教員かと思いきや、国語科や理科の先生の名前が挙がったこともありました。
初めての教育実習では、教室にいる40人の生徒、つまり80個の目が一斉に自分に注目する状況に、大きな緊張感を覚えるものです。これは経験を積めば慣れていきますが、初めは誰でも緊張します。
特に音楽科が使用する音楽室は、普通教室よりも広く、天井が高いことが多いため、普通教室よりもさらに大きな声を出す必要があります。そうした環境で、緊張や授業への自信のなさから萎縮してしまうと、声はどんどん小さくなりがちです。
対策:自分が思っている1.5倍から2倍の声で話す
授業に臨む際は、自分が思っている1.5倍、あるいは2倍くらいの大きな声で話して、ようやく丁度いいくらいだと考えましょう。教育実習生にとって「元気さ」や「若さ」は一番の武器です。緊張を取り払うためにも、意識的にもっともっと大きな声で授業をしてみてください。きっと緊張も吹き飛ぶはずです。
板書・パワーポイント:生徒の言葉に「翻訳」する視点
2つ目のつまずきポイントは「板書」や「パワーポイント」の作成です。
初めての授業で、板書やパワーポイントの内容が少しずれてしまうのは、ある意味当然のことです。なぜなら、授業を受ける生徒たちがどんな子たちで、どんな知識を持っているのかを完全に把握しないまま作成するからです。
一口に「中学生」「高校生」と言っても、学年や地域、そして生徒一人ひとりの背景は様々で、クラスによっても雰囲気は異なります。「中学1年生用」として作っても、全ての中学1年生に通用するとは限りません。
対策:生徒を観察し、指導教員に確認してもらう
まず気を付けたいのは、生徒たちと「共通の用語」や「共通の言語」でコミュニケーションをとることです。彼らがどのような言葉を、そして音楽用語をどの程度知っているかを把握した上で作成する必要があります。
初めから完璧に作るのは難しいので、まずは「たたき台」を作成しましょう。ノープランは避けるべきです。そして、授業を通して生徒たちをよく観察し、彼らが使う言葉に合わせて、作ったものを「翻訳し直す」という意識が大切です。
さらに、指導教員など普段から生徒に接している先生に、作成した板書やスライドを添削してもらいましょう。
- 言葉は生徒に通じるか?
- 1ページあたりの文章量は適切か?
- 話す内容と合っているか?
といった点を確認していただくことが不可欠です。大学の模擬授業は、相手が大学生であるため、文字がびっしり詰まっていたり、難しい言葉を選んだりしがちです。対象となる生徒の学年や知識レベルを踏まえ、一度作ったものを調整していきましょう。
音楽の授業における板書の仕方(→動画はこちらから)
音楽授業におけるパワーポイントの使い方(→動画はこちらから)
音楽授業で板書とパワーポイントを使い分ける方法(→動画はこちらから)
音楽用語の「思い込み」:全ての基準は「教科書」にあり
3つ目のつまずきポイントは「音楽用語」の扱いです。これは音楽科に限らず、他の教科にも通じる問題でしょう。
ここで質問です。以下の3つの記号は、何と読みますか?
- cresc.
- ff
- poco
正解は、
- クレシェンド
- フォルティッシモ
- ポーコ
です。
ピアノ教室などで習った読み方と異なり、『自分の知識が間違っていたのか』と戸惑う方もいるかもしれません。これは毎年多くの実習生が経験する、ごく自然なつまずきです。実際に、生徒の中にも『クレッシェンドと習った』と言う子がいるかもしれません。
しかし、学校教育における授業の基準は、「自分がどう習ったか」や「本来のイタリア語の読み方」ではなく、「教科書にどう書いてあるか」です。
対策:教える前に、まず教科書を確認する
中学校や高校で使われている音楽の教科書には、必ず音楽用語が載っているページがあり、そこには「読み方」が明記されています。学習指導要領にも音楽用語は載っていますが、読み方までは書かれていません。授業で使ったり、板書に書いたりする用語は、必ずこの教科書の表記に準拠させましょう。
なぜなら、中学校には「テスト」があるからです。テストで「クレッシェンド」と書いた場合、教科書の表記が「クレシェンド」であれば、それは不正解となります。実際に、教科書に合わせて「クレッシェンド」はバツにしていた経験があります。教科である以上、マルとバツの基準は必要です。
これは音楽用語に限りません。
- 曲名: ベートーヴェンの交響曲は「運命」ではなく「交響曲第5番ハ短調」が正式名称です。「ブルタバ」か「モルダウ」か、なども同様です。
- 人名: 作詞者、作曲者の名前
- 楽器名: 楽器の正式名称
など、自分が先入観で知っていることや、知りすぎて省略して覚えていることがあります。思い込みが一番怖いのです。生徒に教える前に、まずはご自身が教科書を隅々まで見直し、何と書いてあるかを必ずチェックして、学び直すことからスタートしましょう。
まとめ:共通のつまずきを知り、より深い学びへ
毎年多くの教育実習生を受け入れていると、同じような点でつまずくことが多いことに気づきます。もちろん、個々の実習生や授業によって改善点は異なりますが、今回ご紹介した3つのような共通の課題は、事前に知っておくだけで対策が可能です。
- 声の大きさ
- 板書やパワーポイント
- 音楽用語
これらの事前準備は、単に失敗を避けるためだけのものではありません。それは、失敗を恐れずにのびのびと挑戦し、未来の教育者として大きく成長するための土台となります。万全の準備をして、自信を持って実習に臨んでください。
この記事は動画「【音楽科実習生へ】声の小ささ、パワポ、用語…その不安、全部解決できます。指導教員が教える最強の授業準備術」をもとに作成しました。




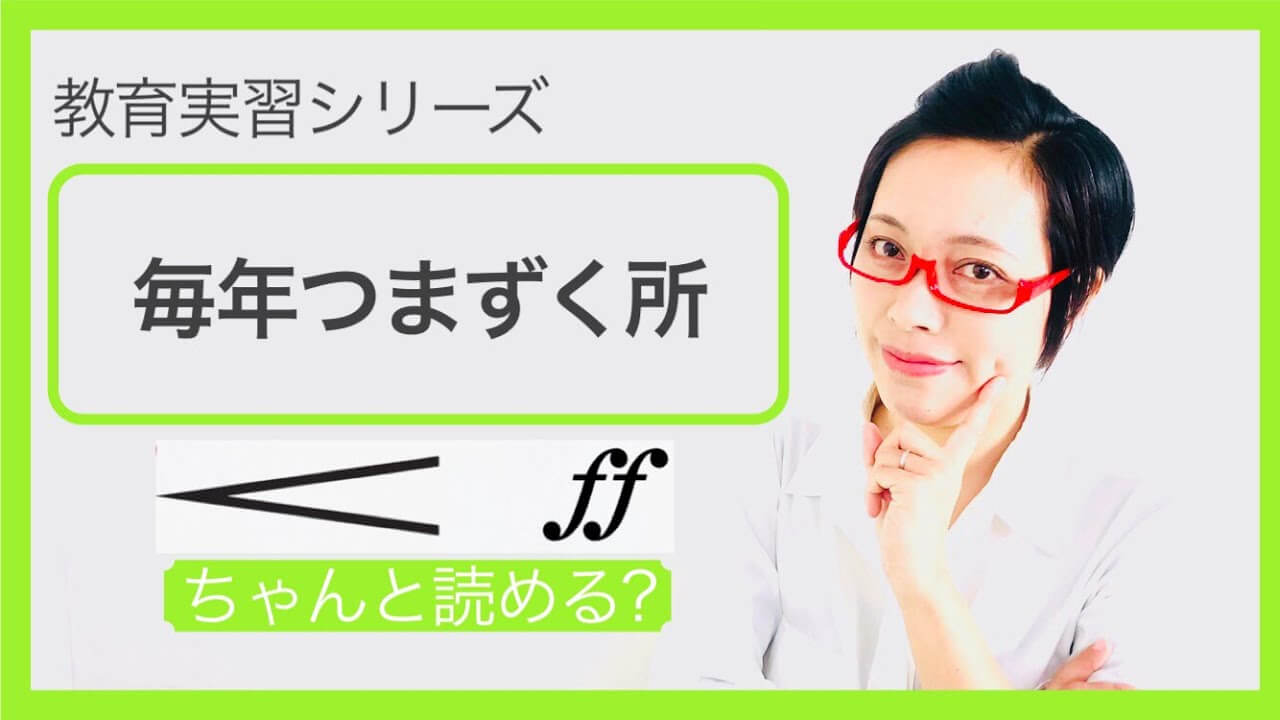


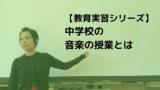






コメント