多様な背景を持つ子どもたちが集まる学校現場。音楽の授業においても、一人ひとりの生徒に寄り添った指導を行うために、どのような配慮ができるだろうか、と日々考えている先生も多いのではないでしょうか。
この記事では、学校における多様性について、特に音楽科で配慮すべき3つの視点を解説します。
私は以前、大学と共に性的マイノリティやジェンダーに関する研究を進める中で、多角的な視点の重要性や自身の勉強不足を痛感した経験があります。今回はその経験も踏まえ、学校に存在する多様性の一部として「外国籍」「その子の特性」「性的マイノリティ」の3つのテーマについて考えていきます。

外国籍の生徒・家族への配慮
まず、外国籍の生徒やその家族への配慮についてです。生徒本人が外国人である場合と、家族が外国人である場合があります。
言葉の壁への対応とサポート
過去には、生徒本人が日本語を話せないケースや、本人は話せるが家族が話せないというケースがありました。
本人が日本語を話せない場合は、まず日本語の指導から始める必要があり、授業やテストでのフォローが非常に重要になります。また、家族が日本語を話せない場合は、配布するプリントや行事の連絡などで、生徒本人に通訳を頼んでコミュニケーションをとることもありました。
現在では様々なサポートが利用できる可能性があるため、お住まいの地域の行政の取り組みを調べてみることをお勧めします。
言語の壁を越えて:宗教・文化的背景への深い理解と配慮
配慮が必要なのは言葉に限りません。宗教や文化的な習慣についても理解と配慮が求められます。
- 宗教: その宗教が持つ考え方、特にタブーとされている事柄については、正しい知識を持ち、配慮することが不可欠です。
- 習慣(ピアスなど): 国によっては、生まれてすぐにピアスの穴を開ける習慣があります。しかし、日本の多くの学校ではピアスが禁止されています。このような場合は、家庭と連携を取りながら理解を求めると同時に、周りの生徒たちにもその文化的な背景を説明し、理解を促すといった対応が必要になります。
これら以外にも、外国籍の生徒や家族への配慮には様々なケースが存在します。多くの実例や解決策、行政の対応に関する情報が公開されていますので、ぜひご自身で調べてみてください。
生徒一人ひとりの「特性」への配慮
次に、生徒が持つ様々な特性への配慮です。(※特別な支援が必要な子どもへの全体的な配慮については、「【音楽の授業】特別支援が必要な生徒への配慮|具体的な対応法3選」の動画で詳しく解説しています。)ここでは「色覚特性」と「聴覚過敏」の2点に焦点を当てます。

色覚特性を持つ生徒が見やすい環境づくり
症状は人によって異なりますが、特に「赤と緑の区別がつきにくい」という生徒がいました。
- 教材の配慮: 現在の教科書はユニバーサルデザインが採用されており、色覚特性を持つ生徒にも見やすいように作られています。
- 教員が作成する資料: しかし、教員が作成する板書やPowerPointのスライドなどについては、配慮が必要です。チョークの色を選ぶ際に気をつけたり、その生徒にとって色がどのように見えているかを考えたりすることが大切です。クラスに色覚特性を持つ生徒がいるかを事前に把握し、誰もが見やすい教材を作成することが求められます。
「音楽授業のワークシートの作り方」(動画はこちらから)
「音楽授業の板書の書き方」(動画はこちらから)
「音楽授業で板書とパワーポイントの使い分ける」(動画はこちらから)
聴覚過敏の生徒が安心して授業を受けるために
聴覚過敏とは、周囲の物音が我慢できないほど大きく聞こえたり、些細な音がひどく気になったりする特性です。(※この特性についても、「【音楽の授業】特別支援が必要な生徒への配慮|具体的な対応法3選」の動画で詳しく解説されています。)
中学生くらいになると、生徒自身が特性を自覚し、対処法を心得ている場合もあります。まずはクラスにそうした生徒がいるかどうかをきちんと確認し、音楽の授業においてどのような配慮や対処ができるかを一緒に考えていくことが重要です。
性的マイノリティの生徒への配慮
3つ目は、性的マイノリティの生徒への配慮です。これは、私が大学と連携して研究したテーマでもあります。
報道などでは「LGBT」という言葉がよく使われますが、これはレズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシャル(B)、トランスジェンダー(T)の頭文字を取ったものです。他にも「LGBTQ」や「SOGI」など、様々な表現が存在します。
音楽科の授業においても、すべての生徒が自分らしくいられる、安全で安心な環境を作るための配慮が不可欠です。
音楽科の授業で気をつけたい言葉遣い
何気ない言葉が、性的マイノリティの生徒にとっては辛い言葉になることがあります。
- パート分け: 「男性パート・女性パート」という声の分け方。
- 声の表現: 「男の子だから」「女の子だから」といった前提や、「男らしい声」「女らしい声」といった表現。
- 変声期: 体の性が男性で心の性が女性の生徒もいるなど、変声期に対して非常に神経質になっている場合があります。こうした生徒の存在を知っておく必要があります。
- 楽器の準備: ティンパニなどの重い楽器を運ぶ際に、「大きい男子来て」といった発言。
- 伝統文化の解説: 歌舞伎、文楽、祇園祭など、性別によって役割が定められている芸能やお祭りについて解説する際の言葉選び。
「らしさ」という無意識の線引き
習い事に関しても配慮が求められます。ピアノ、フルート、ヴァイオリンといった楽器を習うことに対して、性別による「らしさ」を無意識に結びつけて考えてはいないでしょうか。
教員自身が性別による「らしさ」で線を引かないようにすることはもちろん、周りの生徒たちが無意識のうちにそうした線引きをして誰かを傷つけていないか、気を配ることも大切です。
まとめ:多様性を学び、教育に活かす
今回は、学校現場で配慮が必要な生徒の「多様性」について、3つの視点からお話ししました。
『多様性(ダイバーシティ)』への理解は、現代の教育現場に不可欠な視点です。外国籍の生徒、様々な特性を持つ生徒、そして性的マイノリティの生徒。すべての生徒が安心して音楽を楽しめる環境を作るために、この記事をきっかけに、一つひとつのテーマについて学びを深めてみてはいかがでしょうか。
この記事は動画「【音楽教員向け】授業で必須の多様性への配慮とは?生徒を傷つけないための3つの視点」をもとに作成しました。




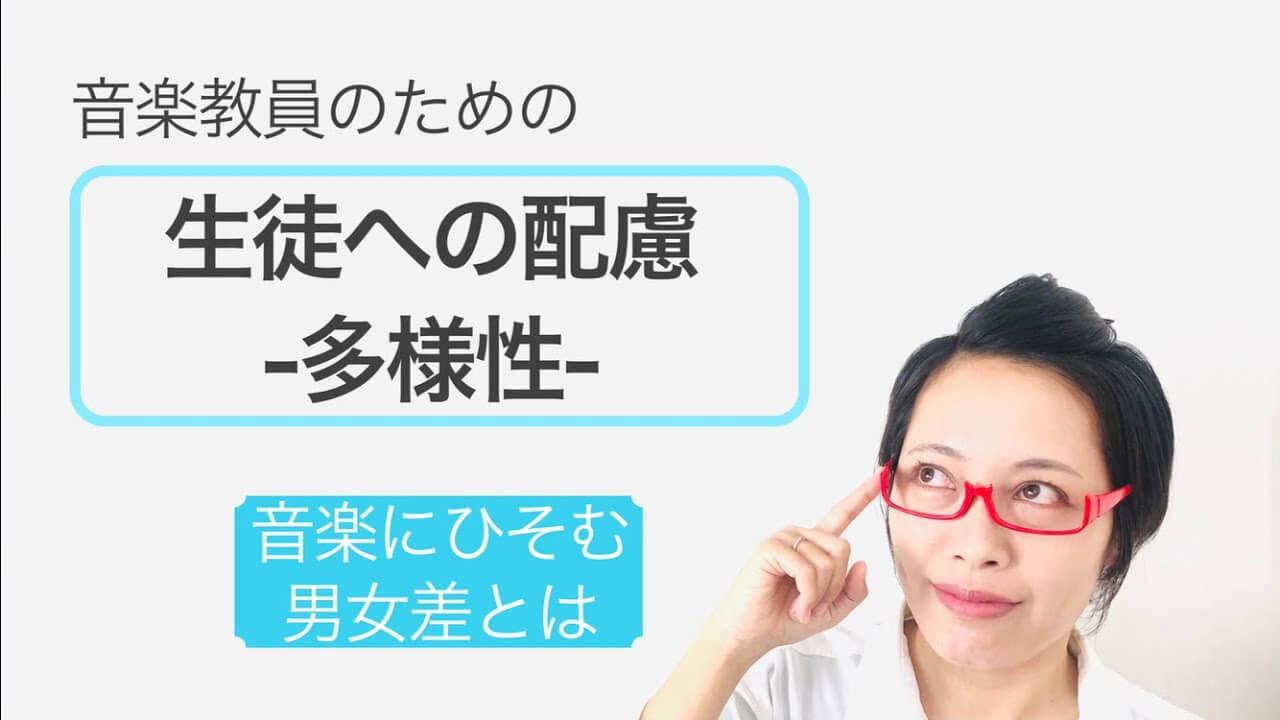

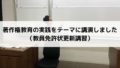
コメント