この記事では、中学校で音楽教員としての経験をもとに、生徒からの「困った質問」への対応についてお話ししています。
音楽の授業では、生徒からの純粋な質問だけでなく、時には先生を困らせようとする意図的な質問もあります。
しかし、こうした質問にどう答えるかは、教員自身のアイデンティティの確立にもつながります。今回は、代表的な「困った質問」を3つ取り上げ、それぞれにどう対応するかを具体的に紹介します。
また、この困った質問に対応すべく、「音楽の教材研究はこう進めよう!授業に活かす考え方とコツ」や「【音楽の新学習指導要領】音楽教員のための3つの改訂ポイント解説」の動画もあります。是非参考にしてください。
知らないことを聞かれた時は「素直さ」がカギ
1つ目の困った質問は、「知らないこと」や「調べていなかったこと」に関するものです。
- 例:「この作曲家はこういう人なんですか?」
- 例:「この楽器はこういうものなんですか?」
こうした質問に対しては、正直に「今は分からない」と伝えることが大切です。その上で、「良い質問だね」「私も知らなかった、気づかなかった」とポジティブに評価してあげましょう。そして、次の授業までに調べて答える、もしくは「調べても分からなかった」と素直に伝えることが重要です。
ポイントは、嘘をついたりごまかしたりせず、「私も一緒に学んでいるんだ」という姿勢を持つこと。こうした対応は、生徒との信頼関係にもつながります。
「できない」と言われたときは共感と励ましを
2つ目の困った質問は、「〇〇ができない」という訴えです。
- 例:音程が取れない(歌唱)
- 例:楽器が弾けない(器楽)
こうした悩みに対しては、指導方法を伝えるだけでなく、「音楽はすぐにできるものではない」というメッセージを添えることが効果的です。
例えば、「国語の漢字や英語の単語のように、音楽も何度も繰り返して練習することで上達するんだよ」と伝えると良いでしょう。
私自身も、ピアノを毎日何時間も練習し、ようやく今のレベルに到達したという実体験を交えて話すことで、生徒に「才能ではなく努力が大事」というメッセージを届けることができます。
生徒は「自分は不器用だから」「才能がないから」と結果を急ぎがちですが、音楽は継続が鍵だということを伝えることで、安心感を与えることができます。
「なぜ音楽を勉強するの?」にどう答えるか
3つ目の質問は、「音楽をなぜ勉強しなければならないのか?」というものです。
この質問には、生徒が本心で疑問を持っている場合もあれば、先生を試すような意図も含まれているかもしれません。確かに音楽は受験科目ではありませんが、東京都では評定が2倍で換算されるため、重要な教科でもあります。
この問いに対しては、教員自身が「音楽を勉強する意味」を哲学として持ち、それを生徒に語ることが大切です。
私の場合、「生活や社会と関わる音楽」という学習指導要領の理念をベースに、著作権、税金、CSR(企業の社会的貢献)、政治と音楽といったテーマを扱いながら、「音楽を通して社会について考える」という授業を行ってきました。
こうした話をすることで、「音楽でなければ学べなかったこと」「音楽の向こう側にある世界」を生徒が実感することができるのです。
■音楽を通じて著作権を考える授業例→音楽科で教える知的財産権の指導方法の実践例
■音楽を通じて税金を考える授業例→「文楽」をテーマに取り上げた授業を実施しました
■音楽を通じてCSRを考える授業例→音楽のオンライン授業実践編《教材:交響曲第5番ハ短調(運命)》
まとめ:困った質問は、成長のヒント
今回は、以下の3つの困った質問について取り上げました:
- 知らないことを聞かれた時の対応
- 「できない」という悩みへの向き合い方
- 「なぜ音楽を勉強するのか?」という根本的な問いへの答え方
これらの質問は、単なる「困りごと」ではなく、教員自身の授業改善や教材研究の大きなヒントとなります。
生徒からの質問を前向きに捉え、自分が成長するための糧として活用していきましょう。
こど記事は動画「『なんで音楽を勉強するの?』生徒の困った質問にどう答える?授業で使える3つのヒント」をもとに作成しました。




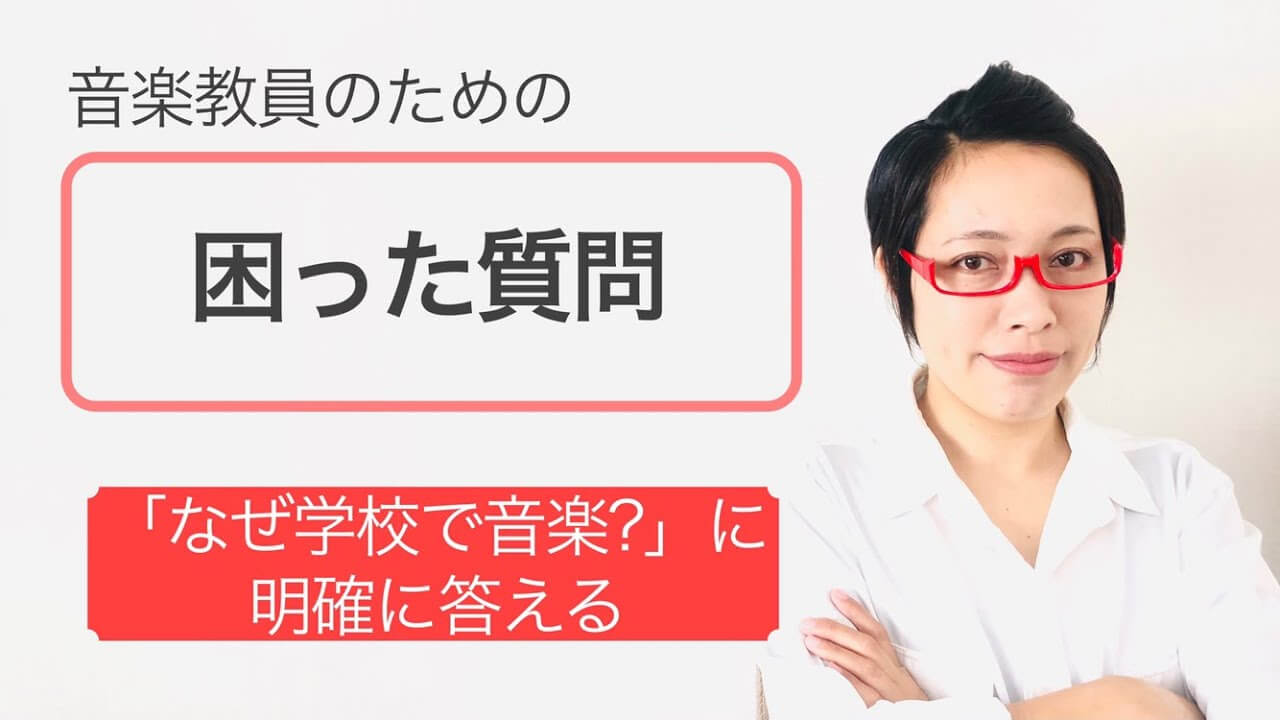


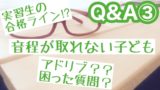





コメント