学校の先生を目指す皆さん、そして教壇に立ち始めたばかりの先生方。日々の業務の中で、「自分一人の力ではどうにもならない」と感じることはありませんか?
実は、学校には学級担任や教科担任以外にも、子どもたちの学びと成長を支える多くの専門家たちがいます。しかし、教育実習の短い期間では、その存在の重要性に気づくのは難しいかもしれません。
この記事では、担任や教科担当の先生方が教育活動に専念できるよう、陰で学校を支える「縁の下の力持ち」ともいえる専門家たちをご紹介します。彼らの存在と役割を知ることで、「自分は一人ではない」という心強さを得て、日々の教育活動にさらに自信を持って臨めるようになるはずです。
学校用務員さん:オールマイティーな学校のプロフェッショナル
学級担任や教科担任が教育活動に専念できるのは、学校用務員さんの存在があってこそです。近年では「学校技術員」「校務員」「学校主事」「技能員」「管理作業員」「スクールヘルパー」など、様々な名称で呼ばれていますが、その仕事内容はまさにオールマイティーです。
多岐にわたる仕事内容:清掃から設備の修理まで
普段、私たちが目にするのは、校内の清掃や、中庭・花壇の手入れといった園芸関係の仕事かもしれません。植物の剪定をしたり、時には果物や野菜を育ててくださったりすることもあります。
しかし、それだけではありません。天井や壁にできてしまった穴や傷の修繕、立て付けが悪くなったドアの修理など、学校設備の点検・修理も重要な仕事の一つです。
私自身は、音楽室のドアの立て付けが悪くなった際、すぐに他の教室のドアと交換してもらい、非常に助かったという経験があります。
学校行事での活躍と教員へのサポート
学校行事の場面でも、用務員さんは大活躍します。行事で必要となるポットやスリッパ、茶器といった備品の準備や片付けを一手に引き受けてくださることで、教員は生徒指導に集中できます。
「さっきあちらで見かけたのに、もうここにいる」と感じるほど、校内を縦横無尽に動き回り、私たちが気づかないような多くの業務をこなしてくださっています。
中には、扉の修理を手伝うなどを通して、用務員さんと仲良くなる生徒もいるようです。特に、楽器の運搬や電気関係の細々とした修理などで関わることが多い音楽科の教員にとっては、非常に心強い存在と言えるでしょう。
学校事務員さん:学校運営の要を担う窓口
事務室で働く学校事務員さんも、学校にはなくてはならない重要な存在です。子どもたちにとっては直接的な関わりが少ないかもしれませんが、学校運営の根幹を支えています。
生徒と教員、それぞれの視点から見る仕事
事務員さんの仕事で最も分かりやすいのは、電話応対や来客対応でしょう。宅配業者から保護者まで、学校の全ての窓口としての役割を担っています。
【生徒との主な関わり】
- 証明書の発行
- 教材費、給食費、学年費といったお金の管理
- 転出入の管理や教科書の発注に関わる学籍の管理
- 就学援助など、学校生活の支援手続き
【教員との主な関わり】
- 学級や教科で必要となる備品の購入
- 学校全体の修繕計画や予算組み(突発的な事態への対応も含む)
- 給与明細の配布や出張経費の申込み
- 休暇届や動静表の管理といった出退勤の管理
音楽科は大きな楽器の購入など、お金が動く機会が多いため、事務員さんと密にやり取りをすることが頻繁にあります。時には事務室が憩いの場になることもありますが、お金の面ではまさにプロフェッショナルです。
教員からは見えない複雑な予算の制約がある中で、ただ「できません」と突き放すのではなく、「この予算では難しいですが、こちらなら何とかなります」といったように、親身に代替案を探してくれる心強い存在なのです。
もっと知っておきたい!多様化する学校の「外部専門家」たち
用務員さん、事務員さんの他にも、様々な専門知識を持った方々が学校を支えています。
スクールカウンセラー、SA、SSW:心と福祉の専門家
- スクールアドバイザー(SA):文科省管轄のスクールカウンセラーとは異なり、自治体や教育委員会に紐づいています。資格はカウンセラーと同じですが、業務内容は若干異なります。
- スクールソーシャルワーカー(SSW):2008年から文部科学省が設置。社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つ福祉相談の専門家で、児童相談所など行政機関との連携役も担います。
スクールロイヤー、スクールサポーター:法律と安全の専門家
- スクールロイヤー:近年、特に重要性が増しているのが弁護士であるスクールロイヤーです。2020年度から文部科学省によって本格的に設置されました。いじめや虐待、保護者からの過剰な要求といった困難な問題に対して、法的な視点から具体的な対応策を助言してくれます。教員向けの研修や予防教育も担っており、先生方を法的に守ってくれる、まさに「最後の砦」ともいえる存在です。
- スクールサポーター:警察のOBなどが就任し、その知識を活かして児童生徒の問題行動への対応、防犯講話、不審者対応、学校の安全点検、行事の見回りなど、学校の安全を守ります。
地域との連携
さらに、退職された校長先生や地域の民生委員・児童委員が不登校生徒に対応してくださったり、地域の自治会・町内会、同窓会が学校を支えてくれたりと、語り尽くせないほど多くの人々が学校に関わっています。
まとめ:あなたは一人ではない。チームで子どもたちを支えよう
今回は、学校を支える人々を「生活編」としてご紹介しました。前回の「【初任者・実習生へ】先生は一人じゃない!養護教諭・スクールカウンセラーとの連携で知る「学校のチーム力」」と合わせると、いかに多くのプロフェッショナルが学校に関わっているかがお分かりいただけたかと思います。

特に、スクールロイヤーのように新しく設置されたポジションもあります。常に新しい情報にアンテナを張り、こうした専門家の方々と連携していくことが、これからの教員には求められます。
日々の業務に追われると、つい視野が狭くなりがちですが、あなたの周りにはこれだけ多くの専門家がいます。一人で抱え込まず、ぜひ積極的に彼らを頼ってみてください。それぞれのプロフェッショナルと「チーム」として連携することが、子どもたちの豊かな学びを守り、そして何より先生自身の心を守ることにも繋がるのです。
この記事は動画「【初任者・実習生向け】用務員さん、事務員さん…どう関わる?明日から使える「チーム学校」の作り方」をもとに作成しました。




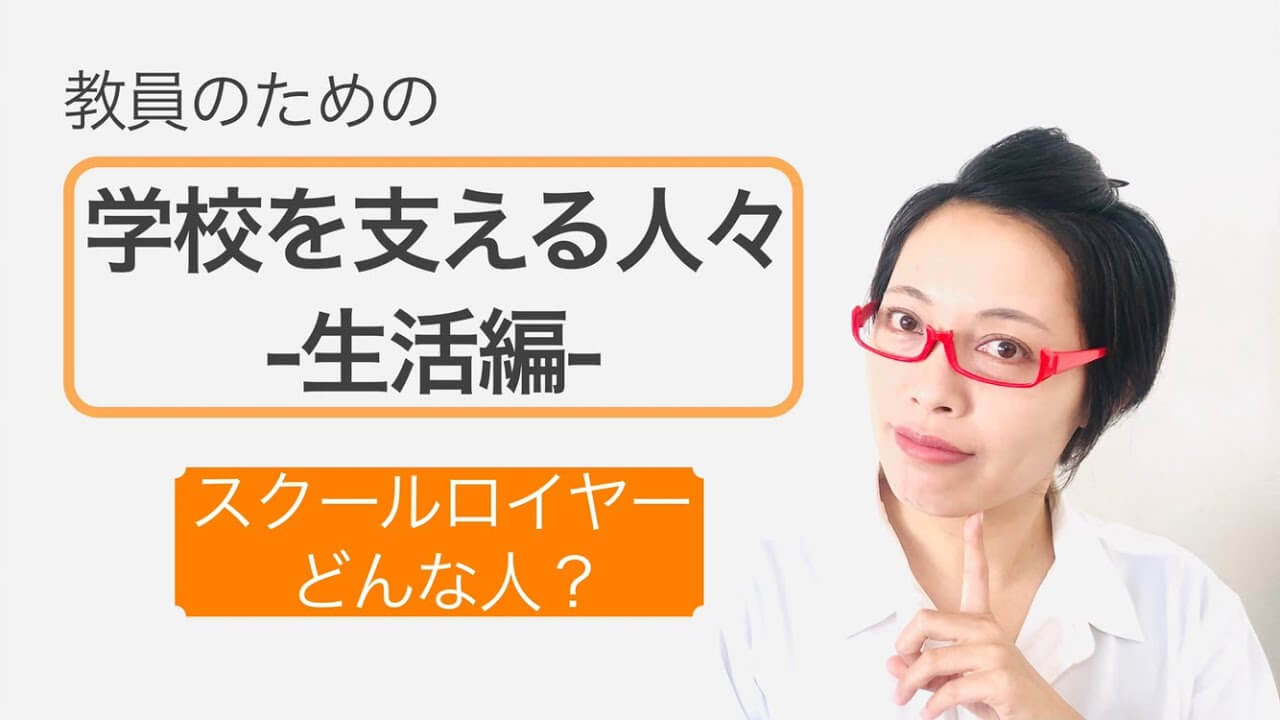


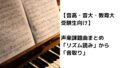

コメント