「教員だって、怒らなくていいなら怒りたくない」
これは多くの先生方が感じることではないでしょうか。
しかし、ドラマティックな毎日が繰り広げられる学校生活の中では、どうしても生徒を指導するために怒らなければいけない場面に直面します。
この記事では、教員歴10年の経験から身につけた、生徒を良い方向へ導くための「プロの怒り方」について、3つのポイントに分けて解説します。感情的にぶつかるのではない、生徒の未来を見据えた冷静で効果的な指導法をご紹介します。
プロの怒り方①:強く怒る時
まず一つ目は、「強く怒る時」を見極めることです。基本的には感情的に怒らないことが大切ですが、時には強く、ビシッと怒らなければならない場面があります。
それは、以下のような状況です。
- 本人や周りに危険が及びそうな時
- 差別的な発言や行動があった時
- 人や物を傷つけた時
これらのケースでは、まず感情を込めてでも強く「いけないことだ」と伝える必要があります。
危険が伴う行為は、本人だけの問題ではなく、他者を巻き込む怪我につながる可能性がある非常に怖いことです。また、差別的な発言も、本人が無意識であったとしても、まずはっきりと「いけない」と指摘することが重要です。
理由がどうであれ、人や物を傷つける行為は絶対に許されません。その第一歩として、「強く怒る」という姿勢が求められます。
プロの怒り方②:怒った後の「冷静な対話」の手順
強く怒った後には、必ず個別で話す時間を設けます。ここからは冷静な対応が鍵となります。問題を起こした生徒と向き合い、座って話すことが大切です。
なぜ強く怒ったのか理由を話す
まず、なぜ自分が強く怒ったのか、その理由を丁寧に説明します。
「あなたや周りに危険が及ぶ可能性があった」「もしそのままにしていたら、もっと怖いことが起こっていたかもしれない」ということを、ゆっくりと伝えます。
生徒の言い分を最後まで聞く
次に、問題を起こした生徒の言い分を聞きます。
この時、最も重要なのは「話を途中で遮らずに、最後まで聞く」ことです。途中で「ん?」と思ったり、イラッとしたりしても、そこはぐっとこらえ、「うん、そうだね」と肯定的に相槌を打ちながら、まずは全てを聞き切ります。
矛盾点や詳細について質問する
生徒の話を全て聞いた上で、こちらから質問をします。
「これとこれは話が矛盾しているけれども、どういうことかな?」 「その時、どういう気持ちだったの?」 「ここについて、もう少し詳しく話してくれる?」 といった形で、矛盾している点や、より深く知りたい点について尋ねます。
この質問に対する回答も、決して遮らずに最後まで聞く姿勢を貫きます。このやり取りを何度か繰り返します。
良い所・悪い所・改善点を伝える
最後に、「良い所」「悪い所」「改善点」の3つを話します。
怒られるような問題行動の中にも、その子なりの良い部分が一つや二つはあるはずです。例えば、暴力という行動の裏に「自分を守りたかった」「前に自分が嫌なことをされた仕返しをしたかった」といった感情が隠れていることもあります。
一方的にその子だけを責めるのではなく、行動の背景にある「自分を守りたかった」といった感情を受け止め、その部分を「良いところ」として認めて伝えてあげます。
その後に、悪い点をズバッと言います。「言い分は分かった。けれども、それを暴力という形にしてはダメだ」とはっきりと伝えます。
そして、具体的な改善点を提示します。「もしイラッとしたら、手を出すんじゃなくて、まずは言葉で説明すればいい。それが難しければ、その場を離れて冷静になって、他の人や先生に協力を求めればいい」というように、次に繋がる行動をきちんと話してあげます。
この段階まで来ると、お互いに冷静に話ができているはずです。最後は笑顔で、「もっとこういう風にしてくれたら良かったんだよ」「今回のことで、こういうことが分かったね」と肯定的に生徒を送り出してあげましょう。
プロの怒り方③:怒る時の注意点
最後に、怒る際に注意すべき点についてです。これは指導の効果を最大化し、教員自身を守るためにも非常に重要です。
教員は複数で対応する
生活指導は、一対一ではなく複数の教員で対応するのが基本です。
教員自身の冷静さを保ち、指導の客観性を担保する(証拠を残す)意味でも、また役割分担のためにも、複数での対応が鉄則です。もし一人で対応せざるを得ない場合でも、改めて時間を設け、教員が二人以上いる状況で話をするようにしましょう。
記録をきちんととる
指導の内容は、きちんと記録に残すことが大切です。
生活指導専用のノートを作り、「言ったこと」や「やったこと」を記録していくのが最善です。様々な場所にメモをしたり、紙切れに書いたりすると、情報が漏れたり紛失したりするリスクがあります。専用ノートは鍵のかかる場所で厳重に管理しましょう。
ICレコーダーでの録音は、大人でも気分が悪いもので、相手を身構えさせてしまうため、あまりお勧めしません。どうしても必要な場合は、必ず相手の許可を取ることが大事ですが、なるべく避けたい方法です。
特別な支援が必要な可能性を心得る
感情的に行動してしまう生徒の中には、自分の言いたいことややりたいことを口でうまく伝えられず、結果として暴力などの行動に出てしまう場合があります。
「この子は特別な支援が必要かもしれない」「感情を言葉にするのが苦手なのかもしれない」「暴力という手段しか知らないのかもしれない」といった配慮を、頭の片隅に置いて指導することが必要です。
周囲と連携する
生徒指導は、一人で抱え込むものではありません。
その生徒が何をしたのか、そしてどのように指導したのかという情報を、管理職、学年主任、生活指導主任、養護教諭、そして保護者といった周りの人たちと連携を取りながら進めることが不可欠です。
まとめ:怒ることは、その子を導くための指導
「怒る」という行為は、単なる感情のぶつかり合いではありません。時間や人、手間をかけて、その子を良い方向に導いていくための「指導」です。だからこそ、一人では絶対にできないのです。
子ども側からすれば、怒られることは「怖い」「うるさい」と感じるかもしれません。しかし、教員側は声を大きくして強く伝えている時でも、頭の中は「この子をどう指導すれば良いか」「どうすれば良い方向へ導けるか」を考えている、意外と冷静なものです。
そして、この怒ったこと、ぶつかった経験が、後々その子との「絆」になることも少なくありません。怒ったからといって、その子の全てを嫌いになるわけでも、人格を否定するのでも決してないのです。
怒った後に何が待っているのか、その子の未来をどう見据えるか。その子の未来まで見据えて関わっていくことこそ、プロの指導と言えるでしょう。
この記事は動画「【先生のための生徒指導】もう感情的に怒らない!叱責を「絆」に変えるプロの技術」をもとに作成しました。




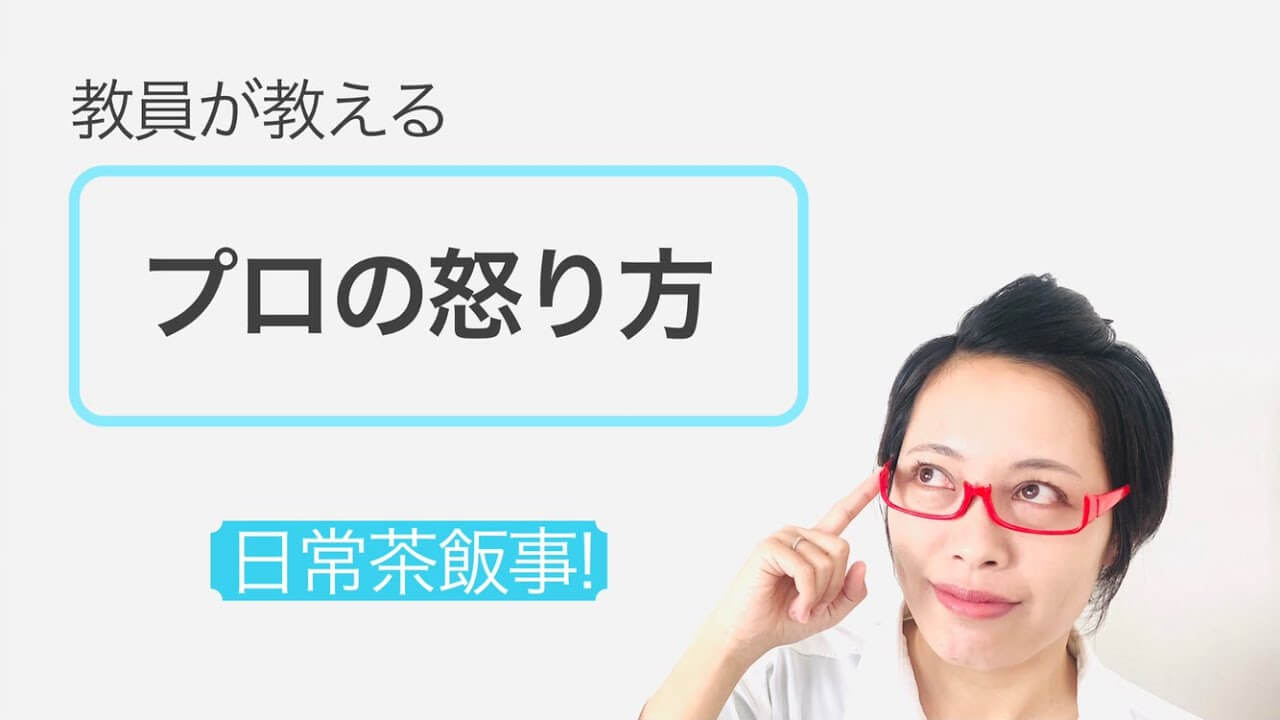





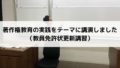

コメント