今回は「評価」についてお話しします。
2021年度から中学校では新しい学習指導要領が施行され、評価の方法にも変更が加えられました。大きな変化として、評価の観点が4観点から3観点に整理された点が挙げられます。詳細については、教職員支援機構が公式に解説を出していますので、そちらをご参照ください。
本記事では、現場レベルで評価を行う際に私が実践している3つのポイントをご紹介します。
学習評価の基本:新学習指導要領で変わる評価の視点
2021年度から中学校では、新学習指導要領が完全実施され、評価方法にも大きな変化がありました。
従来の「関心・意欲・態度」などの4観点評価から、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性」の3観点評価に改定されました。
新学習指導要領に対応した評価方法については、NITS教職員支援機構が公式に詳しく解説しています。以下の動画もぜひご参考ください:
コツ1:評価項目は「先に言う」
どの項目がどのように評価されるのかを事後に伝えるのでは、後出しジャンケンのようになってしまいます。そのため、単元ごとに「このような項目があり、このように評価します」とあらかじめ伝えておくことが大切です。
たとえば、1学期や前期ごとに評価のポイントを明示しておけば、生徒は自分の得意・不得意を踏まえて対応策を考えることができます。歌が苦手な生徒は筆記試験で挽回しよう、筆記が苦手な生徒は実技で頑張ろう、というように目標を立てやすくなるのです。
このように評価項目を「先に言う」ことは、生徒にとっても教員にとっても非常に重要です。
コツ2:評価基準には「明確な線」を設定する
評価で気をつけること、二つ目は「明確な線」です。
ワークシートなどを添削するとき、「どういった内容だとA」「どういった内容だとB」「どういった内容だとC」と、あらかじめ設定しておくことが大事です。
この「明確な線」は、教員だけでなく生徒や保護者にもわかるように示すことが大切です。評価を進めていく中で基準がぶれてしまわないように、初めにしっかりと設定しておきましょう。
また、評価の軸を維持するためには、ワークシートの添削などをなるべく時間をまとめて一気に行うのが理想です。
時間を設定するのはなかなか大変です。たとえば、1人あたり1分で評価したとしても、1クラス35人、1学年140人を評価するには2時間以上が必要です。その時間をきちんと確保して、一貫した評価を行いましょう。
時間管理の方法については、他の動画でも紹介していますので、ぜひそちらもあわせてご覧ください。
コツ3:評価の「記録を残す」
実技試験、特に歌の試験などでは、録音や録画をして記録を残すことが重要です。
後で評価について疑問が出た場合や、質問を受けた場合に確認ができるようにしておきましょう。
また、生徒や保護者から評価について質問があったときに、「これがその理由です」と明確に説明できるようにするためにも、記録は自分自身を守る手段になります。
ワークシートなどすべての記録を残すのは難しいかもしれませんが、最近では複合コピー機にスキャナー機能がついていることが多く、USBやSDカードに画像データとして保存することも可能です。
重要だと感じたものや残しておきたいと判断したものは、積極的にスキャンして記録しておくとよいでしょう。コピー機の性能にもよりますが、自動送りの設定を使えばスキャンにもさほど時間はかかりません。ぜひ活用してみてください。
まとめ:生徒に信頼される評価方法を目指して
今回は評価の方法について、現場で気をつけている3つのポイントをご紹介しました。
- 評価項目は「先に言う」
- 評価基準には「明確な線」を設定する
- 評価の「記録を残す」
今日は評価の仕方のポイントについて話をしました。評価は生徒の一生を左右するほど重要なものです。自分自身が納得していれば、生徒や保護者の方にも納得してもらえるはずです。
そして、生徒への評価は自分自身の評価にもつながります。自身の指導法を見直す際には、生徒の評価を参考にしてみてください。
この記事は動画「音楽教員必見!生徒が納得する評価の付け方【新指導要領の3ポイント】」をもとに作成しました。






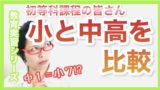





コメント