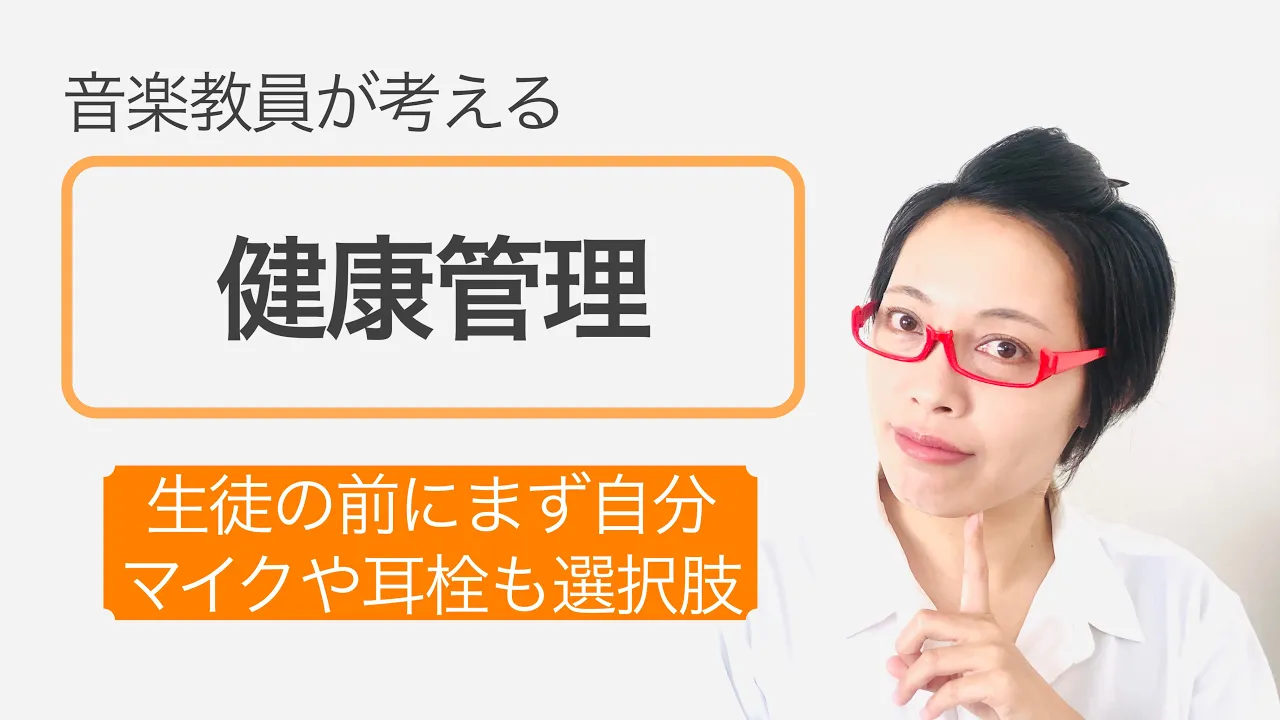日々の授業準備や生徒対応に全力で取り組む中で、ご自身の体のことを後回しにしていませんか?
「授業後はいつも声がガラガラ」
「立ちっぱなしや指揮のしすぎで肩や腰が痛い」
「ピアノの弾き過ぎ」
「忙しすぎて自分のケアまで手が回らない」
…そんな風に感じたことはありませんか?
音楽科の教員にとって、声や耳そして体そのものは、授業を届けるための「大切な楽器」そのものです。
この記事では、音楽科の健康管理をテーマに、先生方ご自身の心と体を守り、無理なく長く楽しく教員を続けていくための具体的な方法を、3つのポイントに絞ってご紹介します。
明日からすぐに実践できるセルフケアのヒントがきっと見つかりますので、是非最後までご覧ください。
健康管理の第1歩:「守る」技術
健康管理の1つ目は「守る」技術です。
声、耳、体を守る技術についてお話しします。つい頑張ってしまいがちな私たちですが、自分を守るための具体的な工夫を知っておくだけで、日々の負担は大きく変わります。
大切な「声」を守る工夫
まずは声についてです。大きな声を出さなくても生徒に指示を届かせる方法はたくさんあります。
マイクを常に使う習慣
毎時間地声で声を張り上げるのは声帯にとって大きな負担になるため、マイクを常に使うことを習慣にしてみてはいかがでしょうか。
先生の声が小さいと言われるのが不安かもしれませんが、これはプロとして自分の喉を守るための大切な仕事道具だと考えてみてください。
指示の出し方の工夫
合図を、手を挙げる、和音、手拍子など、音や見た目で分かるものに決めておくと便利です。
例えば、リンリンという鈴の音とか、カウベル コンコンといったものを合図にしておくのもいいと思います。生徒がその合図に慣れてくれば、教員も何度も声で注意を促す必要がなくなり、声の消費を抑えられます。
歌の指導での模唱
歌の指導での模唱も、回数・やり方を決めましょう。教員が見本を見せる、生徒が歌う、確認をする。このワンセットで十分です。
なぜなら、何度も繰り返し見本を示すと、それだけで喉を酷使してしまうからです。これは生徒が主体的に歌う時間を確保することにもつながります。何度も見本を見せるという癖をつけてしまうと、1回の集中力も途切れがちになってしまいます。

「耳」を大きな音から守る
次に耳です。特に器楽や吹奏楽の指導などでは、大きな音に長時間さらされます。
金管楽器や打楽器の近くからは少し距離を取ることを意識してみてください。大音量のスピーカーや長時間のイヤホンも同様に、音と距離を取ることを意識しましょう。気がつかないうちに聴力がダメージを受けてしまう可能性があります。
どうしても近くで指導する必要がある場合は、短時間だけでも耳栓を使うというのも自分を守る有効な手段です。最近では、完全に音を塞ぐだけの耳栓ではなく、適切な音量で音を聞き取るというような耳栓もあります。是非探してみてください。
「体」のケアと教室環境
そして体のケアです。
指揮や立ち仕事
指揮を振る時は、腕だけで振ろうとせず、体全体を使って楽に振ることを意識してみてください。譜面台は目線より少し下ぐらいが見やすいです。
なぜなら、肘とか肩に余計な力が入ってしまうと痛みの原因になってしまうからです。足元も大切なので、できればクッション性のある靴や着圧のソックスなどを選ぶと、長時間の立ち仕事も少し楽になります。
教室の環境
意外と見落としがちなのが教室の環境です。
乾燥は喉の敵です。加湿器などで湿度を40%から60%ぐらいに保つこと、そして授業の合間には一口でも水を飲むこと、換気することなどを心がけてみてください。声帯の潤いを保つことがかすれ声の予防になります。

重いものの運搬
最後に、楽器など重いものを運ぶ時、台車を使ったり、2人で運んだり、生徒の力を借りるということを当たり前にしましょう。無理して体を痛めてしまっては元も子もありません。
「これくらい平気」という過信が1番危険だったりします。
負担を「減らす」工夫
音楽科の健康管理2つ目は「減らす」です。
体の負担だけではなく、頭や心の負担を軽くするということも健康管理には欠かせません。
頭と心の負担を軽くする
授業の型を決める
まずは授業の型を決めてしまうという方法があります。
例えば、導入5分・本日の活動展開が40分・振り返り5分のように、時間の流れをパターン化します。導入の中でも、例えば常時活動とか、まとめの仕方もいつも同じになっている、そういった「型」を決めてしまいます。
そうすることによって、毎回ゼロから授業構成を考える必要がなくなります。毎回考えるとそれだけで大きなエネルギーを使ってしまいます。もちろん型通りに行かない日や活動もありますけれども、基本の軸があるだけで準備の負担が減り、心に余裕が生まれます。また、生徒もその型を知っていれば事前に動いてくれるということもあるかもしれません。

評価はできるだけシンプルに
次に、評価はできるだけシンプルにするということをお勧めします。
例えば、評価の基準を3段階ぐらいに絞って、そして採点をするのは火曜の放課後というように、評価業務をする曜日を固定してしまう。これもいいと思います。
なぜなら、いつでもできると思うとかえって後回しにしてしまって、精神的な負担になり続けるからです。評価に悩む時間を減らし、その分生徒たち子供と向き合う時間を増やしたいものです。

心身の休息を確保する
連絡の境界線を引く
それから、連絡の境界線を引くということも大切です。
教員は保護者の方や同僚の先生、部活動の連絡、外部の連絡などもあります。そういった対応する時間帯というのをあらかじめ決めておくというのが1つの手です。
理由は、時間外の連絡に対応することが当たり前になってしまうと、心も体も休まらなくなってしまうからです。
誠実に対応することはもちろん大切ですし、生徒の対応は最優先です。ですので、自分を守るためのルール作りとして、その他の急がない対応については境界線を引くというのがいいと思います。

必ず休む日を先に確保する
そして特に忙しい合唱コンクールの時期や入学式、卒業式などの時期でも、週に1日は必ず休む日を先に確保してください。
やることが終わったら休もうと思っていると、休める日は永遠に来ないからです。先にプライベートの用事や自分をケアする日をあらかじめ確保しておくといいです。声も体も心も完全にオフにする日を作ることで、また次の日から頑張るエネルギーが湧いてきます。
体の小さな負担を減らす
物の置き場所を固定する
そして小さなことですが大事なこと、物の置き場所を固定するということで、ちょこちょこと動き回る手間が省けます。
例えばピアノの横に小さなトレーなどを用意しておいて、指示の棒・指揮棒・筆記用具、それからタイマーや赤ペン・笛、それからホワイトボードマーカーとか消すものとか、そういったものの定位置を決めておくということです。
そこに指定席を作るだけで、授業中あちこち動き回る手間が省けて体の負担を減らすことができます。
日々の回復と「備える」習慣
音楽科の健康管理3つ目は「備える」です。
日々の回復と、もしもの備えです。頑張るためには土台となる心身のコンディションを整えて、万が一のサインに気づけるようにしておくということが重要です。
健康の土台作り
まず健康の土台作りとして、起きる時刻を毎日揃えることを意識してみてください。休日も平日も同じ時間に起きることで、体内リズムが整って睡眠の質が向上しやすくなります。
朝食をしっかり食べること、少しでも歩くことなども基本的なことですが、やはり大切なことです。
自身の状態に気づく
1分間の簡単な記録
そして是非試していただきたいのが、1分間でいいのでその日の簡単な記録をつけることです。手帳の隅などに、声の調子はどうだったか、よく眠れたか、体調はどうかなどを、丸や一言メモするだけです。
自分の心身の状態を客観的に見る習慣がつくことで、ちょっと無理が続いているなという不調の前兆に早めに気づけるようになるからです。
我慢せず早めに相談する
もし辛いと感じることがあれば、我慢せず早めに相談してください。学校には養護の先生、管理職の先生、産業医の先生など頼れる方々がいらっしゃいます。
「これぐらいで相談するの大げさかな」なんて思う必要は全くありません。先生方が1人で抱え込まず元気でいてくれることが、子供たちにとっても1番大事なことです。
専門家への相談が必要な「要注意サイン」
特にかすれ声が3日以上続く場合、片方の耳が聞こえにくい・強い耳鳴りがするという場合、ぐるぐる回るような眩暈がするという場合、2週間以上眠れない日が続くなという場合、こういったサインは専門家の相談が必要な要注意サインです。
もし見つけたら早めに専門医を受診し、この状況を学校と共有するようにしてください。

まとめ:できることから、まずは小さな一歩を
今回は音楽科の健康管理というテーマでお話ししました。
3つの観点、「守る」「減らす」そして「備える」。こういった観点でご自身の行動、生活を見直してみてください。
たくさんあって全部いっぺんにやるのは大変そうと感じたかもしれません。
でも大丈夫です。完璧にやろうとしなくて構いません。まずは1つ、ご自身ができそうだなと思うことから試してみてください。
例えば、「明日は授業の合間に水を一口飲もうかな」とか、「週末は起きる時間だけ揃えてみようかな」とか、そんな小さな一歩で十分です。
教員という仕事は本当にやりがいがありますが、同時に自分を削ってしまいがちな仕事でもあります。どうか子供たちを大切に思うのと同じくらい、ご自身のことも大切にしてあげてください。教員が心も体も健康でいることが、最高の音楽を子供たちに届けるための何よりの土台になります。
この記事は、動画「【音楽科の先生へ】あなたの体は「大切な楽器」!無理なく教員を続けるための健康管理術 3つのポイント」をもとに作成しました。