今日は「教材の探し方」について、私が実践していたことをお話しします。
日常の校務や生活に追われていると、教材探しの時間がなかなか取れないと感じるかもしれません。しかし、実は日常の中にこそ教材のヒントがあふれています。
私は職業病のように、どこかに教材が転がっていないかという視点が常にあります。このような視点で生活をすると、「これが教材になりそう」「あれが使えそう」とアンテナが高くなっていきます。今回は、私が実践してきた具体的なヒントをご紹介します。
街に出て教材を探そう
まず一つ目の方法は「街に出ること」です。
もちろんインターネット上にもたくさんの情報がありますが、やはり一番大切なのは実際に街に出ることです。特に音楽科の場合、街には音楽や音がたくさんあふれています。音楽に関する情報はもちろん、何気ない生活音や自然の音も教材に活用できる可能性があります。
また、既存の教材や教科書と組み合わせて利用する方法もあります。情報を得るには自分の足で稼ぐことが重要です。パソコンやタブレット、本や資料と向き合うことも大切ですが、ぜひ街に出て新たな発見をしてください。街に出ることで、多くの教材のヒントが見えてくるはずです。

ウェブサイトを活用する
教材探しの二つ目の方法は「ウェブサイト」です。
街で情報を集めた後は、ウェブサイトを使って情報を整理し、深めていきましょう。もちろん、事前にウェブサイトで情報を収集してから街に出るのも良い方法です。
情報収集については、私はブックマークの整理がとても重要だと考えています。
私のChromeのトップページは、「毎日見る」「週1見る」「暇なとき見る」「ツール」「学校」「個人」「仕事」などに分類しています。特に「毎日見る」「週1見る」「暇なとき見る」のカテゴリが、私の重要な情報源となっています。
毎日見る
教育分野では文部科学省や文化庁などの省庁のサイト、音楽分野ではオリコンスタイルなどの最新情報、一般ニュースではNHKやYouTubeの情報、新聞や地元紙、共同通信や時事通信などのニュースソース、教育新聞や日本教育新聞といった教育専門紙を毎日確認しています。
週1見る
政党や内閣府、政府広報など、教育や子育てに関する情報が豊富なページをチェックしています。これらの情報は新聞よりも早く動向が把握でき、長期的な視点でも役立ちます。
さらに、電通報や日経スタイルなどの広く一般的な情報源、東洋経済やダイヤモンドといった雑誌系のウェブサイトも週1回確認しています。
暇なとき見る
音楽関連ではヤマハやカワイといった音楽教育・楽器関連のサイト、レコード会社の最新情報、CDや配信、DVDの発売情報、アーティストの動向などを収集します。また、合唱や吹奏楽といった部活動関連の情報もウェブサイトから得ています。
教育関連では塾やベネッセといった教育産業関連企業のウェブサイトも見ています。さらに、趣味も兼ねて芸能関係のサイト(ワタナベエンターテインメント、ジャニーズ、吉本興業など)もチェックしています。
新聞と教科書を活用する
教材探しの三つ目の方法は「新聞」と「教科書」です。
街やウェブサイトに加えて、紙媒体も非常に重要です。新聞はウェブサイトでも確認しますが、一般紙、地元紙、教育専門紙など幅広く目を通します。
教科書は、特に音楽科のように教科書に完全には沿わない授業が行われる場合、再度くまなく読むことをおすすめします。初めに一通り読んだとしても、2度3度読むことで意外な発見があることもあります。体系的な説明が可能になる箇所や、新しい活用法が見えてくることもあるでしょう。
教科書を読む際には学習指導要領と並行して確認するのも良い方法です。
学習指導要領のどの項目に対応しているのかを確認したり、教科書の工夫に気づいたりすることができます。
また、自分が担当する学年や校種の教科書だけでなく、他学年・他校種の教科書も見てみると新たな発見があります。たとえば中学校にいる場合は、小学校5・6年生や高校の教科書にも目を通すことで、学びの流れや発展を理解できます。
まとめ:教員のための授業教材の探し方(生活・社会の中から見つけるには?)
今回は教材探しの方法についてお話ししました。
教材研究や具体的な教材の活用方法については、他の動画でも詳しく紹介しています。教材探しは非常に重要な第一歩です。
先生方が置かれている環境や情報収集のしやすさには個人差があります。文字情報から得やすい方、五感で感じ取る方、教材探しの段階(最初・途中・最後)によっても、得る情報の方法や種類は異なります。ぜひ複合的な視点で、教材探しに取り組んでみてください。
この記事は、動画「教員必見!街・Web・紙から教材を見つける3つのコツ【実践例つき】」をもとに作成しました。







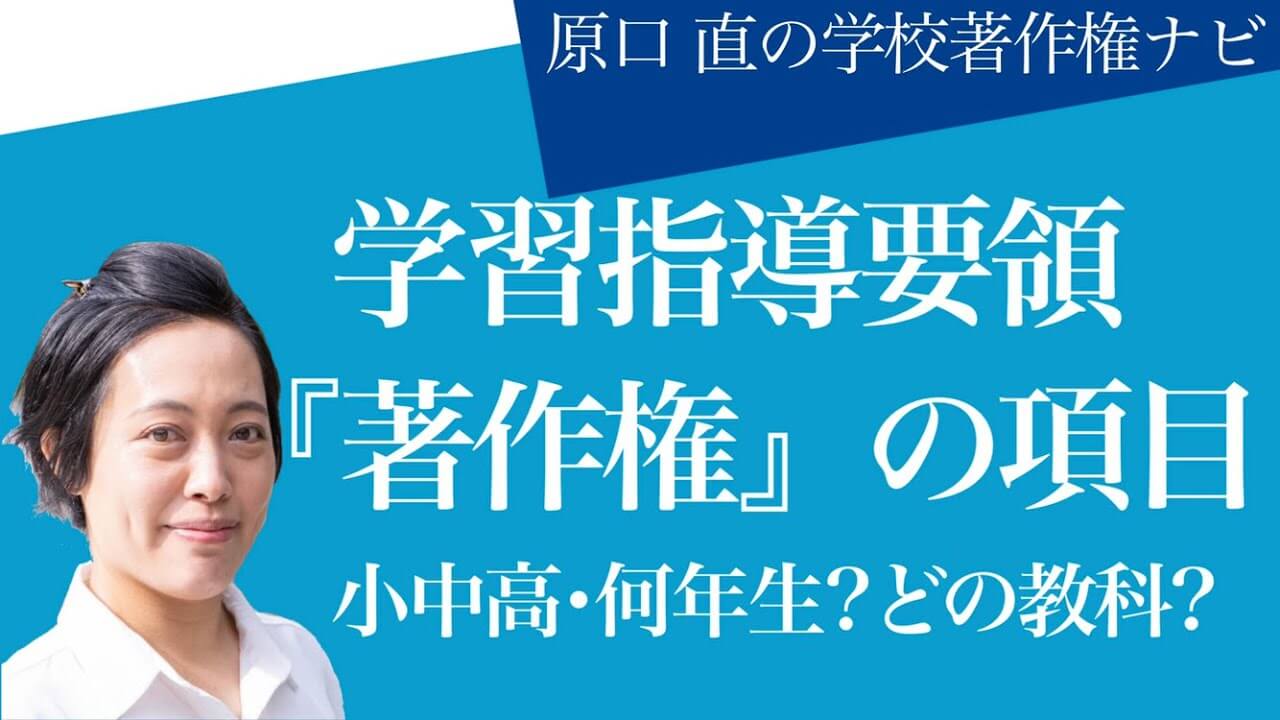



コメント