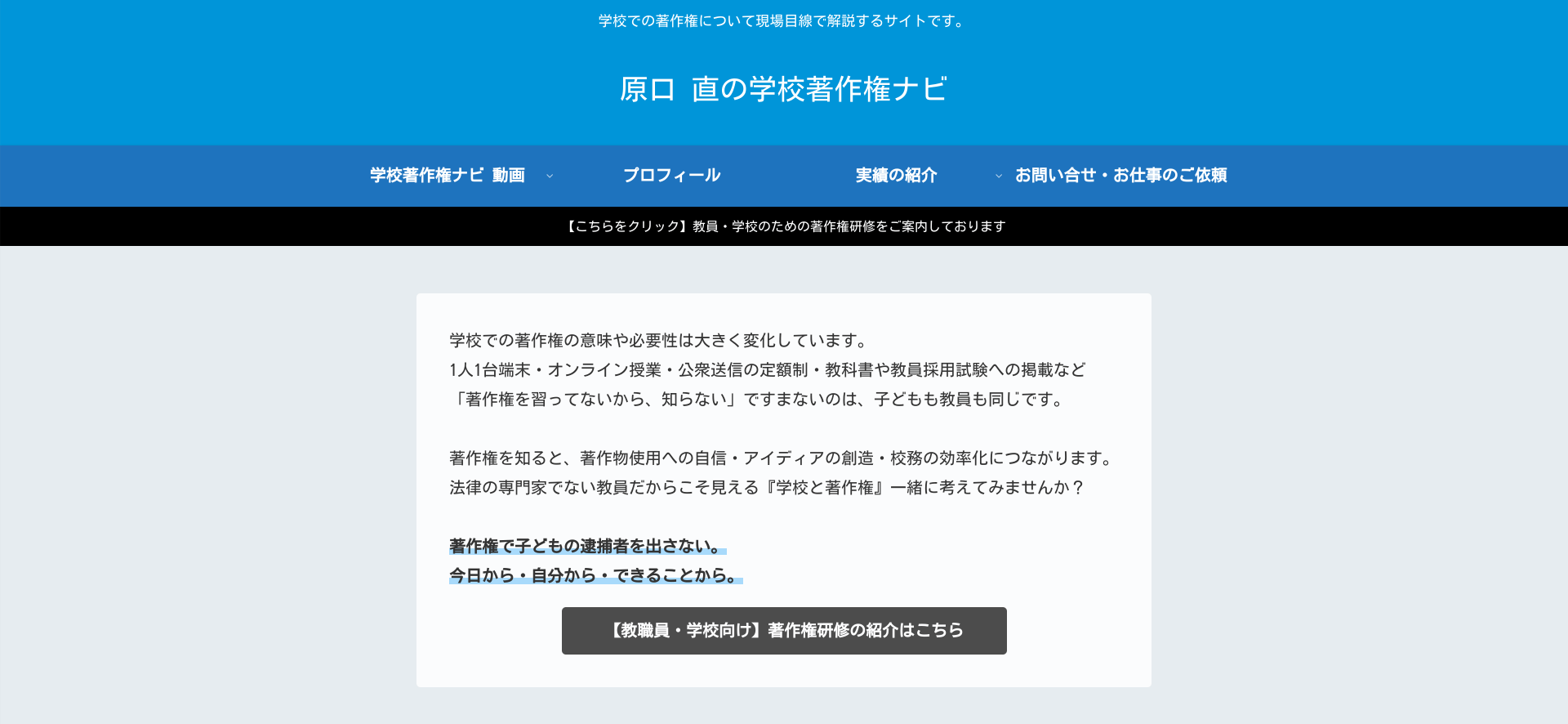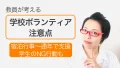Nコン2025に参加する際に欠かせない「著作権」に関する重要なポイントを解説します。
課題曲の発表とともに、毎年楽しみにしている方や、今年初めて参加するという学校もあることでしょう。この記事では、自由曲の選定、楽譜コピーの注意点、改変の扱い、放送配信に関するルールなど、音楽科の授業に近い感覚で、できるだけ専門用語を避けながら分かりやすくご紹介します。

自由曲の選曲と放送配信の確認
Nコンでは、課題曲と自由曲が設定されており、課題曲は校種ごとに指定されています。一方で自由曲は各校が自由に選べますが、ここで注意すべきなのが「放送配信可能な楽曲であるかどうか」という点です。
Nコンの演奏はテレビやインターネットで放送・配信されるため、著作権の管理団体であるJASRACやNexToneの検索サイトで、その楽曲の「放送」「配信」欄が「○」になっているかどうかを必ず確認してください。「×」や空欄の場合、放送できない可能性があります。
また、検索には作品コードが必要です。Nコンの公式サイトには、フローチャート形式で楽曲の確認手順がわかりやすく掲載されているので、ぜひ活用してください。
楽譜コピーのルールと許諾手続き
人数分の楽譜を揃えるのは手間やコストがかかるため、コピーを検討したくなることもあるかもしれません。しかし、基本的に楽譜のコピーは著作権上NGです。
ただし、次のような例外があります:
- 楽譜が絶版または廃版で、入手が不可能な場合
このような場合は、出版社やJASRACなどに連絡してコピーの許諾を取得してください。許諾書が届いたら、それをコピーに貼付して提出する必要があります。申請中であっても許諾書が手元にないと審査対象外となることがあるため、早めの対応を心がけましょう。
改変には著作権者の許可が必要
自由曲には演奏時間の制限があるため、「小節を削る」「繰り返しを省略する」「移調する」などの変更を加えたくなることがあります。しかし、これらの行為はすべて「改変」にあたるため、著作権者の許可が必要です。
以下のような行為は改変と見なされます:
- 小節の削除
- リピート(繰り返し)の省略
- 移調・転調
- テンポの変更
- 楽器の変更
- ディヴィジの削除
改変を行う際には、「楽譜の許諾に関する報告書」と著作権者からの許諾書をセットで提出しなければなりません。なお、楽譜に「一部省略可能」と明記されている場合は、報告書の提出は不要です。
改変の申請には時間がかかることもあるため、「この曲を自由曲にしたい」と思った時点で、早めに行動することをおすすめします。
放送配信と著作権管理団体の登録確認
自由曲を放送や配信したい場合、誰が著作権を持っているかも重要な確認事項です。楽曲がJASRACやNexToneといった著作権管理団体に登録されていれば、NHKが一括して手続きを行ってくれます。
しかし、これらの団体に登録されていない場合や、個人が著作権を保有している楽曲は、放送や配信ができない可能性があります。したがって、楽曲の使用を検討する際には、必ず著作権の管理状況を事前に確認しましょう。
また、著作権者は必ずしも「作曲者本人」であるとは限りません。著作権が相続や譲渡により別の人に移っているケースもあるため、確認を怠らないようにしましょう。
まとめ:著作権を理解して安心してNコンに臨もう
Nコン2025に参加する際に押さえておくべき著作権のポイントを、次の4点に整理しました:
- 自由曲の放送配信の可否を事前に確認する
- 楽譜のコピーは原則NG、例外時は許諾を取得する
- 改変には必ず著作権者の許可が必要
- 放送配信のために著作権管理団体への登録状況を確認する
これらの手続きが面倒に思えるかもしれませんが、著作物を使用する際には本来すべて必要なプロセスです。私たちが授業で楽譜を自由に使えるのは、著作権法第35条という特例があるからです。
「著作権法第35条って何?」と思った方は、ぜひYouTubeチャンネル「原口直の学校著作権ナビ」をご覧ください。第35条の内容や、なぜ学校教育の中では申請せずに使用できるのかを分かりやすく解説しています。