毎日多くの生徒や保護者、業者の方々と接する教員の仕事。たくさんの人と関わる中で、知らず知らずのうちに身についてしまう「職業病」はありませんか?
今回は、音楽教員歴10年の経験から見えてきた、職業病ともいえる「人の見方」について、3つのポイントに分けて詳しく解説します。生徒や保護者を覚えるためのヒントや、他の業種でも役立つ視点が含まれていますので、ぜひ最後までご覧ください。
「この人はロック好き?」身だしなみから音楽の好みまで見抜く
まず目がいってしまうのが、その人の「身だしなみ」です。これは、持っているものや服装が高価かどうかということではありません。
グッズや時計、カバン、服装、さらには髪型やメイクといった見た目から、その人がどんな人なのかを判断・推測してしまいます。
特に音楽教員ならではの癖として、その人の身だしなみから「好きそうな音楽のジャンル」や「演奏しそうな楽器」を分けて考えてしまうことがあります。
例えば、「この人はロックが好きそうだ」「フォークソングが似合いそう」、あるいは「フルートを吹いていそうだ」といった具合です。これはまさに職業病と言えるかもしれません。
音楽の先生におすすめの服装・靴・メイクの選び方–保護者対応から授業まで役立つ実践法
【教育実習生必見】持ち物完全ガイド|靴・服・カバンの選び方をわかりやすく解説
視線は口ほどに物を言う?目力で相手の心を読む観察眼
人と話す際、「視線」や「目力」も無意識に注目してしまうポイントです。
こちらがじっと相手の目を見て話した時に、相手がどう反応するかを見てしまいます。こちらに負けじと見返してくる人もいれば、目力に負けて視線をそらしてしまう人、なかな目が合わない人もいます。もちろん、こちらと同じように強い目力でじっと見てくる人もいます。
これは子どもも大人も同じで、その人が「どこを見ているか」「どのように見ているか」に注目してしまうのも、教員ならではの職業病の一つでしょう。
声:音の特性から話の組み立て方まで分析
音楽教員だからこそ、人の「声」は否が応でも気になってしまいます。
絶対音感はなくとも、声の高い低い、抑揚、声の裏返り、さらには息を吸う・吐く・止めるといった息継ぎの細部に至るまで、無意識に分析してしまいます。
さらに、声という物理的な特徴に留まらず、口癖や話の組み立て方といった論理的な側面にも注意が向きます。「この人は筋道を立てて話せる」あるいは「同じ内容を言葉を変えて繰り返している」など、話の内容まで分析してしまうのです。これもまた、子ども大人を問わず行ってしまう職業病かもしれません。
まとめ:人を覚えるための視点を鍛えることの重要性
教員にとって、生徒や保護者を覚えることは非常に大切な仕事です。生徒や保護者から見れば先生は一人ですが、先生側は多くの生徒、そして保護者を覚えなくてはなりません。特に保護者の方を覚えるのは難しいものです。
しかし、保護者の方は先生が自分のことを知っていると思って話しかけてくださるため、失礼のないように対応する必要があります。
今回ご紹介した「身だしなみ」「視線」「声」といった「人を見る視点」は、相手を覚えるために非常に役立ちます。この視点を日頃から鍛えておくことは、円滑なコミュニケーションのために有効でしょう。
この観察眼は、教員の仕事に限らず、あらゆる職場で役立つ普遍的なスキルと言えるでしょう。人を深く理解するための「見る技術」として、ぜひ日々の業務で意識してみてください。
この記事は動画「【教師向け】生徒・保護者の顔と名前が覚えられない…を解決!音楽教師が教える人を見る3つの視点」をもとに作成しました。







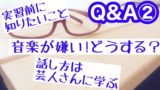
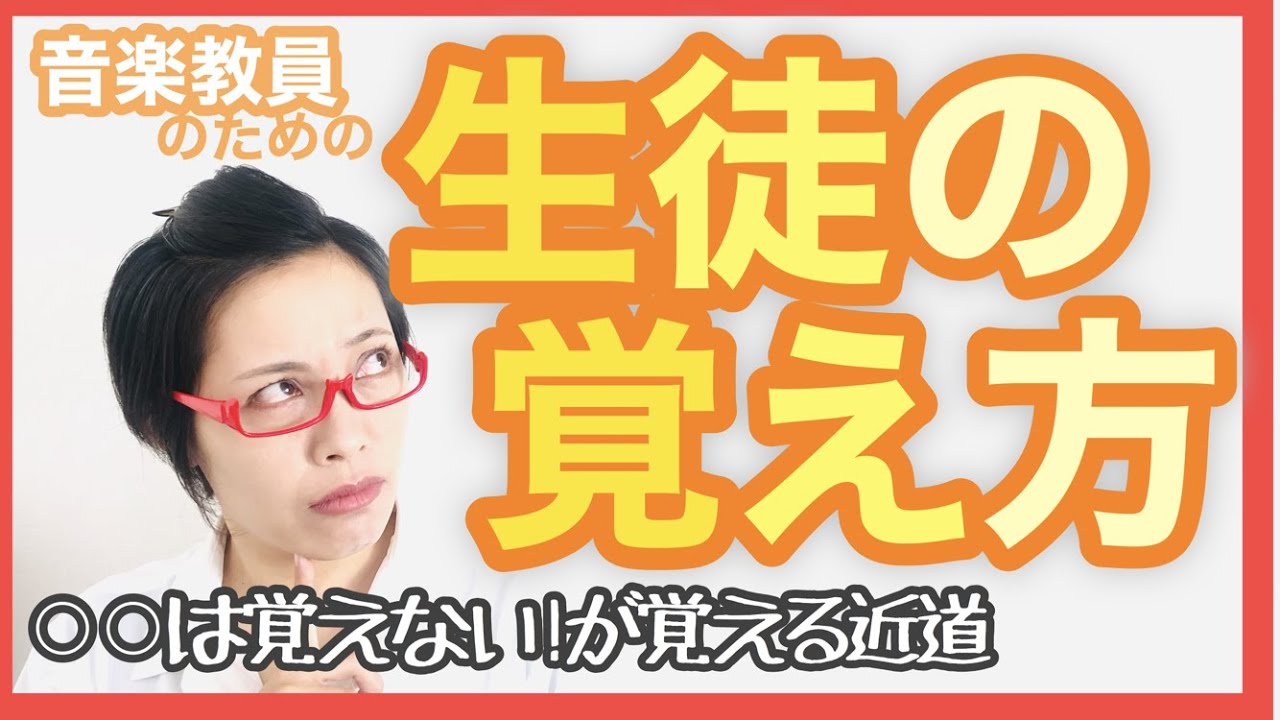
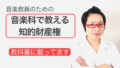

コメント