先生方は授業中の生徒からの予想外の発言に、どう対応していますか?
様々な学校の研究会や教育実習で授業を見るたびに、私が痛感するのは「授業者のアドリブ力」の重要性です。生徒の突飛な発言にアドリブでうまく返すことで、授業の流れを円滑に作ることができるのです。
このアドリブ力は、ベテランと若手の先生の授業を分ける大きな違いとも言えますが、中には経験年数に関わらず、アドリブが非常に上手い若手の先生もいらっしゃいます。
私はこの「アドリブ力」が、お笑い芸人さんの能力に似ているなと常々感じていましたが、そのスキルを学校教育の現場向けに翻訳するのは、なかなか難しいと感じていました。
そこで今回は、かつて芸能プロダクションでお笑い芸人の卵たちを間近で見てきた私なりに、教員のアドリブ力について分析してみたいと思います。
この記事は、次のようなことを知りたい方に是非ご覧頂きたい内容です。
- 生徒への上手い「返し」を知りたい方
- アドリブの力で授業をより良くしたい方
- 生徒からの予想外の反応が怖いと感じる方
この動画の他には、
「シーン…と静まり返る教室。」「次々に出る意見に、授業がまとまらない…」
音楽の授業で、子どもの予想外の反応に頭を抱えていませんか?
基礎を抑えた上で、気をつけたい学習指導案の書き方についてお話ししています。事前に項目を確認する必要性について話しています。
併せてご覧ください。
なぜ教員にアドリブ力が必要なのか?その「条件」とは
授業を参観していてアドリブ力が必要だと感じるのは、まさに生徒の反応に対する「返し」の場面です。
教育実習生の授業後の協議会でも、「あの場面で、どう返したら良かっただろう?」という議題は頻繁に上がります。学習指導案に「予想される生徒の反応」を書いても、その反応に対する反応、つまり「返し」までを具体的に考えている先生は少ないのではないでしょうか。
お笑い芸人の連携プレーに学ぶ
複数のお笑い芸人さんが出演するテレビ番組を見ていると、彼らが話し始めからオチまでの流れを何手も先まで読み、その流れを出演者間で共有していることがわかります。
「最後にこの人のリアクションや話でオチをつける」というゴールに向かって、司会者からフリがあり、数名でパスを回し、時には「裏回し」と呼ばれるサポート役が軌道修正をしながら、見事にオチまで導いていく。
この様子はサッカーのパス回しに例えられますが、その根底にあるのは、瞬時に状況を判断し、場の流れを読む高度なスキルです。
これを実現するためには、
- お互いがどのような能力を持っているかを把握している
- 誰がどのポジションで最も輝けるかを理解している
- そして、お互いを信頼し合っている
という条件が必要です。
さらに、番組によってはアドリブのように見えて、実はすべてが計算されていたり、放送作家が作成した台本に流れが示されていたり、事前の打ち合わせやリハーサル、他のライブ等での実践が重ねられていたりします。
授業は「台本なしの一発勝負」
これを授業に置き換えてみましょう。
フリである「発問」や、授業のまとめである「オチ」は教員が担当するとして、その過程で生徒一人ひとりがどのような能力(個性や知識)を持っているかを把握し、彼らのポジションを活かし、互いを信頼し合う関係を築くことが大切になります。
そして決定的な違いは、授業には台本もリハーサルもなく、常に一発勝負だということ。
だからこそ、私たちは生徒の反応を丁寧に予想し、その精度を上げることで、一発勝負の授業に備えなければならないのです。
アドリブができる目安は「1000時間」
私が大好きなYouTubeチャンネルの一つに「ナイツ塙の自由時間」があります。その中の「若手芸人へ!「アドリブ」で笑いを取ろうとするな!【笑辞苑】」という動画で、ナイツの塙さんと銀シャリの橋本さんが、漫才中にアドリブをしていい芸人の条件として「1000舞台を超えた芸人」だとおっしゃっています。
これを教員に当てはめてみましょう。仮に「1000時間」がアドリブをできるようになる条件だとすると、中学校の音楽科で3学年・各4クラス(計12クラス)を担当した場合、年間約460時間の授業を受け持つことになります。
つまり、教員がアドリブを自在に使いこなせるようになるには、およそ3年かかるという計算になります。これは現場の感覚からしても妥当な数字です。
裏を返せば、最初の数年間は焦らずに基礎を固めるべき大切な時期だ、ということです。それくらい、アドリブには腕と経験が必要だということです。
アドリブの「返し」を磨く2つのアプローチ
では、授業における生徒への「返し」の力は、どのように学んでいけば良いのでしょうか。ここでは、2つの方法をご紹介します。
理論から学ぶ
芸人さんの場合、たとえ台本があったとしても、細かな一言一言は芸人さん自身が考えていることが少なくありません。話の筋は決まっていても、返しは台本に「(リアクション)」と書かれているだけ、というケースもあります。
授業での返しは一発勝負で事前に考えるのは困難ですが、あらかじめ「型」となるパターンを知っておくことは有効です。
- ダイヤモンドオンラインの記事「「褒められたとき」に何と返す?コミュ力の高い、好かれる人の答え」
芝山大補さんが、褒められた時の返しとして「謙遜ボケ」や「もう一度言わせる」といった手法を紹介しています。 - 日経スタイルキャリアの記事「職場の雰囲気を明るく! 笑いを誘う「返し」の言葉」
中北朋宏さんが、けなされた時の返しとして「繰り返し」「例え返し」「ノリ返し」といった手法を紹介しています。
このようにお笑いの手法を解説した書籍は数多く出版されており、話し方やコミュニケーションを学びたい社会人にとっても有益です。私たち教員も「人」が相手の職業ですから、芸人さんのスキルを理論的に学ぶことは大いに役立つはずです。
耳から慣れる
もう一つの方法は、ラジオやトーク番組をとにかく聞くことです。
私自身、高校生の頃からお笑いが大好きで、特に爆笑問題さんのラジオやトーク番組、ネタ番組を録音して、何度も何度も、セリフを覚えるくらい聞いていました。
もちろん、ただ聞いていれば自然にできるようになる、という単純なものではありません。しかし、話の展開や言葉の選び方など、笑いの要素を身体に染み込ませる方法の一つとして、ラジオや番組、落語を聞くのは非常に良い訓練になると思います。
【実践編】生徒のこんな発言、あなたならどう返す?
それでは、具体的な場面を想定してみましょう。皆さんなら、どう返しますか?
- 場面1: 中学1年生、英語の授業。現在進行形を学習している最中に、ある生徒が「お腹すいたー」と発言した。
- 場面2: 単純な書き写しの作業を指示した直後、ある生徒が「何するか分からないー」と言った。
- 場面3: 特別活動や学校行事について、ある生徒が「やる意味がわからないー」とつぶやいた。
どれも授業の流れに反する、一見するとやる気のない発言です。
生徒は、「こう言うと先生は困るかな…」「どんな反応をするだろう…」と、ある種試すような気持ちで言っているのかもしれません。必ずしも本心ではないこともあります。
ここで大切なのは、怒ったり、声を荒らげたりしないこと。 むしろ、生徒と同じくらいのテンションで、あるいはボソッと小さい声で返すのが効果的です。
予想外の反応が返ってくると、生徒はニヤッとしたり、驚いた表情を見せたりして、それ以上強い言葉をかぶせてくるのをやめることがあります。話の腰を折り、興味の対象をそらすのです。
私だったら、こう返すかもしれません。
- 「お腹すいたー」
→ 「You are ハラヘリングだね」 - 「何するか分からないー」
→ 「え、眠いかお腹すいたか帰りたいの三択だと思ったのに、まさかの4つ目が出た」 - 「やる意味がわからないー」
→ 「分からない意味がわからない」
授業は「大喜利」である
生徒の突飛な発言に反応するのは、もはや「大喜利」です。 「笑点」や「IPPONグランプリ」のような番組はもちろん、今ではYouTubeやX(旧Twitter)でも多くの大喜利コンテンツに触れることができます。
大喜利の回答も理論的に分析すると、「あるある」「言葉遊び」「裏切り」など、いくつかのパターンに分類できます。大喜利を勉強することも、アドリブ力を鍛えることにつながるかもしれません。
まずは日々の授業参観の中で、「ん?今の一言、言われた先生はどう返すかな?」という場面で、実際に先生が返した言葉を記録したり、「自分ならどう返すか」をシミュレーションしたりすることから始めてみましょう。その積み重ねが、あなただけのアドリブ力を育てていきます。
まとめ:アドリブは一日にしてならず
今回は、教員のアドリブ力について、お笑い芸人さんのスキルをヒントにお話ししました。
あまり上手く言語化できなかった部分もあったかもしれませんが、「芸人さんたちの返しを学ぶことは、日々の授業に必ずつながる」と感じていただけたら嬉しいです。
ナイツの塙さんがおっしゃるように、アドリブはそう簡単にできるものでもなければ、安易にして良いものでもありません。
これはピアノや他の芸事と全く同じです。まずは授業の基本的な『型』を何度も繰り返し、無意識に実践できるまで体に染み込ませる。その盤石な基礎が自信と余裕を生み、その土台があって初めて、自分らしい自由な表現、つまり本当の意味でのアドリブが生まれてくるのです。
最初から完璧なアドリブをしようと焦る必要はありません。まずは日々の実践の中で経験を積み、「アドリブをしたいな」「できるかもしれない」と思えるようになるまで、じっくりと力をつけていきましょう。
この記事は動画「【授業で困らない】生徒の予想外の発言に神対応!教員のためのアドリブ力講座」をもとに作成しました。




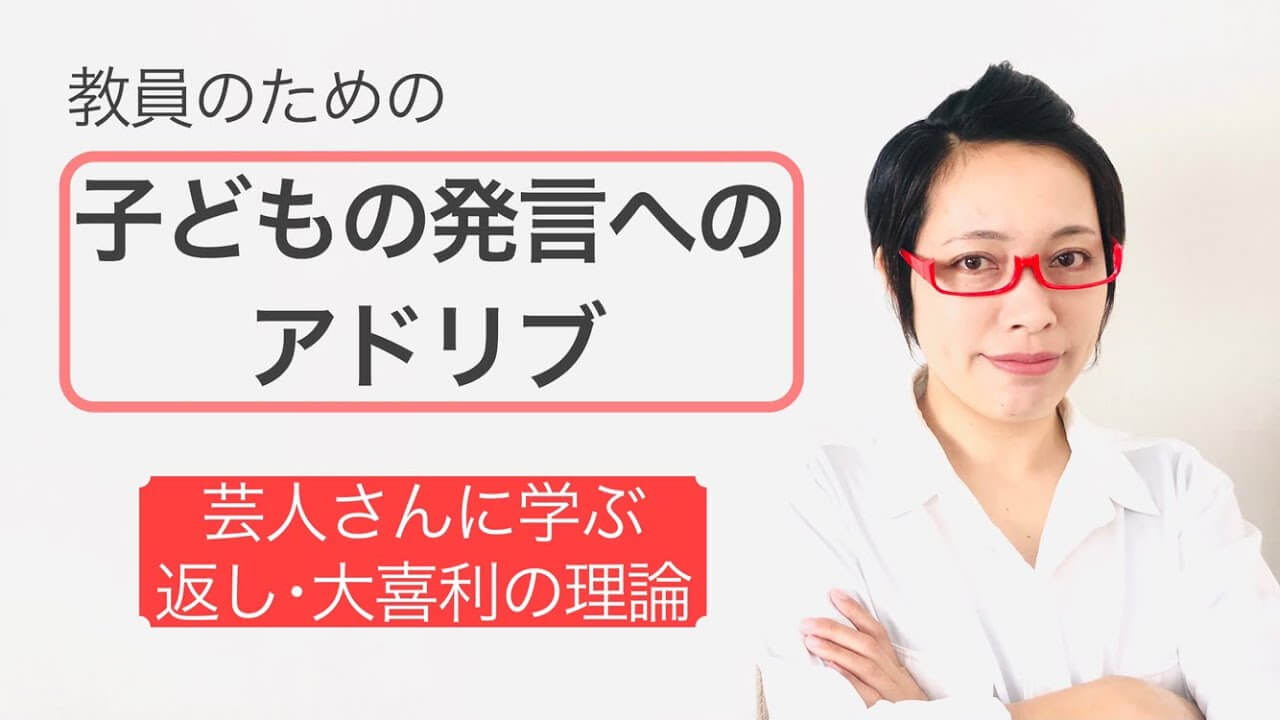


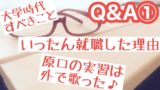


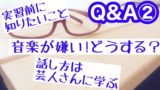


コメント