今回は、音楽授業において効果的に活用できるパワーポイントの作り方についてお話しします。
以前は黒板と板書が中心だった授業も、現在ではスクリーンやプロジェクター、パソコンなどの設備が整い、パワーポイントの利用が主流となりつつあります。
では、どのように作れば、生徒の興味を引き出し、理解を深めることができるのでしょうか。ここでは、パワーポイント作成の3つのコツをご紹介します。
「不親切なパワーポイント」で生徒の思考を引き出す
最初のコツは「不親切なパワーポイント」を作成することです。これは、以前に「音楽教員必見!生徒が集中する「ワークシート作り」3つの秘訣」という動画でご紹介した「不親切なワークシート」と同じ考え方に基づいています。

パワーポイントの利点は、情報を視覚的に豊富に提示できることです。しかし、教科書の文章や写真をそのまま載せたり、スライドの文字を読み上げるだけでは、生徒の興味を引くことはできません。スライドを見ただけで授業の内容が理解できてしまっては意味がありません。
そこでおすすめするのが、スライドをシンプルに保つことです。例えば、写真だけ、あるいは単語だけを表示するなど、生徒に「これはどんな話が聞けるのだろう?」と想像させる余白を与えることで、授業への集中力が高まります。
見やすく、聞きやすいスライド作成
次のコツは「見やすく・聞きやすい」パワーポイントを作成することです。
見やすさの工夫
教室が広い場合、最も後ろに座っている生徒にも文字や写真がはっきり見えるよう、文字サイズや画像サイズに注意を払う必要があります。
パソコン画面上で作っているだけでは気づきにくいため、実際にスクリーンに映して確認することが重要です。
また、時間帯によって日差しや教室内の明るさが変わるため、照明を調整したり、明るい色合いのデザインを選ぶといった工夫も有効です。
聞きやすさの工夫
音源をスライドに貼り付ける場合は、音量のバランスに配慮しましょう。
オンライン音源や編集した音源を使用する際、シーンによって音が大きすぎたり小さすぎたりすると、生徒の集中を妨げる原因になります。複数の音源を使用する場合は、それぞれの音量を事前に調整しておくことが大切です。
参考文献の明記を習慣にする
3つ目のコツは「参考文献を必ず明記する」ことです。
パワーポイントを作る際には、さまざまな資料を使用することが多くなります。そのたびに出典やリンク先を記録しておくことで、次年度の資料改訂や一部再利用の際に、必要な情報にすぐアクセスできるようになります。
また、外部発表や研究授業の資料として使用する際にも、出典が明記されていれば、他者にとっても理解しやすくなります。著作権の観点からも、参考文献を明記することは極めて重要です。
最後のスライドを参考文献専用のページとして用意し、常に記載する習慣を身につけましょう。
まとめ:削ぎ落としと余白が生徒の学びを深める
今回は、音楽授業でのパワーポイント作成における3つのコツをご紹介しました。情報を詰め込みすぎず、あえて削ぎ落とすことで、生徒に考える余地や、先生が語る余白を残すことがポイントです。
パワーポイントの使い方を工夫すれば、授業を大いに助ける強力なツールになります。ぜひ、自分に合ったスタイルを見つけて、より良い授業づくりに役立ててください。
この記事は動画「【音楽授業】不親切なスライドで生徒を引き込む!パワポ活用3つのコツ」をもとに作成しました。








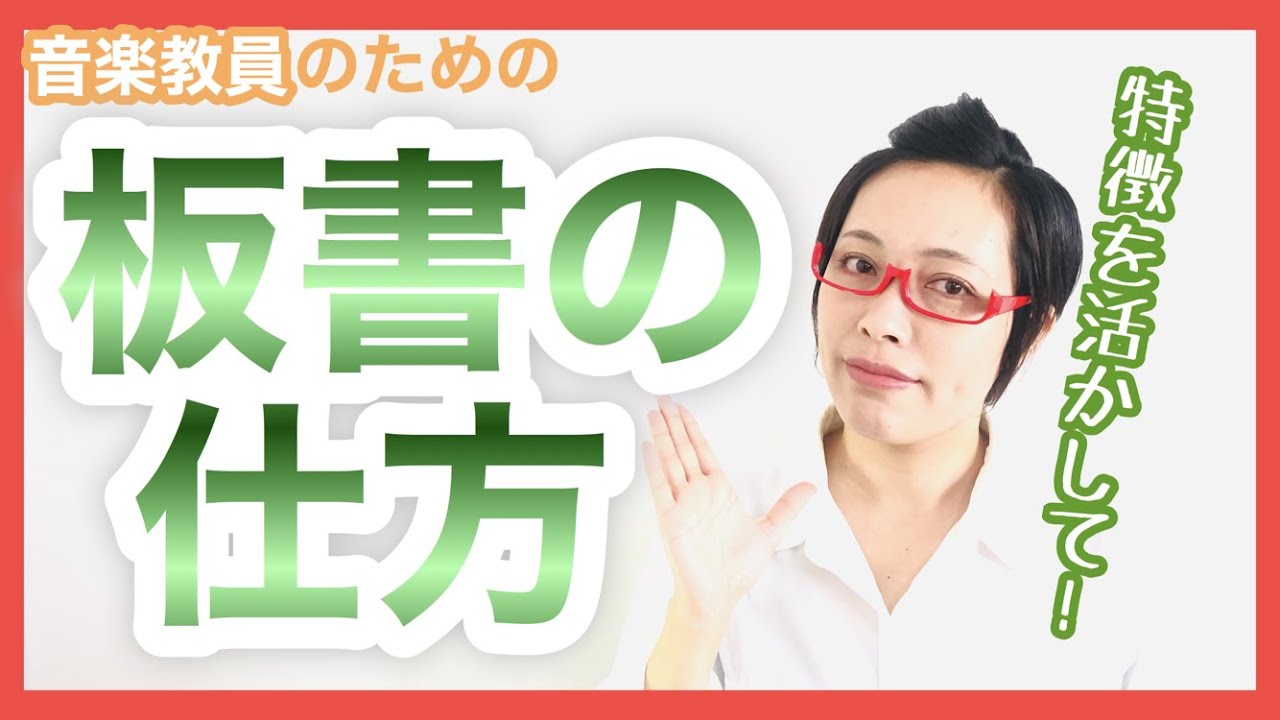

コメント