今回は「音楽の授業における板書の仕方」についてご紹介します。
今後はワークシートやパワーポイントの作り方、板書とパワポの使い分け方についても動画を公開予定ですので、ぜひ併せてご覧ください。
音楽の授業では、他教科と比べて板書が軽視されがちですが、その使い方によっては非常に効果的です。国語や数学では板書の研究が進んでおり、関連書籍も多数存在します。
では、音楽の授業ではどう活用すべきか。今回は私の考える3つのポイントをお伝えします。
無地と五線の使い分けを工夫する
最初のポイントは、「無地と五線の使い分け」です。多くの学校では、無地と五線が上下に並んだスライド式の黒板や、表裏で構成された黒板・ホワイトボードが設置されています。
授業の流れを妨げないように、黒板をひっくり返したり上下に動かしたりする時間を最小限に抑える工夫が必要です。集中力を途切れさせないためにも、事前に教室の板書設備を把握し、適切な使い分けを意識しましょう。
国語や数学のように1枚の無地黒板で完結する授業と異なり、音楽ではこうした違いを理解した上で板書を活用することが大切です。
マグネットの活用で視覚的効果を高める
次に重要なのは、「マグネットの有効活用」です。「音色」「強弱」「速さ」など、「音楽を形づくっている要素」に関するマグネットを用意しておくと、話の流れに応じて視覚的に内容を補足でき、非常に便利です。
また、強弱記号や楽語に加え、「強い」「弱い」「美しい」「激しい」といった形容詞を記載したマグネットを使用している先生もいます。こうした工夫は、授業の理解を深める助けになります。
ただし、マグネット作成時には西洋音楽に偏りすぎないよう注意が必要です。楽語や記号は西洋音楽に由来するものが多いですが、他の音楽ジャンルや楽器にも対応できる共通語の活用を心がけましょう。
最も実用的なのは、学習指導要領の末尾にある「覚えるべき単語や楽語」がまとめられた図を参考にすることです。
音符や記号は正確かつ丁寧に書く
最後のポイントは、「音符や記号の丁寧な書き方」です。音楽の先生が1人しかいない学校では、音符やト音記号を書くのはその先生のみです。そのため、音符はしっかりと丸を書いて棒を立て、ト音記号もト音から丁寧に書くことが大切です。
雑になったり、走り書きしたりせず、美しく整った板書を心がけましょう。実際に、ト音記号をきれいに書いただけで生徒から「おぉー!」と驚かれた経験もあります。ト音記号を正確に書けることも、一つの音楽的才能です。
私たちにとっては当たり前のことでも、生徒にとっては学校で唯一の音楽の専門家が示す姿勢そのものです。音楽を正しく伝えるという立場からも、丁寧な板書が求められます。
まとめ:板書の可能性を再確認
今回は、音楽の授業における板書の仕方について、以下の3つのポイントを紹介しました。
- 無地と五線の使い分け
- マグネットの有効活用
- 音符や記号の丁寧な書き方
近年ではPowerPointを活用した授業が主流になりつつありますが、板書も活用次第で非常に効果的な手段です。今後、パワーポイントの作り方や、板書との使い分けについても動画で解説する予定ですので、そちらもぜひ参考にしてみてください。
この記事は動画「音楽の授業で差がつく!板書のコツ3選【教室の黒板をフル活用】」をもとに作成しました。




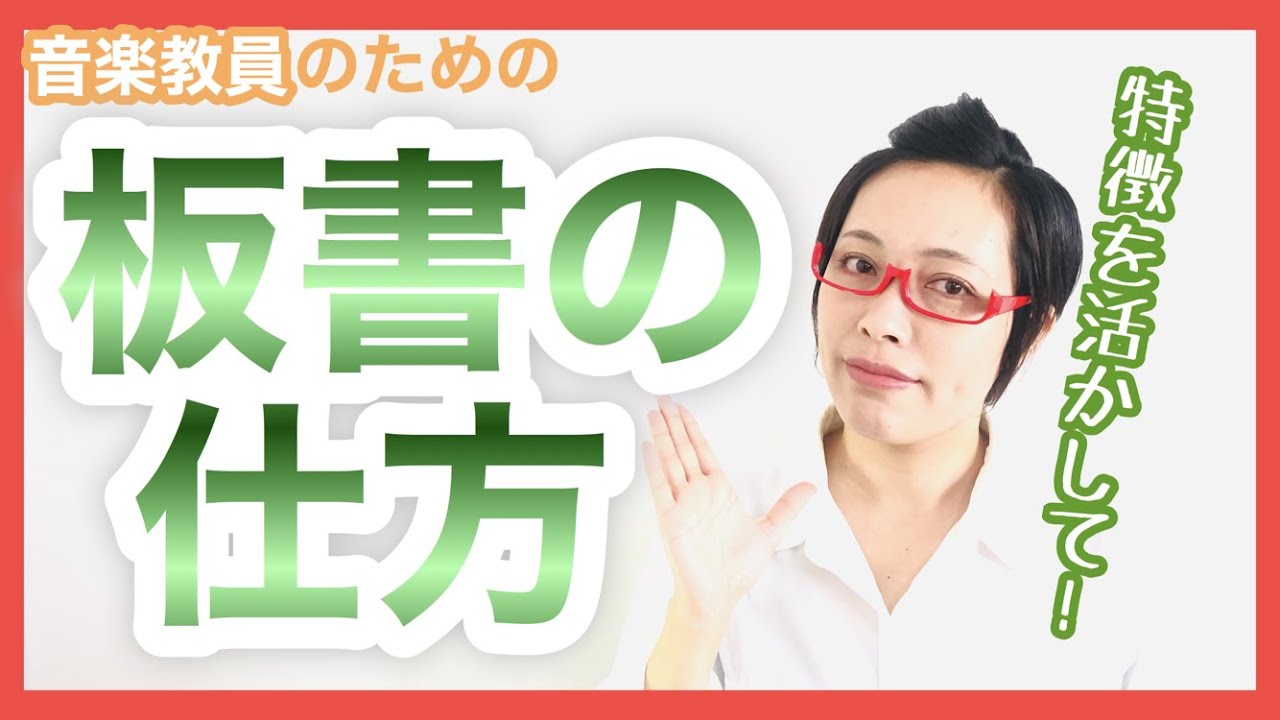

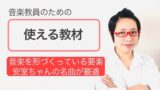
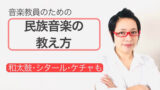



コメント