学校現場では、教科指導、学級経営、校務分掌、部活動など、教員は一人で多くの役割を担っています。勤務年数を重ねても「この担当は初めて」という状況は誰にでも起こりうるため、初任者や若手の先生だけでなく、すべての教員にとって「相談相手」の存在は不可欠です。
しかし、『こんな時、誰に相談すればいいんだろう?』『一人教科だから、校内に話せる相手がいない…』と、一人で悩みを抱え込んでしまう先生も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな先生方のために、学校内・学校外・そして書籍やSNSを含めた相談相手の見つけ方について、具体的な場面ごとに解説します。
この動画の他には以下の動画もおすすめです。
「学校を支える人(生活編)」では学校用務員・学校事務員・スクールアドバイザー・スクールソーシャルワーカー・スクールロイヤー・スクールサポーターを紹介
「学校を支える人(楽器屋さん)」「学校を支える人(調律師さん)」では特に音楽科に限定して紹介
併せてご覧ください。
まずは身近な存在から!学校内の相談相手
最も身近で頼りになるのが、校内にいる先生方です。担当業務ごとに、誰が適切な相談相手になるのか見ていきましょう。
教科の相談 – 「一人教科」でも孤立しないために
音楽科のように一人教科の場合、校内に同じ教科の先生がおらず、相談相手がいないと感じるかもしれません。しかし、視点を変えれば、必ず力になってくれる先生がいます。
- 美術科の先生: 同じ芸術教科として、指導方法や評価について助言をくれるでしょう。
- 保健体育や技術家庭科の先生: 同じ実技教科として、一斉指導と個別指導の違いなど、共通する悩みについて相談できます。
また、これらの教科の先生とは、文化祭などの行事を見据えた年間指導計画についても情報交換が可能です。
学級の相談 – 最も頼りになる存在は「学年」にあり
学級経営に関する悩みは、同じ学年の先生方、特に学年主任が最も頼りになる存在です。
学年主任は学年全体の状況を把握しているため、今後の展開を予測したり、トラブル発生時に子どもの背景を理解していたりします。日頃から子どもの様子などを雑談レベルで話しておくことが、お互いのために良い関係を築く鍵となります。
また、そのクラスや学年を以前に担当していた前任の先生も大きな力になってくれます。ただし、前任の先生も新しい学級が始まれば多忙になります。隠しているわけではなく、単に余裕がないだけなので、こちらから主体的に情報を聞きにいく姿勢が大切です。
校務分掌の相談 – スムーズな引き継ぎのコツ
初めて担当する校務分掌では、前任者が最も効果的な相談相手です。まずは前任者が校内にいるか確認しましょう。
もし異動や退職で不在の場合は、同じ分掌や部で一緒に動いていた先生に、なるべく早く全体像を聞いておくことが重要です。
例えば、「文化祭は秋だから、準備は夏休みからでいいだろう」と考えていたら大間違いです。展示品の製作や部活動の準備など、夏休み前から教科や部活動は動き出します。昨年度の資料や書類がデジタルフォルダか紙ファイルで残っているはずなので、作成された日付に注目し、早め早めに準備を進めましょう。
特に、新しい取り組み(例えば、合唱曲の決め方を少し変えるなど)を行う際は、一度で承認されるとは限りません。反対意見が出ることも想定し、事前に相談しておくことが肝心です。
視野を広げる!学校外の相談相手
校外にも、心強い相談相手を見つける機会はあります。
同じ市区町村の教科の先生とのつながり
同じ市区町村の音楽科の先生とは、以下のような場でつながりを持つことができます。
- 定期的な研究会や集まり
- 部活動の大会や練習試合
- 市区町村主催の演奏会や展示会の企画・運営
こうした機会に日々の相談事をできる先生を探し、「今後連絡をとってもいいですか?」などと声をかけて、つながりを作っておきましょう。ただし、学級経営や校務については学校ごとのルールや文化があるため、校外の先生に相談するケースは少ないかもしれません。
「同期」というかけがえのない存在
校外でのつながりの中で最も強いのは、初任者研修で出会った同期です。はじめの1、2年を共に過ごした同期は、何でも話せる心強い友となります。数年経ち、異動やライフイベントで疎遠になることはあるかもしれませんが、最初の数年間の支えは非常に大きなものです。
書籍やSNSから専門的な情報を得る
対面での相談だけでなく、書籍やSNSも貴重な情報源となります。
教育書 – 読み継がれる名著から最新情報まで
教科・学級・校務分掌に関する情報は、教育書に豊富にあります。大きな書店に行けば、その種類の多さに驚くでしょう。
読み継がれる名著から最新の研究、素晴らしい実践例まで、多くの知見を得ることができます。現在はオンライン書店や電子書籍も充実しており、どこに住んでいても情報を集めることが可能です。
SNS – 「#教師のバトン」と情報活用能力の重要性
SNSにも教育に関する情報は多く存在します。以前は現職教員がSNSで発信することにためらいがありましたが、2021年3月に文部科学省が始めた「#教師のバトン」を機に、現職教員による発信が目に見える形で増えました。
ただし、書籍やSNSの情報は、あくまで発信者個人の考えや実践に基づいています。私たちが子どもたちに指導するのと同様に、教員自身もその情報を吟味し、自身の状況に合わせて取捨選択する冷静な視点が不可欠です。
学習指導要領で示されている「情報活用能力」は、まさにこのことを指しています。情報を集める際、
- 目の前の先生に聞くのか
- 書籍や論文を読むのか
- Googleで検索するのか
- SNSのハッシュタグで収集するのか
まず「何が最もふさわしい情報手段か」を選ぶ力が必要です。そして、その情報の発信者が、自分の悩みを解決するのにふさわしい相手かを見極める必要もあります。これは、対面であろうとオンラインであろうと変わりません。
まとめ:困ったときは、素直に「困ってます」と発信しよう
学校の規模や人員構成は様々で、誰がどの業務を担当するかは多岐にわたります。だからこそ、勤務年数にかかわらず「初めて」は誰にでも訪れます。
相談相手を見つける一番のコツは、一人で抱え込まず、素直に、謙虚に『困っています』と周囲に伝える勇気を持つことです。
教員は、困っている人に手を差し伸べたくなるという大切な本能を持っているはずです。たとえ望む解決に直結しなくても、必ず解決へのヒントや道筋を示してくれます。一人で抱え込まず、まずはその悩みを声に出して発信することから始めてみましょう。




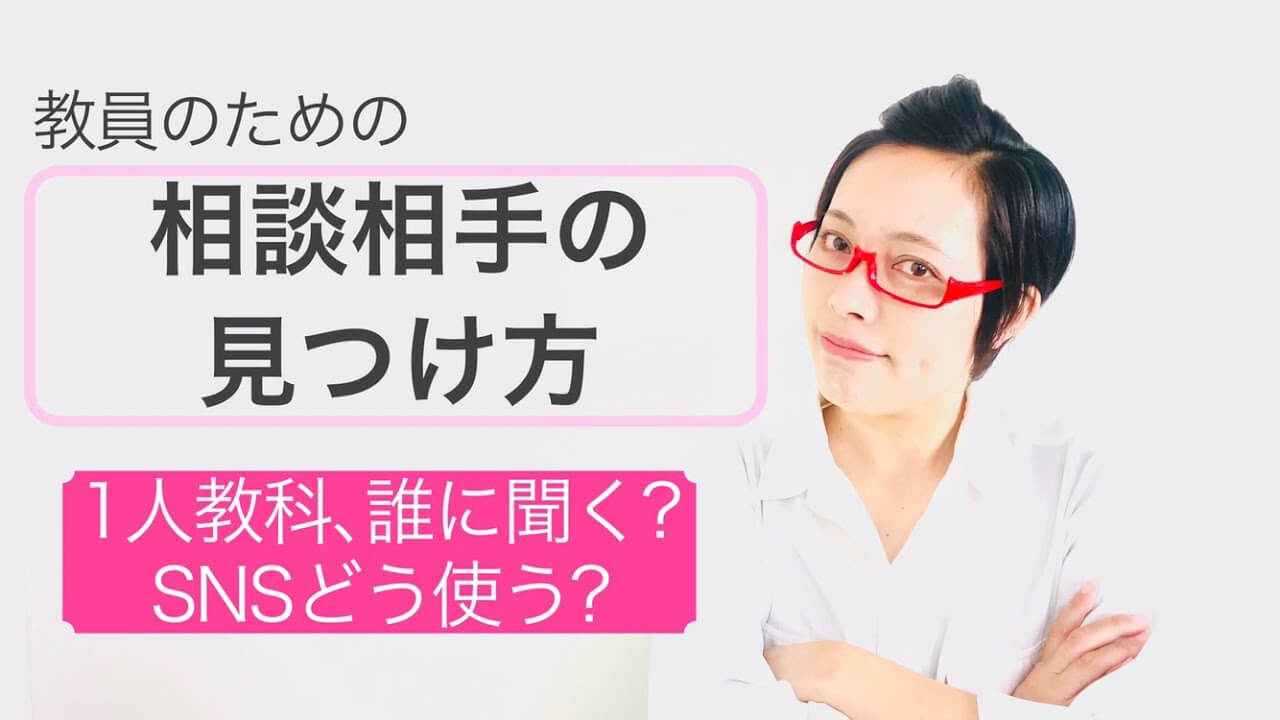












コメント