授業の中で聞こえる声には、教員の指導の声、子どもの発言や話し合いの声、そして私語・おしゃべりがあります。
この私語は一概に悪いものとは言えません。ある時は授業の流れを作ってくれたり、教員を救ってくれる鶴の一声となることもありますが、授業規律の観点ではルール違反となり、最悪の場合は授業や学級そのものの収拾がつかなくなることもあります。
本記事では、私語の定義を整理し、発言と私語の線引き、そして不要な私語を未然に防ぐための具体的な対策について取り上げます。学級や学校の状態、授業内容、教員の指導方針や発達段階、教科などによって状況は異なりますので、一例としてお読みください。
この記事は、次のようなことを知りたい方に是非ご覧頂きたい内容です。
▶どこからが私語なのか整理をしたいという方
▶私語か私語ではないかの線引きが難しいと感じている方
▶授業中の子どもの私語をやめさせたいという方
この動画の他には
年度初めが肝心な授業規律。どう伝えて、どう守らせるか。そして、破られた時にどうするかという話をしています。
中学生に「関わろうとする」と「関わる」の違いとは?、子ども扱いと大人扱いの塩梅。そして、やまない私語をおもしろがって分析して学級だよりに載せたという話をしています。
併せてご覧ください。
対策1:どこからが私語?発言との線引きを明確にする
授業中に子どもが声を出してよい場面とは、教員の発問に対する回答や意見、話し合いでの発言などです。音楽科では歌唱、保健体育科では競技中のかけ声といった教科の特性もあります。
中学生の授業では、挙手して発言するよりも、指名されたり思いついた子が自由に発言する場面が多く見られます。こうした自由発言が授業の流れをつくり、発問の展開につながることもあります。
例:
- 「ブルタバ(モルダウ)はどの国を流れる川でしたか?」という問いに「チェコ」と答えた子どもに対して、「チェコだけでしたか?」「作曲者は誰でしたか?」と発展させる。
- 「よさこいが日本全国に広まって地元の人はどう思いますか?」という問いに「有名になってうれしい」と答えると、「地元をきちんと答えられますか?」「本当に嬉しい人だけでしょうか?」と展開させる。
こうした発言は教員にとってありがたいものですが、年度初めの授業規律では「雑音なし」として楽音以外の声を厳しく制限する場合があり、矛盾が生じます。
また、自由発言は得意な子や声の大きい子が有利になりがちで、目立ちたくない子やじっくり考えたい子、ワークシートに書きたい子などを別の方法で見取る必要があります。
難しいのは、不要な私語とも取れる声やボソッと呟いた声が、授業の流れを作る鶴の一声になる場合です。この見極めが非常に難しいため、次は線引きについて考えていきます。
対策2:発言と私語の線引きをどう行うか?
ベテラン教員や経験を積んだ教員は、子どもの自由発言を活かしながら、授業や単元の目標に沿って臨機応変に授業を進める技術を持っています。しかし、教育実習生や若手教員にとって、この線引きは簡単ではありません。
私は教育実習生を指導してましたが、実習期間中に発言や私語をコントロールできた教育実習生はいませんでした。
わかりやすい線引きの方法として、以下のような工夫があります:
- 発言できる時間を明確に区切る
- 教員が「意見がある人?」「分かった人?」と発言を促す
- 学級のルールに基づいた発言様式を採用する
小学校では、起立して椅子を机に入れ、定型文で発言してから着席する流れが見られます。中学校では、座ったまま指名されて発言するのが一般的で、発達段階の違いが関係しています。
次の段階としては、教員が特定の子どもを指名したり、目線や手の合図で発言を促すことです。また、事前に机間巡視を行い、ワークシートの記述や活動の進捗、子どもの得意不得意を把握することが重要です。
線引きが明確であれば、教員にとっても発言をコントロールしやすく、子どもにとっても安心して発言できる環境になります。
対策3:危険な私語への対応
崩壊状態にある学級や授業は、さまざまな観点から見られますが、分かりやすい一つの指標が「授業に関係のない私語の多さ」です。
授業に関係のある発言から脱線し、関係のない話題へと広がっていくケースもあります。
例として:
- 「和太鼓の叩く面は何の動物でしょう?」という問いに「牛」と答えた子に対し、別の子が
- 「牛丼食べたいな」
- 「この間すき家に行ったよ」
- 「鬼滅の刃のコラボ始まったよ」「鬼滅のあれ見た?」と展開
このような脱線はわずか数秒で起こり、収拾がつかなくなります。
教員が「響凱の体についている太鼓は小鼓なので牛ではなく馬皮ね」といった形でキャラクターを使いノリツッコミで戻す方法もありますが、これはベテランや心に余裕がある教員でないと難しい技術です。
最初から授業と無関係な私語が始まる場合もあり、これはより深刻です。
こうした危険な私語を防ぐためには、授業規律の徹底が最も効果的です。
具体的な取り組み例:
- 授業規律を教える際に「音とは何か?」という理科的視点から楽音・雑音の違いや文化的な捉え方の違いを説明し、「私語は雑音。音楽の授業には不要」と伝える。
- ルールは年度当初に示すだけでなく、継続して共有し、破られたときにはルールに基づいて考えさせる。
- 発言や指名の工夫、子どもが今すべきことを明確にすることで私語の隙を与えない授業構成にする。
素晴らしい授業では、あっという間に50分が過ぎたように感じることがあります。子どもたちも同様に、集中して課題に取り組んでいれば私語が出にくくなるのです。
危険な私語をする原因は子どもではありません。
関係のない私語が出たとき、子どもに対して不満を抱くのではなく、自分の授業構成に問題がなかったかを冷静に振り返ることが求められます。もちろんイラッとすることもありますが、指導者としての姿勢が大切です。
おわりに:私語対応は経験がものを言う
私語への対応は、経験に裏打ちされた指導技術が問われる場面です。「私語をやめさせたい」と思ったとき、原因は一つではなく複合的に存在します。
自分の授業を俯瞰して見直すこと、他の教員に授業を参観してもらい助言を受けることも効果的です。
また、「私語のない授業」には、教科の特性、教員の性格、授業規律の構築など、さまざまな要素が関係しています。他教科や他の教員の授業から学ぶ姿勢を大切にしましょう。
この記事は動画「【若手教員必見】授業が崩壊する前に!私語を止める3つの実践策」をもとに作成しました。




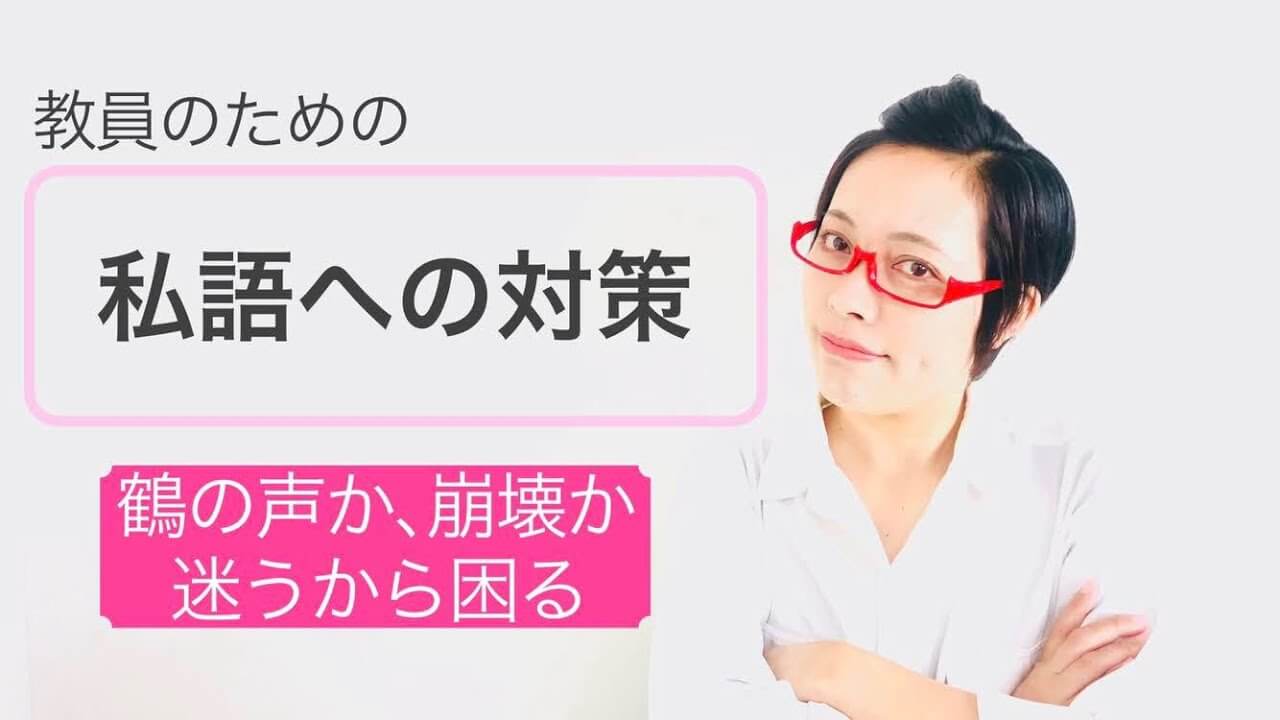








コメント