こんにちは、音楽教員歴10年の原口直です。
このサイトでは、音楽教員のための指導や生活に役立つ情報を発信しています。
今回は、「音楽室の準備」についてお話しします。音楽室は音楽の先生にとっての“戦場”とも言える場所。どのように整えるかによって、授業のやりやすさが大きく変わります。
音楽室の作り方は人それぞれで、正解はありません。学校の構造や備品によっても可能なこと・不可能なことがありますので、あくまでヒントとしてお聞きください。
授業を想定して音楽室を準備する
音楽室の準備で最も大切なことのひとつは、「授業を想定する」ことです。
年間授業計画を立てた際に、どの領域を中心に据えるかを明確にすることで、授業しやすい教室の形が見えてきます。
歌唱を主とする場合
- 合唱や独唱がしやすい隊形が重要
- ピアノの位置、楽譜や譜面台の配置に配慮
- 生徒の動き(前後左右)を考慮
器楽を主とする場合
- 楽器の配置が最優先
- 動かしにくい大きな楽器の位置
- 指導者の近くに配置すべき
- 楽器コンセントの位置に注意
- 合奏時の配置や、準備・片付けのしやすさも考慮
創作を主とする場合
- 録音機器や音響機材の使いやすさが重要
- 教室全体の音響環境を配慮
鑑賞を主とする場合
- スクリーンや黒板の位置、光の入り方などが重要
- PowerPointを使うのか、視聴覚教材中心か
- スピーカーや黒板の活用法に応じた配置
- 生徒が長時間座る環境の整備
スクリーンと黒板の位置関係に注意
今や授業でスクリーンを使用しない日はないほど、スクリーンは黒板以上に重要な要素となっています。
- PowerPointや視聴覚教材が生徒の見やすい位置か
- 窓の位置により明るさのバランスを調整
- 高すぎず低すぎず、全生徒から視認可能な位置に設置
- スクリーンと黒板の配置関係を考慮
- 黒板を覆うようにスクリーンがある学校も
- 黒板の脇にスクリーンがある場合も
- スクリーン固定式/黒板移動式、その逆など、使用頻度に応じて配置を決定
備品(机・椅子・譜面台など)の確認と工夫
学校によって、机や椅子の有無は様々です。
机
- クラス人数分の机がない場合も
- 机付きの椅子を使用している学校もある
- 備品の有無をまず把握
- 足りない場合は副校長・教頭・周囲の先生に相談
- 倉庫に余っている可能性も
- 別教室から譲ってもらえることも
- 新規購入も相談可能
椅子
- 背もたれあり/机付き/丸椅子/重い/軽い椅子など様々
- 丸椅子は机や台としても使えて便利(話し合いもしやすい)
- パイプ椅子から丸椅子へ変更する際は、理由を管理職に明確に伝える
譜面台
- 常備している学校もあれば、机代わりに使う学校も
- 譜面台をあまり使用しない場合は教室の片隅に置く程度で十分
- 書く作業には硬めのファイルを下敷きとして生徒に配布
- クラス人数分を基準に備品を配置すると管理しやすい
- 予備もあると便利だが、個数管理しやすい配置にする
掲示物の工夫
掲示物には教員の個性が出ます。
- 音楽の要素の言葉のマグネットを常に貼っておく
- 作曲家の肖像、音楽史、歌詞の掲示など学校ごとの工夫
- 授業効率化に役立つ掲示も有効
- 「椅子が必要か」「譜面台が必要か」「隊形」などを掲示
- 生徒が教室に入った段階で準備ができるようにする
私は下記のように、「椅子・譜面台が必要か」「どのような隊形で座って欲しいか」を常に掲示しておきました。授業に来た生徒がこれを見て、「今日はこのように座る、椅子が必要だ」と把握していました。
授業開始とともに授業が始められるような工夫…これも掲示物でいくらでもできると思います。

ピアノは音楽室の象徴
- 音楽室には基本的に1台のピアノが設置されている
- ピアノは常にピカピカに磨いておく
- ピアノを大切にする姿勢は、生徒への教育にもつながる
- ピアノの上に物を置かないように徹底
- 初任時に学んだ指導として実践している
その他:音楽室を定期的に見直す
- 常設物(キーボード、大型打楽器、棚、ラジカセなど)の必要性を4月のタイミングで再検討
- 必要な時に必要な分だけ出すスタイルに
- 使わない棚は処分も検討
- 教員自身が居心地の良い空間を作ることも大事
- 加湿器、好きなキャラクターや香りなど
- 職員室・準備室・研究室も居心地の良い空間に
まとめ:この機会に音楽室を見直そう
今回は音楽室の準備についてお話ししました。
新任の先生や新しい学校に赴任する先生はもちろん、引き続き同じ学校で勤務する先生も、ぜひこの4月の機会に音楽室を見直してみてください。今見直さなければ、1年間ずっと同じ状態のままになってしまいます。自分にとっても生徒にとっても心地よい、効率的な音楽室を目指していきましょう。
この記事は動画「【音楽教員必見】音楽室の作り方完全マニュアル|新年度準備で授業が変わる!」をもとに作成しました。










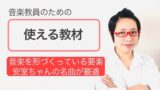




コメント