今回は、1年間の授業を円滑に進めるために重要な「初回授業のガイダンスとアンケート」についてお話しします。
初回の授業をしっかり準備・実施することで、年間を通じた授業運営がとても楽になります。逆に初回を失敗すると、その後の1年間が非常に苦労するものとなってしまいます。
ガイダンスの3つのポイント
自己紹介
生徒と「初めまして」と出会う場であるガイダンスでは、まず自己紹介を行います。自分がどのような教員であるかを伝えることが大切です。
以前に紹介したキャラクターづくりの動画「音楽教員のキャラクターづくり5つの秘訣|生徒との距離をグッと縮める方法」でも触れましたが、どんな音楽が好きなのか、どんなキャラクター、スポーツ、YouTubeが好きなのかなどを話すことで、生徒に親近感や信頼感を持ってもらうことができます。
第一印象は非常に重要です。パワーポイントなどを活用して、生徒にわかりやすく、覚えてもらえるように工夫しましょう。
音楽に対する哲学
少し難しいかもしれませんが、音楽や音に対する考え方を伝えることも大切です。
例えば私は初回の授業で「楽音」と「雑音」について話しました。
楽音は心地良い音、雑音は心地良くない音。同じ「声」という音でも、合唱中に聞こえる声は楽音ですが、私が話している最中に歌い出す声は雑音です。
音楽室では楽音だけが許されるということを、初めに強く伝えます。その後の授業でも「雑音なし!」と注意する場面があり、1年生は面白がって真似をすることもありました。
インパクトのある話を通して、自分がなぜ音楽を教えるのか、音にどう向き合っているかを伝えることが重要です。
良いことと悪いことの明確化
ガイダンスでは、「これは許す」「これは許さない」という線引きを明確に提示しましょう。
私の場合、持ち物や提出物の忘れについても厳しく伝えています。
例えば次のように話します:
「音楽の授業は中学校ではとても少ない。英語や数学の4分の1や5分の1しかない。つまりワークシート1枚は英語のワークシート4〜5倍に相当する。だから忘れてはダメ。必ず締切までに提出すること。一時間一時間、絶対に忘れ物をしないでください。」
また、都立高校の入試では実技教科の評定が2倍で計算されることも伝えますが、評価ばかりを強調するのではなく、ワークシートや提出物の重要性の一部として話すようにしています。
音楽室内のルールも初回で共有します。
たとえば、ピアノや大型パーカッション、機材に触って良いのかどうか。短い休み時間はダメだが長い休み時間ならOKなど、具体的に説明します。
部活動で楽器の扱いに慣れている生徒には許可するが、知らない生徒は触ってはダメ。どうしても触りたいなら相談して教える、というように伝えます。
これらの内容はレジュメとして配布し、ファイルなどに綴じておくと、ルール違反があった際に「ここに書いてあるでしょ」と確認させることができます。小さなことに見えますが、1年を左右する大切な共通認識です。
アンケートの活用方法
初回授業ではアンケートも行います。
私は毎年、1年生の4月に実施しています。内容は以下の通りです:
- 小学校で印象に残った曲や行事
- 音楽系の習い事(楽器やダンスなど)
- ピアノのレベル(習っている年数や現在弾いている曲を記入)
ピアノの習熟度は、合唱伴奏ができるかの判断材料になります。「エリーゼのために」を一つの基準としており、これが弾ければ1・2年生の合唱曲の伴奏は可能と考えています。
また、生活の中で音楽とどう関わっているかについても聞きます。「ラジオを聴きますか?」「音楽番組を見ますか?」「劇場やコンサート、ライブなどに1年以内に行きましたか?」という形式です。
さらに、「おすすめの音楽を3つ書いてください」と記入させます。これにより生徒の嗜好がわかり、会話の糸口にもなります。
最後に、「この人知ってる?」という欄で、約50名の音楽関係者(バッハやモーツァルト、日本の演奏家・作曲家、J-POPアーティスト、伝統芸能の従事者、ボーカロイド歌手など)について、知っていれば〇、知らなければ×、名前だけ知っていれば△をつけさせています。
受験と音楽の間にある問題が「ピアノをいつまで続けるか問題」です。「受験・学業とピアノの習い事は両立できるか(やめどきを判断する曲とは?)」の動画で、音楽教員としての私の考えをお話しています。

まとめ
今回は、初回授業で実施するガイダンスとアンケートについて紹介しました。始めが肝心です。
ガイダンスは生徒との信頼関係や生活指導の基盤にもなります。1年間を通じたスムーズな授業運営のために、ガイダンスとアンケートをしっかり計画・準備して臨みましょう。




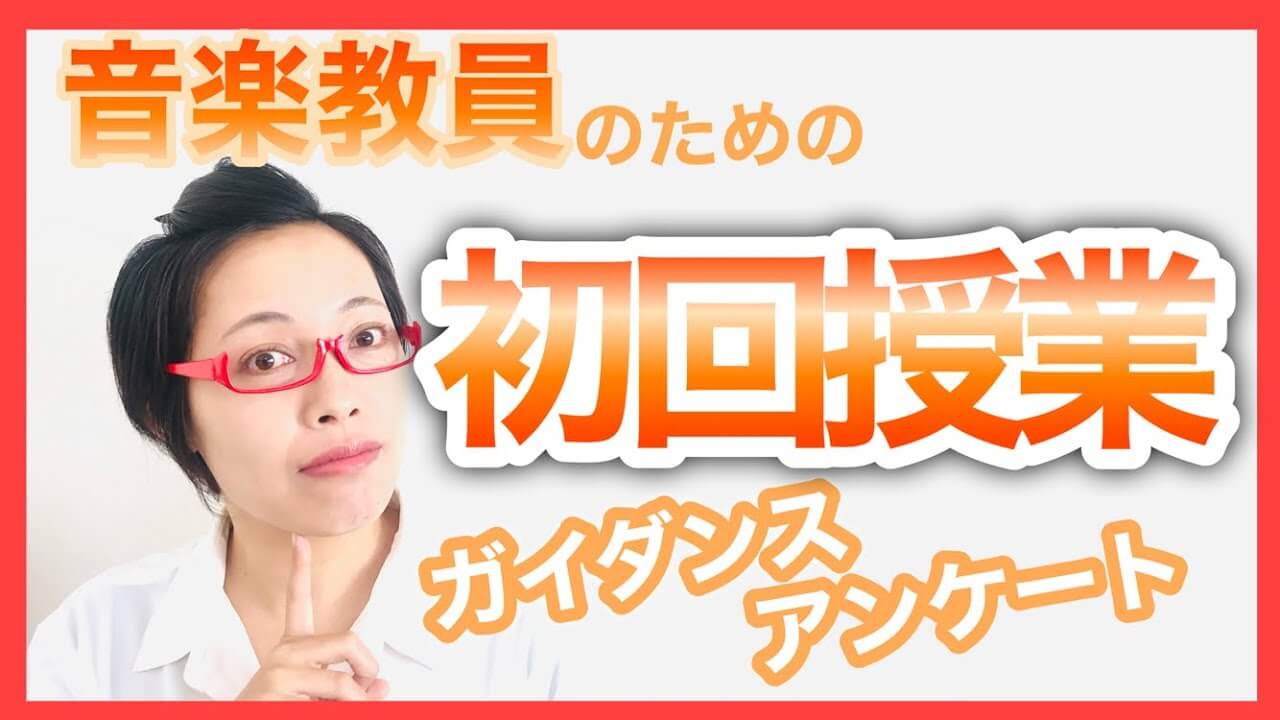








コメント