中学校の音楽授業は、週に1〜2回しか行われないことが多く、その限られた時間の中で全ての生徒の名前と顔を一致させるのは非常に困難です。
ここでは、私が10年間の教員経験の中で実践してきた「生徒の名前の覚え方」について、3つの具体的な方法をご紹介します。
方法1:男子は「覚えようとしない」でも自然に覚えられる
最初の方法は、一見矛盾しているようですが「男子は覚えない」です。実際には、男子の名前や顔は意識しなくても自然に覚えられることが多いのです。
その理由のひとつが、合唱のパート練習です。音楽の授業では、教員が男子パートに入って指導する場面が多く、そこで彼らの顔や声、性格に自然と触れる機会が生まれます。このような関わりの中で、無理に覚えようとしなくても記憶に定着していくのです。
男子は無理に覚えなくても自然と覚えるので、まず男子を覚えない。これが1つ目です。
方法2:役職のある生徒と部活動の生徒を優先的に覚える
次に紹介するのは、「役職のある生徒を優先して覚える」方法です。
授業の進行に関わる指揮者、伴奏者、パートリーダーなどは、早めに顔と名前を一致させておくことが重要です。
また、音楽係や音楽委員などの役割を持つ生徒も同様に優先して覚えましょう。これに加えて、吹奏楽部やオーケストラ部、合唱部、軽音楽部など、音楽系の部活動に所属している生徒は、週に何度も顔を合わせるため、自然と記憶に残りやすいです。
このように、まずは関わりの深い生徒から覚えていくことで、効率よく全体に広げていくことができます。
方法3:生徒の「好きな音楽」と結びつけて覚える
三つ目の方法は、「生徒の好きな音楽を手がかりに覚える」ことです。
私は、初回の自己紹介で生徒に好きな音楽を話してもらったり、記入してもらったりしています。
すると、ジャニーズ、K-POP、ボカロなど、それぞれの生徒の趣味が明らかになります。これらを好む生徒は、自分の好きな音楽について積極的に話しかけてくることが多く、コミュニケーションを通じて顔と名前が一致しやすくなります。
このように、音楽を通じた関心を手がかりにすることで、単なる暗記ではなく、生徒との関係性を築きながら覚えることが可能になります。
おわりに:日々の積み重ねが鍵
私は、定期試験の監督中に「このクラスの生徒をどれだけ覚えているか」を自分自身に問いかける習慣を持っていました。試験監督をしながら、生徒一人ひとりの名前を心の中で確認することで、記憶の定着度を確認することができます。
生徒の名前を覚えることは、日々の指導だけでなく、担任の先生との情報共有にも大いに役立ちます。すぐに全員を覚えるのは難しいかもしれませんが、無理をせず、確実に覚えていくことが大切です。
生徒との信頼関係を築く第一歩として、名前を覚える努力を日々の習慣に取り入れてみてください。
この記事は動画「【教員必見】「覚えない」から始める!生徒の名前を自然に覚える3つの方法」をもとに作成しました。




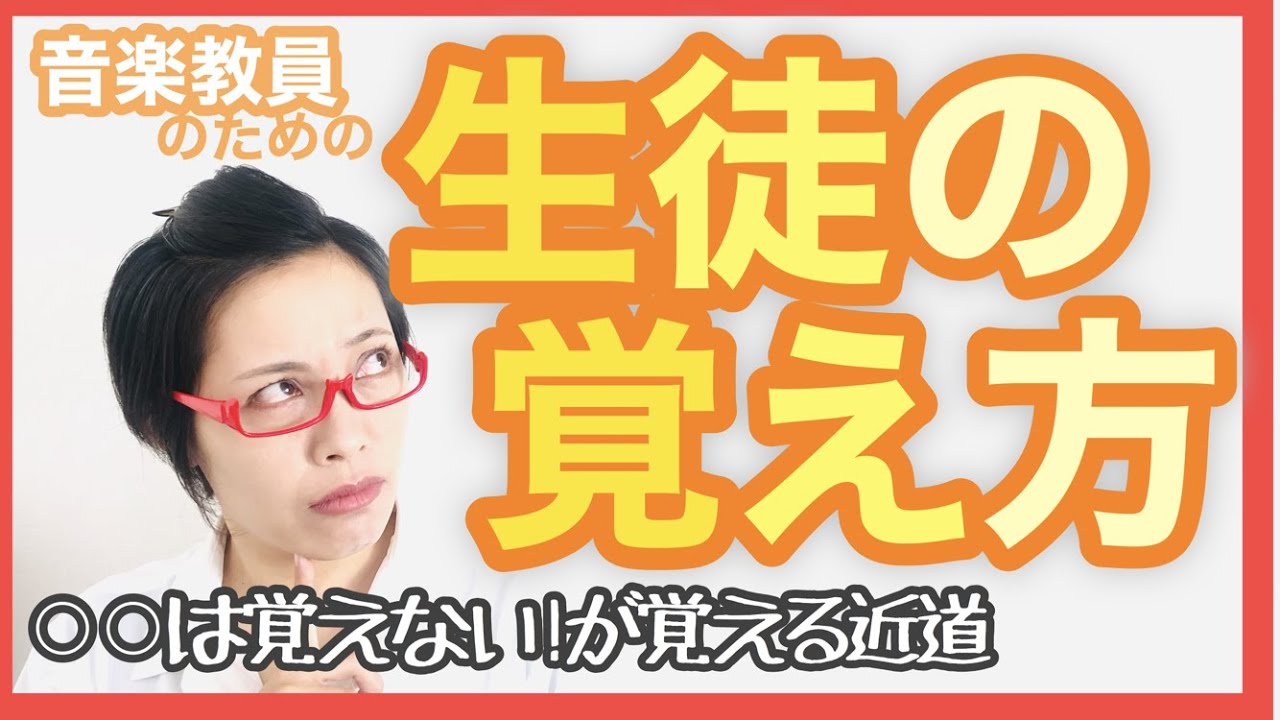







コメント