こんにちは。このサイトでは、音楽教員のための指導や生活に役立つ情報を発信しています。今回は「副教材」についてお話しします。
ここで言う副教材とは、教科書以外に用いる教材のことです。教科書は無償で配布されますが、副教材は保護者に購入していただく必要があるため、その選定には特に注意が必要です。
この記事では、副教材の選び方や気を付けるべきポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。
副教材選びでまず確認すべきこと
予算の確認
副教材を選ぶ上でまず大切なのは予算です。市区町村によって、副教材にかけられる予算や実際に使える金額が異なります。自分が使いたい教材があっても予算を超えてしまうと購入できませんので、十分に注意しましょう。
例年の傾向を把握
また、例年の副教材の傾向を知っておくことも重要です。特に新任で赴任した場合、前年にどのような副教材が使われていたかを確認しておきましょう。前年と同じ教材を使う場合や、3年間継続して同じ教材を使うこともあります。その点も踏まえて慎重に選びましょう。
副教材の4つのタイプ
今回は、副教材を4つのタイプに分けて解説します。
- ワーク系
- 資料系
- 楽譜系
- ファイル類
著作権への配慮
ワーク系、資料系、楽譜系すべてに共通する注意点として、著作権への配慮があります。
コピー自体は法律上認められている場合がありますが、作成者に不利益が生じるような使い方は避けるべきです。見本資料をコピーして使用する際には、十分に注意してください。
ワーク系副教材・資料系副教材の選定ポイント
教科書内容の把握
まず、教科書で事足りる場合は教科書を活用するのが最善です。教科書に何が掲載されていて何が不足しているのかをしっかり把握しましょう。授業全体の3分の2程度で活用できるかが選定のポイントです。
ワークの活用度
数学や英語のようにワーク全体を使用する教科と違い、音楽ではすべてのページを使わないことが多いため、無駄になるページがないか確認して選びましょう。
調べ学習への活用
また、調べ学習に活用できるかどうか、1人1冊必要かどうかも検討しましょう。例えば、図書室に代用可能な資料があれば、必ずしも全員分を購入する必要はありません。
楽譜系副教材の選定ポイント
合唱曲集のポイント
近年はさまざまな合唱曲集が発売されています。選定の際に注目すべきポイントは以下の通りです。
- 掲載曲数:合唱コンクールの選曲にも利用するため、掲載曲数は重要な判断材料です。
- 掲載曲の傾向:NHKコンクールの課題曲が掲載されているものや、最新曲・過去の名曲が含まれるものがあります。
- J-POPアレンジ:最近はJ-POPをアレンジした合唱曲の収録が増えており、その選曲が生徒の需要や教師の好みに合っているか確認しましょう。
- 歌い継がれる名曲の掲載:「大地讃頌」や「時の旅人」など、昔から歌い継がれている曲が掲載されているかも重要です。
- 特色ある楽譜:アカペラ曲やゴスペル曲など特色ある内容が掲載されたものもあります。自分の目や耳で確認して選ぶことが大切です。
- 有名な先生の推薦:「〇〇先生が選んだ」や「〇〇先生が協力した」といったうたい文句が付いたものもあります。
ファイル系副教材の選定ポイント
大きさと素材
ファイルの大きさや素材も重要な選定ポイントです。楽譜やワークシートのサイズ(A4、A3、B5、B4など)に合わせて選びましょう。初めに選んだファイルが、1年間使う資料の大きさに直結します。
ファイルの種類
ファイルの種類にも注目しましょう。
- パンチ穴タイプ
- クリアフォルダータイプ(楽譜を入れたまま書き込みが可能なものもあり、少し高価)
使用シーンの考慮
机がない環境で使用する場合は、プラスチック素材のファイルを選ぶと、座って書きやすくなります。
色の選定
ファイルの色も工夫の余地があります。クラスカラーや学年カラーに統一してもよいですし、他教科と被らないようにあえて異なる色を選ぶ手もあります。実情に合わせて選んでください。
まとめ:音楽の副教材の選び方
今回は、副教材の選び方についてお話ししました。
市区町村によっては、選定した副教材を区や市に申請する必要があります。その際は、なぜその教材を選んだのか、絶対に必要なのか、授業でどう活用するのかについて明確なビジョンを持って説明できるようにしておきましょう。
この記事が、副教材選びの参考になれば幸いです。
この記事の内容は動画「音楽授業の副教材、どう選ぶ?4つのタイプと注意点を徹底解説」をもとに作成しました。






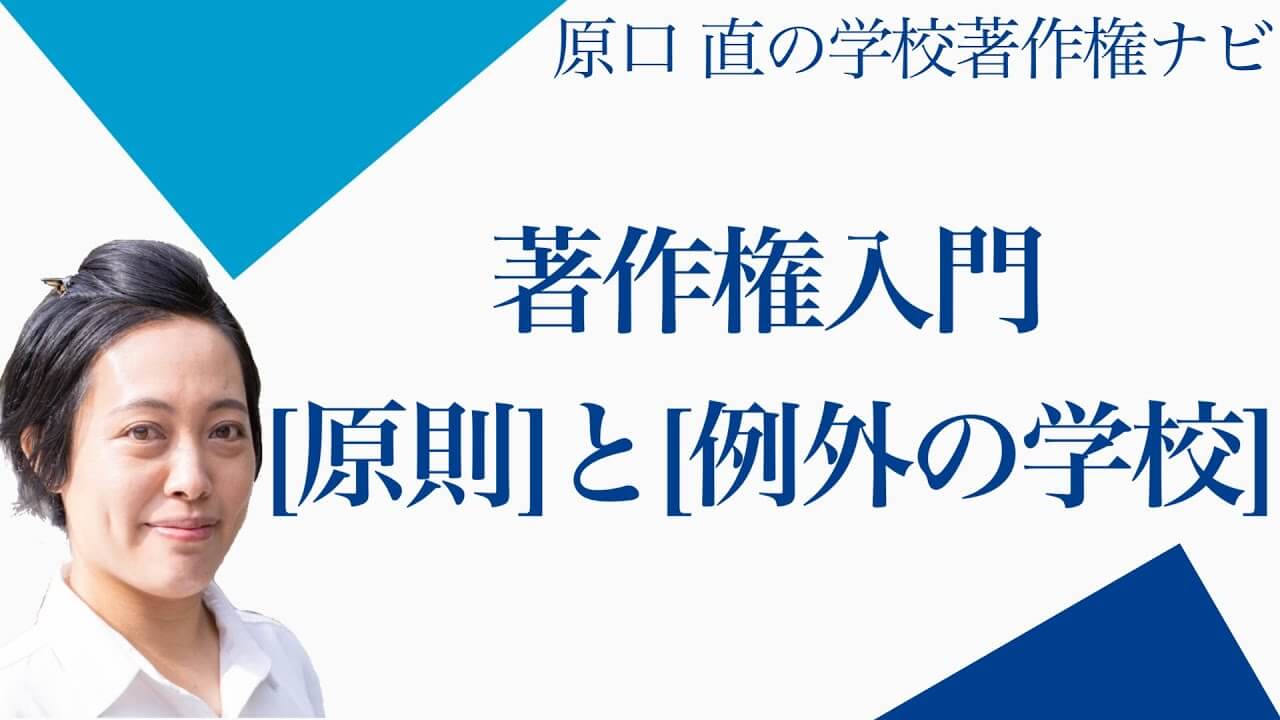












コメント