今回のテーマは「生徒と仲良くなる方法」。
授業時間が限られている中で、生徒とどのように関わり、距離感を保つかについてお話しします。
特に初任者や教育実習生の皆さんにとっては、生徒と仲良くなりたい、好かれたいという思いが強いと思います。生徒との関係は、教員にとって大きなやりがいの一つです。
他には、
教員は日々様々な人と関わっていきます。様々な人に好かれるにはどうすればいいか。そういったことを考えるヒントを話しています
音楽という教科の先生としてどのようなポイントでキャラクターを作ったらいいか、もしくは持っているキャラクターを活かしたらいいか、ということをお話しています。
興味のある方は是非ご覧ください。
全員に好かれようとしないことの重要性
最初のポイントは「全員に好かれようとしない」ことです。
一見矛盾するようですが、これはとても大切な考え方です。クラス全体を広く浅く知る努力は必要ですが、心から仲良くなれる生徒は全体の1割程度で十分です。例えば、1クラスに3〜4人いれば良いと考えましょう。
社会人になっても、心を開ける同僚は多くありません。自分が生徒だった頃を思い返しても、本音を言える友達はそう多くなかったはずです。
中学・高校では教科担任制が主流で、生徒はさまざまな教員と関わります。その中で、誰か一人でも「この先生なら話せる」と思ってもらえる存在になれれば、それだけで十分です。担任でなくても、図書館司書や養護教諭といった立場でも構いません。「好かれようとしない」姿勢が、生徒との自然な関係構築につながります。
学校図書館の話:【全教員に知ってほしい】教員のための学校図書館・司書教諭活用のススメ
養護教諭の話:【初任者・実習生に知ってほしい】養護教諭・学校医・スクールカウンセラー・栄養教諭の役割
「なんでも好き」はNGワード
次に大切なのは、「なんでも好き」と言わないことです。
生徒との共通点を見つけるうえで、音楽の話題はとても有効です。しかし、「なんでも好きです」と答えると、逆に個性が伝わらず、会話のきっかけを失ってしまいます。
自分の好みをはっきりさせることが、生徒との信頼関係の第一歩です。
私のおすすめは「好きなものを3つ」と「苦手または知らないものを1つ」用意しておくこと。ジャンルや楽器、アーティスト、作曲家など、形式は問いません。自分のパーソナリティを言葉で伝えられる準備をしておきましょう。
好きを語るための3つの切り口
「好きなものを3つ」選ぶ際には、次の3つの観点を意識すると効果的です:
- 一般ウケ:多くの人が知っている曲やアーティスト。
- マニアック:一部の人にしか知られていないが、自分が強く好きなもの。
- 意外性:先生がそんなものを好きなの!? と思わせるようなもの。
この3つの切り口をバランスよく組み合わせることで、生徒の興味を引き出すことができます。
私の例では、
- 一般ウケ:「劇団四季やミュージカルが好き」
- マニアック:「リップスライムが大好き」
- 意外性:「東海オンエアが好き」
という組み合わせです。
生徒がどこかに反応してくれれば、それが会話のスタートになります。たとえ全部知らないと言われても、それはそれで話題を広げるチャンスになります。
おわりに:自分の「好き」を大切に
生徒と仲良くなる方法」として、
- 全員に好かれようとしない
- 「なんでも好き」は避ける
- 「好きを語る」ための3つの工夫
という3つのポイントを紹介しました。
私自身、すべての生徒に好かれていたとは思っていません。しかし、「この先生、ちょっと面白いな」と思ってくれる生徒がいれば、それで十分です。そう感じてくれる生徒が、言葉や態度で示さない場合もあるでしょうが、自分の「好き」を発信することで、自然な関係が生まれてきます。
教員として、自分の好きなものを大切にし、それを生徒に伝えることが、信頼関係を築く第一歩になります。ぜひ、今回紹介した方法を参考に、生徒との関係づくりに役立ててください。
この記事は動画「全員に好かれなくてOK!信頼される先生になる3つのヒント 」をもとに作成しました。




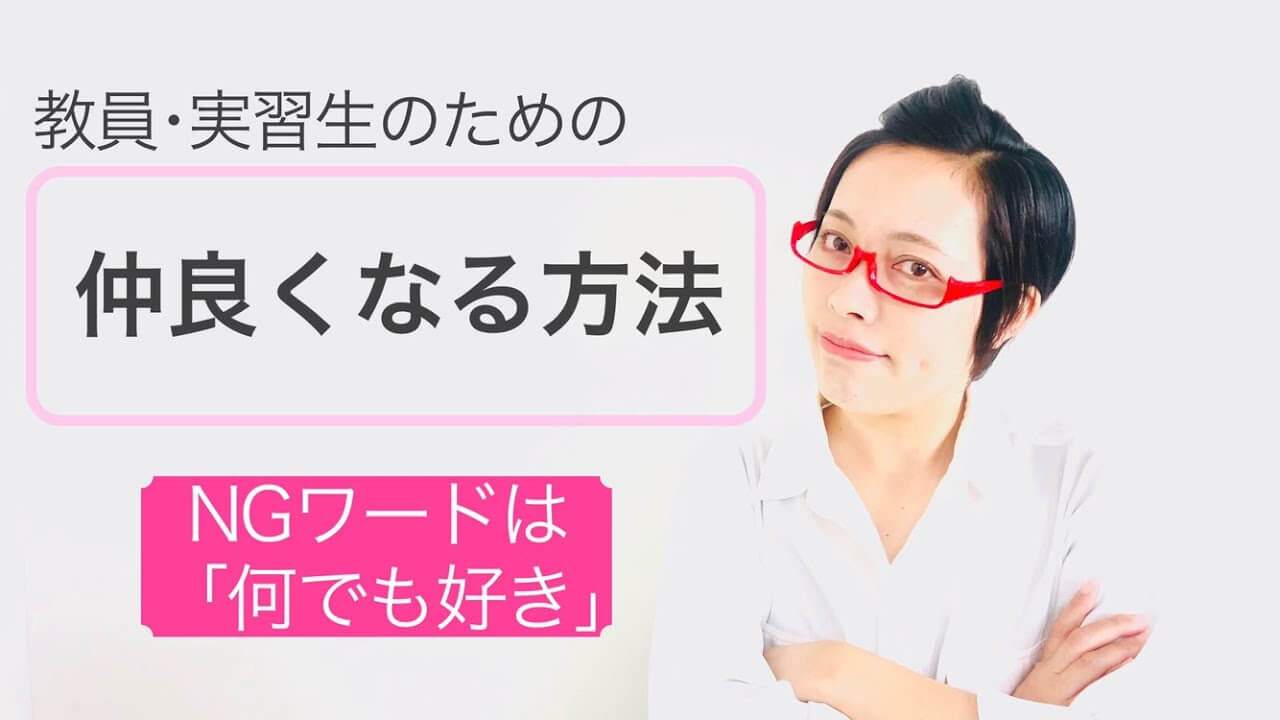










コメント